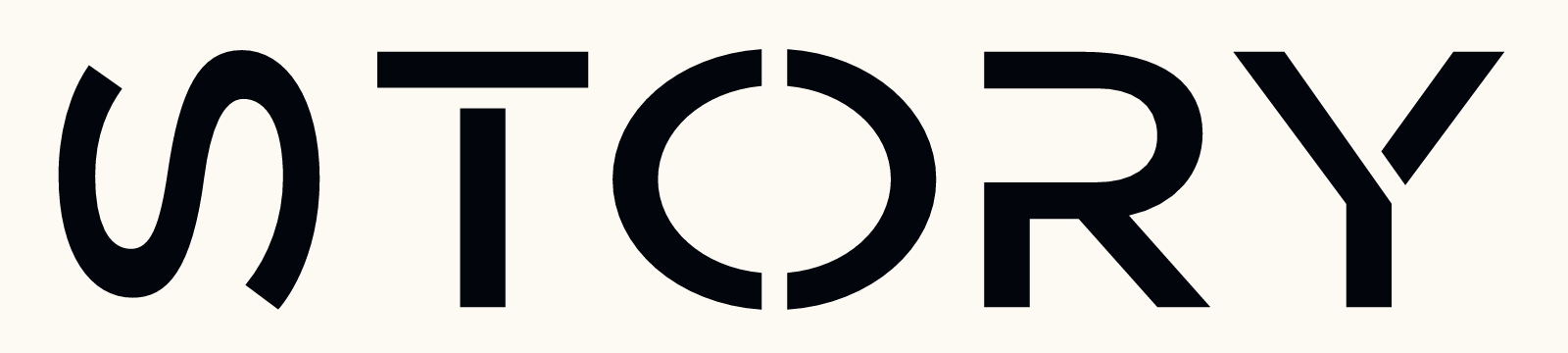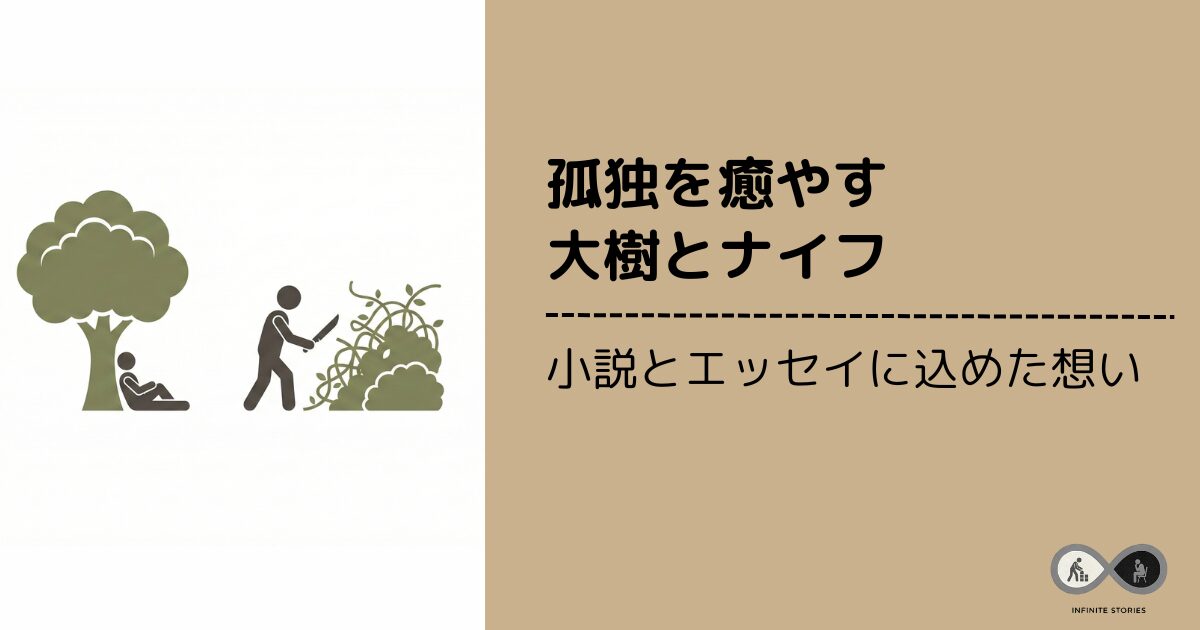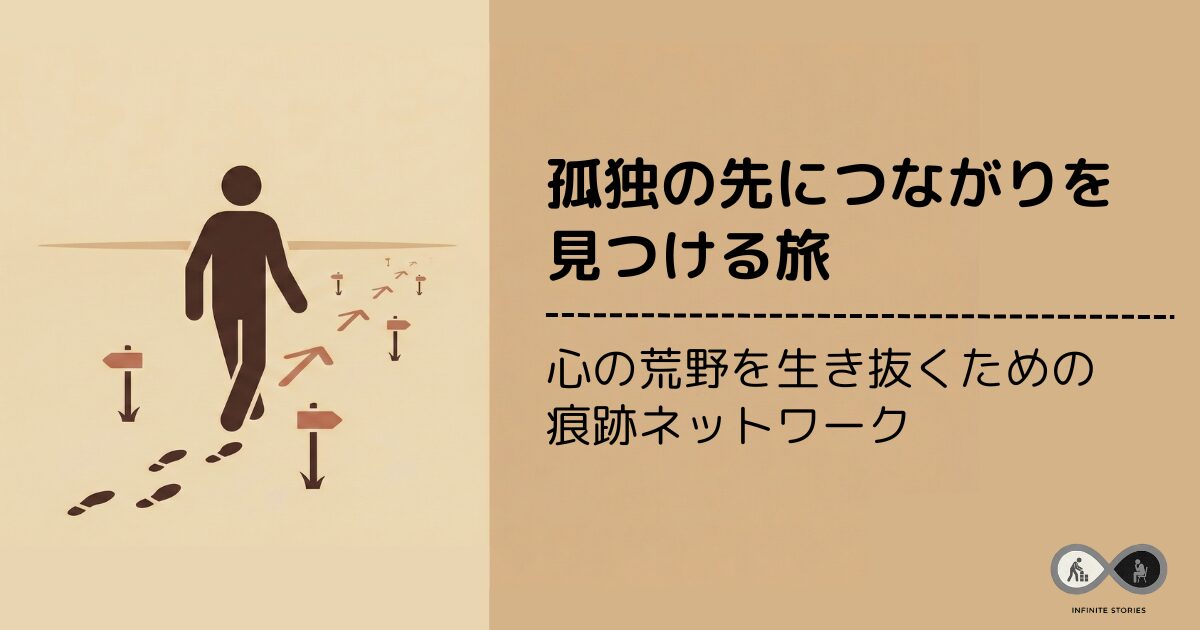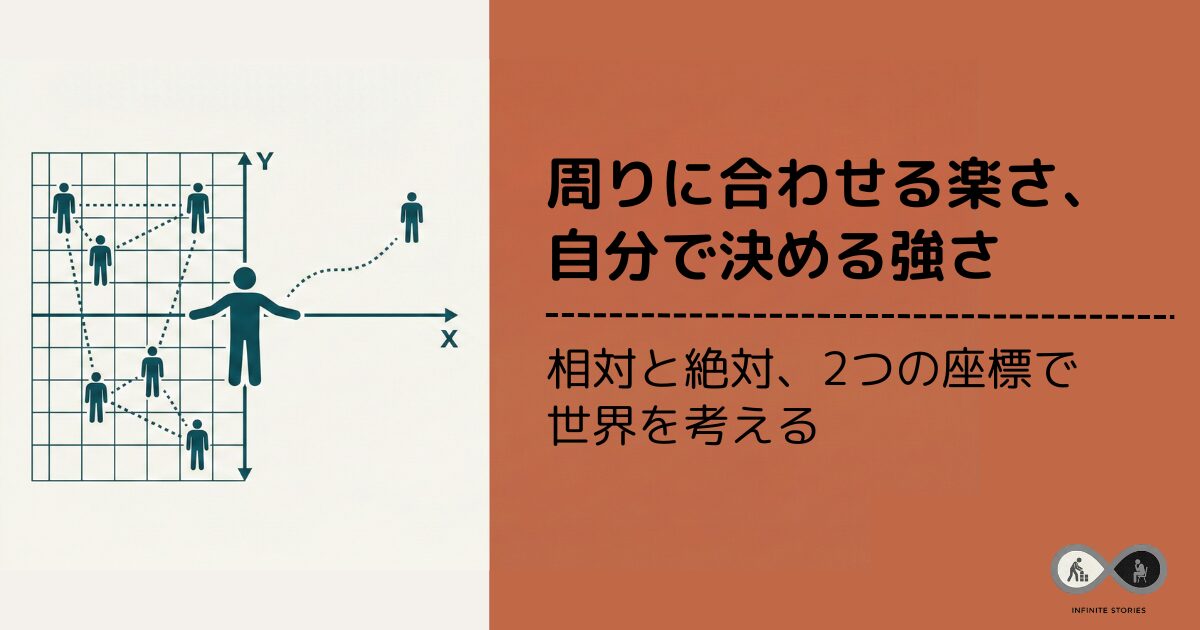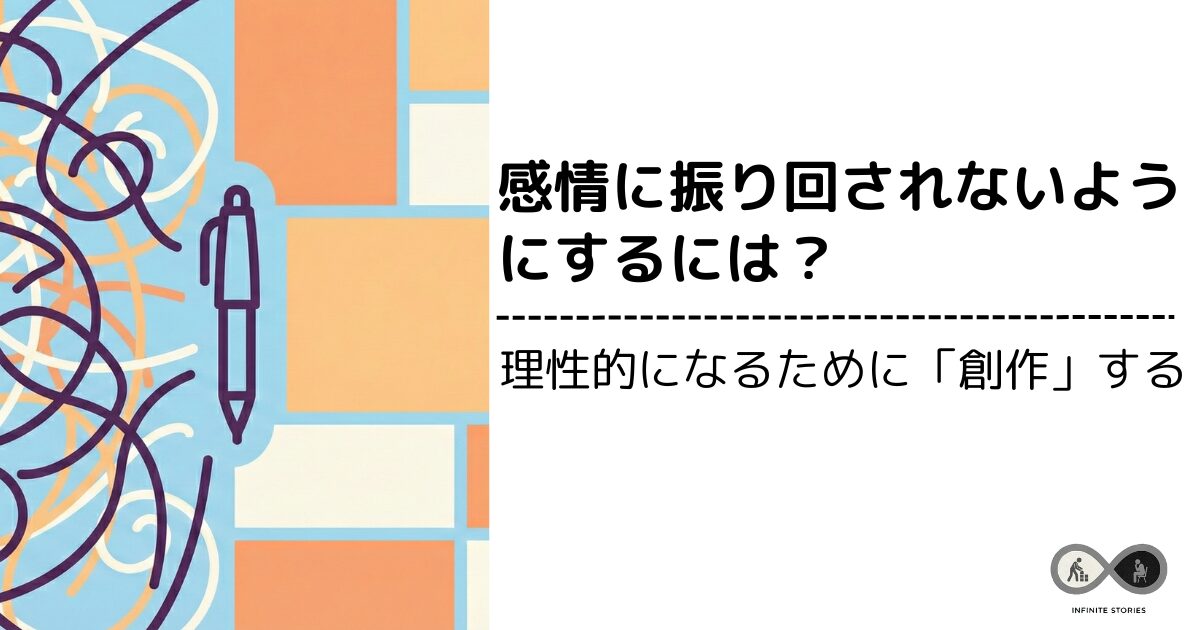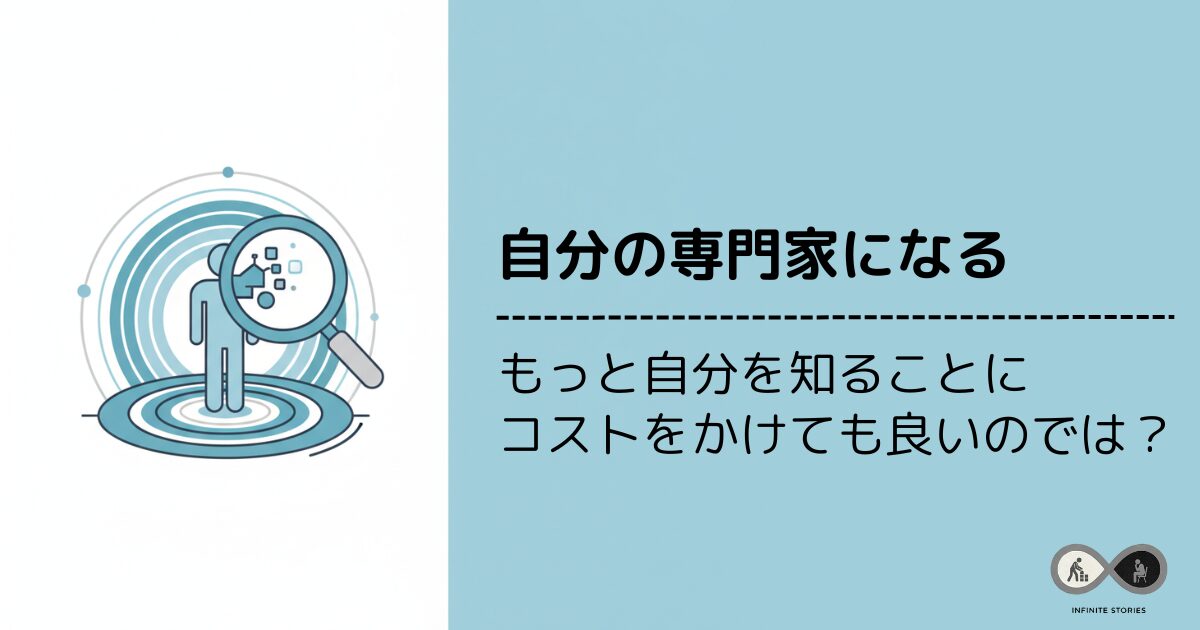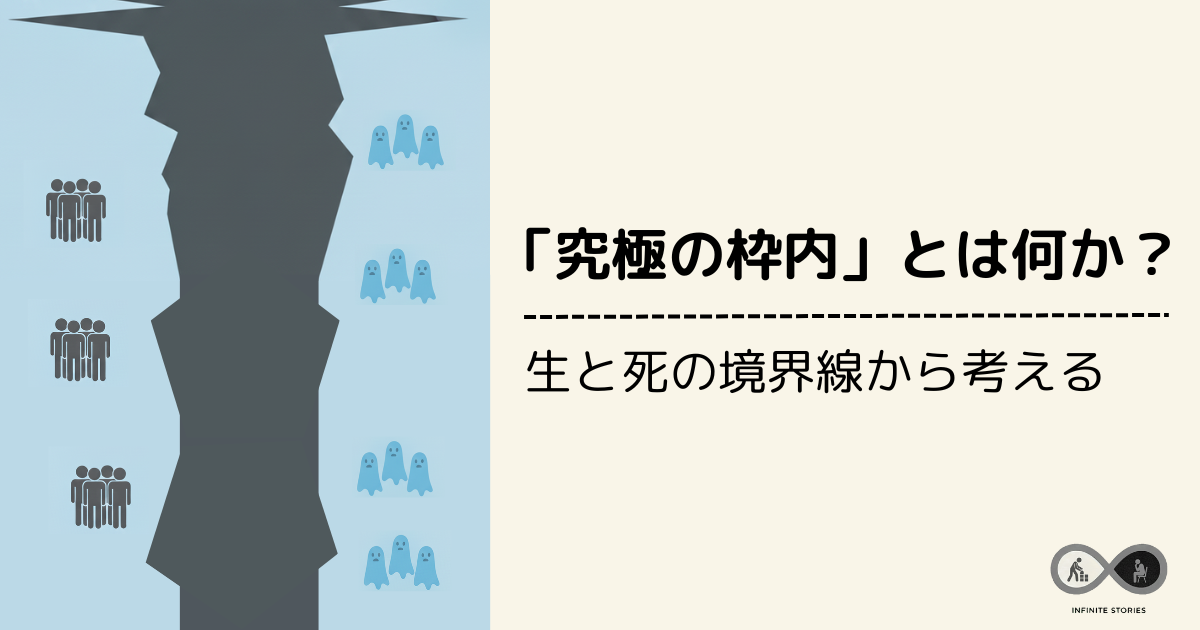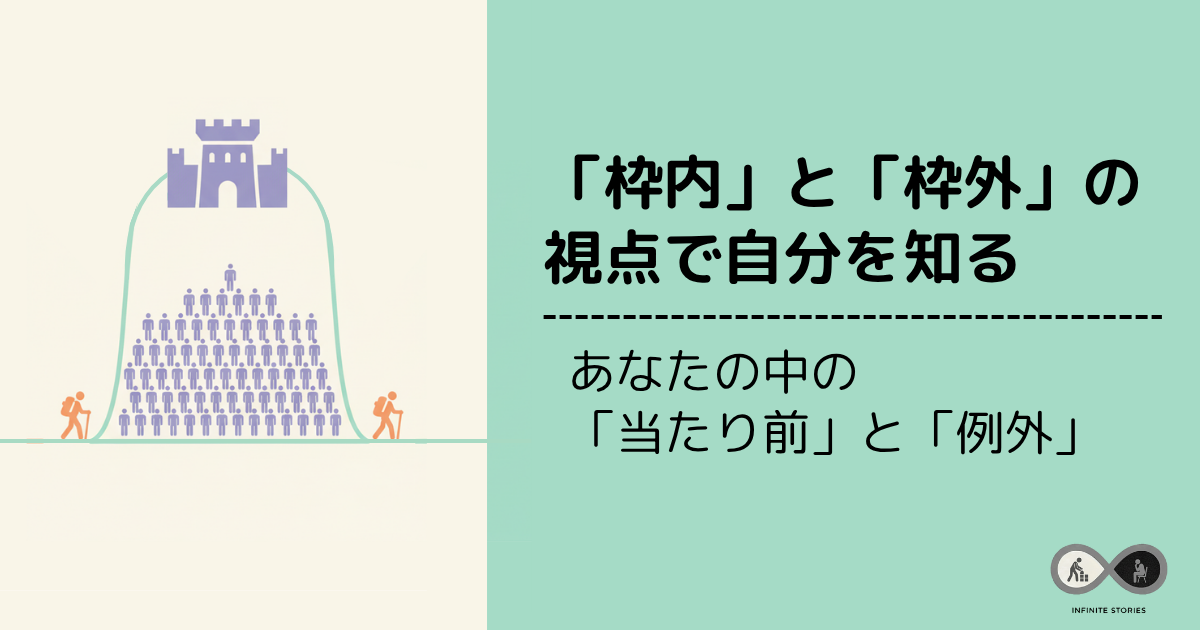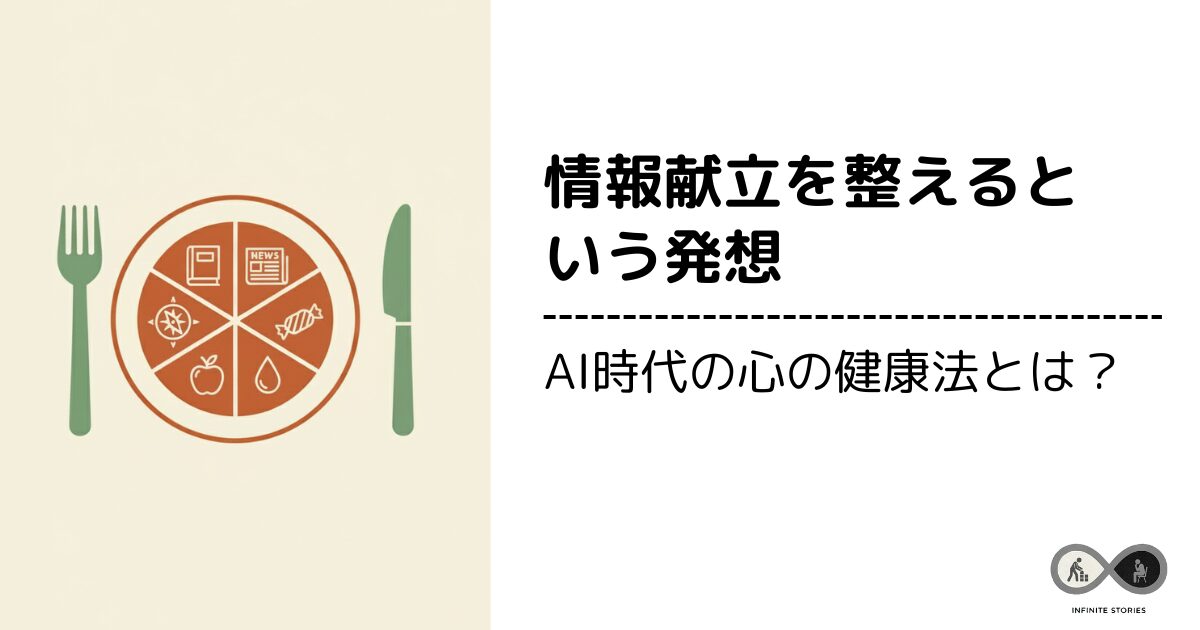『人生は運次第』という言葉に隠れる真実:捉え方で物語は変わるのか?

一言サマリー
「人生は運次第」という言葉の背後にある因果論的思考と、本当に運だけで決まる運否天賦の世界との違いを考察し、なぜ人は理由づけを求めるのかを探ったエッセイです。
要点まとめ
- 「人生は運次第」という言葉は実は運任せではなく、結果から原因を推測する因果論的思考
- 本当の運否天賦の世界なら、誰にでも平等にチャンスがあるため、むしろ希望があるはず
- 人は悪い出来事が続くと「たまたま運が悪かった」ではなく「不幸な星の下に生まれた」と思いやすい
- 「努力は報われる」という考えも、たまたま運が良かったと思いづらいために生まれる
- このような因果論的思考は、公正世界仮説のように時に人を傷つけてしまう
- このように人は理不尽な現実を受け入れるより、何らかの理由を見つけるほうが心理的に安心しやすい
音声コンテンツはこちら
notebooklmによる音声概要
人生って運が大きく関わると思いませんか?
なぜなら、どんなに頑張って築き上げたものでも、どうにもならないことであっさり崩れてしまうことがあるからです。
そんなときは「もう努力する意味なんてないのかも」と思ってしまうんじゃないでしょうか?
実際に私自身も、この考えに苦しんだことがあります。
でも人生は続いていくから、なんとか前を向いて生きたい。そう考え抜いた結果、たどりついたアイデアを今回はエッセイとしてまとめてみたいと思います。
そのアイディアとは「人生は運次第」という言葉が指している「運」って、誰にでも平等に降りかかる“本当の運”とは違うんじゃないかということです。
もし本当の意味で運がすべてを決める“運否天賦の世界”があったら、むしろもっと希望が持てるんじゃないか…というお話です。
目次
「人生は運次第」は本当に運任せ?
まずは、世間でよく耳にする「人生は運次第」という言葉と、本当に運のみで決まる“運否天賦の世界”の違いについて考えてみたいと思います。
「人生は運次第」って、ちょっと暗い響きがありますよね。たとえば「親ガチャ」とか、「才能がすべて」みたいな言い回しも、結局は運が悪いとうまくいかない、という意味合いを含んでいます。
でも、本当に運だけで決まる世界だったら、勝つか負けるかは単なる確率の問題になります。
そうなると、誰にでも勝つチャンスも負ける可能性もあって、むしろ平等ですよね。そこに厭世的なイメージは本来ないはずです。
ところが、「人生は運次第」と言うときには、その平等な感じは出てこない。どうしてだと思いますか?
それは、人が普段“因果関係”をもとにストーリーを組み立てるのが得意だからです。
運否天賦の世界と因果論の世界
この違いを考えるために、人生をカジノのルーレットに例えてみます。
赤と黒が半分ずつのルーレットを回して、赤が出たらいいこと、黒が出たら悪いことが起こるとします。たとえば、
- 最初のルーレットは「どの国に生まれるか」。赤が出れば先進国、黒が出れば戦争中の国。
- 次のルーレットは「どんな家に生まれるか」。赤が出れば愛情いっぱいの両親、黒が出れば冷たい家庭。
そのあともずっと、赤ならいいこと、黒なら悪いことが起こる――これが“運否天賦の世界”です。そこでは文字どおり運で結果が決まります。
一方、「人生は運次第」と嘆いている人が目の前にいると想像すると、その人は自分のルーレットの盤面をどう見ているでしょうか?
きっと黒が多い盤面を思い浮かべているんじゃないでしょうか。
「こんなにうまくいかないのは、運悪く黒一色のルーレットを与えられてしまったからだ」と思うわけです。
でも実際には、盤面全体が見えるわけではありません。連続して黒が出たから「きっと黒い目ばかりのルーレットなんだ」と考えるんです。
なぜなら人は結果を見てから「原因」をあとづけする“因果論”でストーリーを考える傾向があるからです。
運否天賦の世界のルーレットと、因果論で見るルーレットの違い
- 運否天賦の世界
- 赤も黒もあり、どちらの目が出るかは運で決まる。たまたま黒が10回連続で出ることだってある。
- 因果論の世界
- 出た目から盤面を想像する。黒が続けば自分は黒一色のルーレットを与えられたと考える。そして「そんな盤面を与えられた自分は運が悪い」と考える。
どちらの世界でも黒が続いたときに「運が悪い」と感じます。でも、実際にイメージする盤面は違っています。
この違いは「結果がこうだから、きっと原因はこうだろう」と、筋道を立てる癖があるから起こることです。
努力と運は表裏一体
もうひとつの例として、よく運と対比される“努力”の話があります。
「努力したから成功した」という言葉を見ると、運よりも努力が大事って感じますよね。
でも、実はこの「努力が人生を左右する」という考えも、“人生は運次第”という考えと表裏の関係にあると考えられます。
たとえば、何度も赤が出て結果的にうまくいったときに「これは努力で赤い目を増やしたからだ」と思う。
そうすれば「努力が報われた」って納得できます。でも本当は運によって赤が出続けただけかもしれません。
けれど「偶然赤が続いただけかも」とはなかなか思えない。なぜなら、そんな世界じゃ味気ないからです。
だから「努力したからだ」と原因づけしたくなる。そのほうが、自分にも人にも説明がしやすく、前向きな気持ちにもなれるからです。
なぜ人は理由を欲しがるのか
人は、何事にも理由をつけたくなる生き物です。
良くないことが起きたとき「やっぱり自分は不幸の星の下に生まれたんだ」と考えると、ある意味でホッとすることがあります。
理由づけできるほうが、自分の気持ちの整理がつきやすいからです。
理由もなく、ただただ運が悪くて不幸なことが重なったと思うと「理不尽だ」「なんで自分だけ」とつらさが増してしまいます。
だからこそ、人は不幸が続いたときに、自分のルーレットが黒一色と考えてしまいがちです。
同じように、いいことが続いたときにも「偶然なんて認めたくない。自分の努力が実ったんだ」と思いたい。そのほうが自分自身の存在価値を感じやすいからです。
因果論がもたらす危うさ
こうした“因果論”は、科学や社会制度を発展させる原動力でもあります。原因と結果を考えるからこそ、事故や災害の対策が進んだり、問題があった法律を変えたりすることもできる。
でも、時には人を傷つけることもあります。その典型的な例が“公正世界仮説”です。これは「いいことをすればいい報いがあり、悪いことをすれば悪い報いがあるはずだ」という考え方です。
たとえば夜道で暴漢に襲われた女性がいたとき、本来なら加害者が悪いのに「夜遅くに出歩くあなたが悪い」と被害者を責めてしまうケースがあります。
これは、理不尽な不幸が起きたとは思いたくないから、被害者にも“原因”を押し付ける形です。
公正世界仮説は、自分自身に対しても向かうことがあります。たとえば小児がんの明確な原因はまだわかっていないのに「自分の育て方が悪かったせいかもしれない」と親が自分を責めてしまうことがあります。
「運が悪かっただけ」という理不尽が受け入れがたく、原因を求めてしまうんです。
運否天賦の世界を受け入れられるだろうか
私たちは理不尽さを嫌って、どうしても理由を探そうとします。それは生きていくうえで心を守る手段でもあるのです。
- 「自分の人生に不幸が続くのは黒一色のルーレットだから」
- 「幸せなのは努力して赤い目を増やしたから」
こうした因果論的な考え方には安心感があります。でも、その裏には「運否天賦の世界=本当に何が起こるかわからない不条理な世界」を恐れる私たちの姿が垣間見えます。
それでも、あえて“運否天賦の世界”を受け入れるとしたら、どんなメリットがあるのか。次の記事では、そこにフォーカスしてみたいと思います。
まとめ
- 「人生は運次第」という言葉は、本当の意味での運任せではなく、因果論のストーリーによって説明できる。
- 運否天賦の世界では、赤(幸運)も黒(不運)も平等に起こり得る。しかし、そこに人は不条理を感じる。
- 努力と運は対立しているように見えて、その実“ストーリーをつくる”という点で表裏一体の関係。
- 公正世界仮説のような因果論の考え方は、社会を発展させる一方で、ときに被害者をも責める危うさももつ。
- それでも理由を欲するのは、人が不条理を受け入れるのがとても難しく、何かに納得したいから。
よろしければcodocで投げ銭していただけると、創作時間の捻出にもつながり励みになります。
また感想や共感したポイントがあればXでぜひ教えてください。下のXボタンから共有ポストできます。