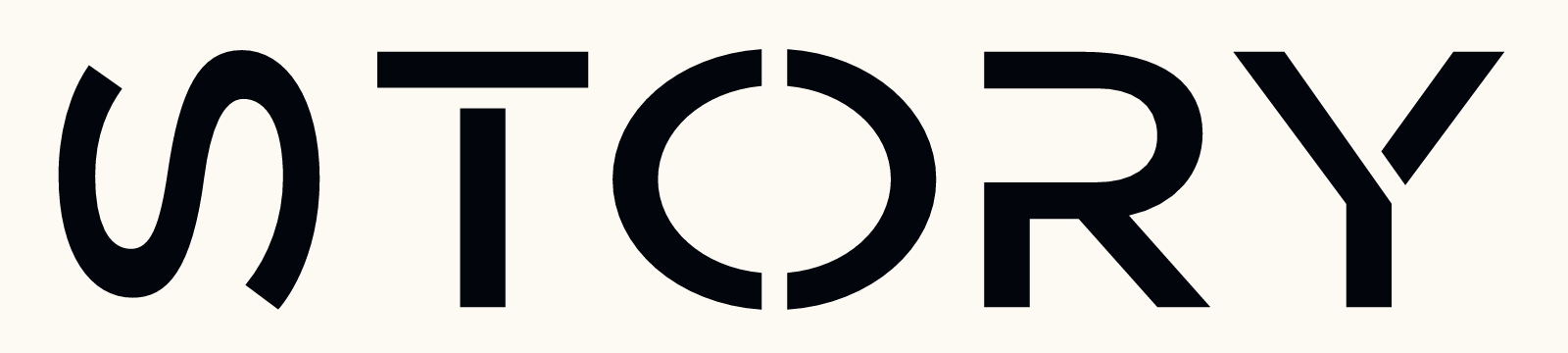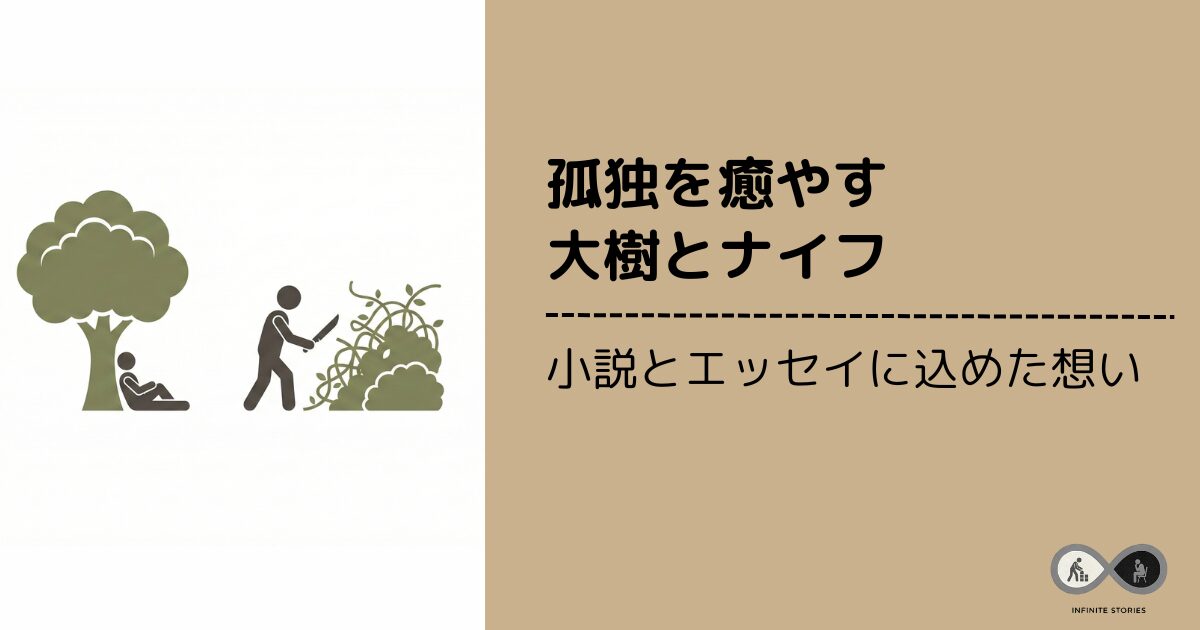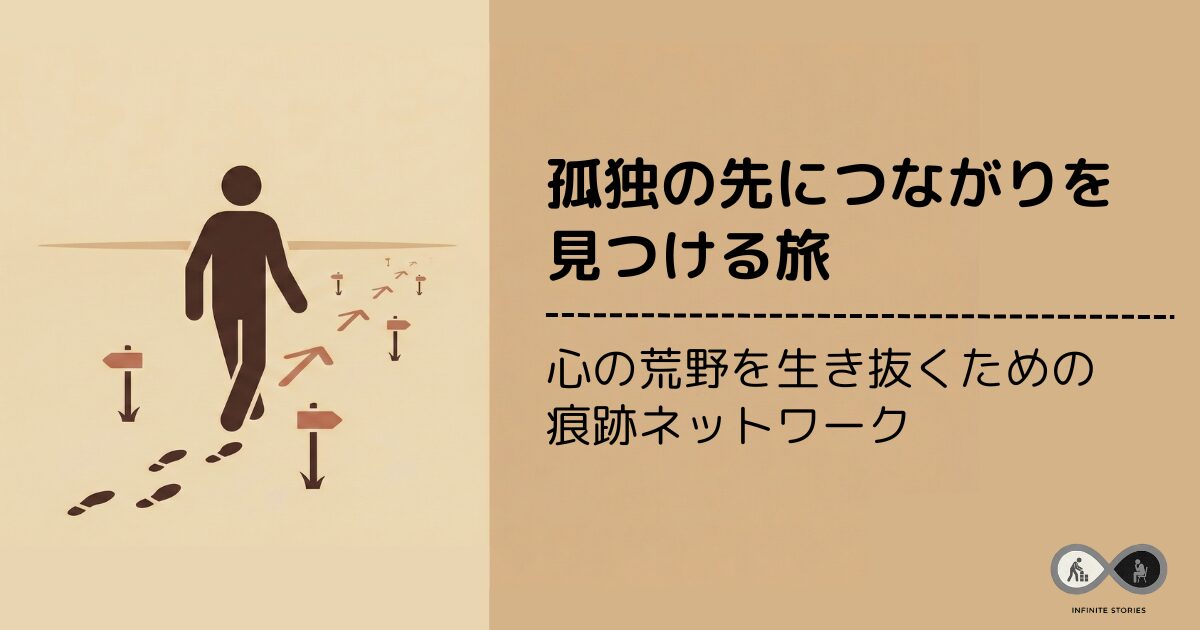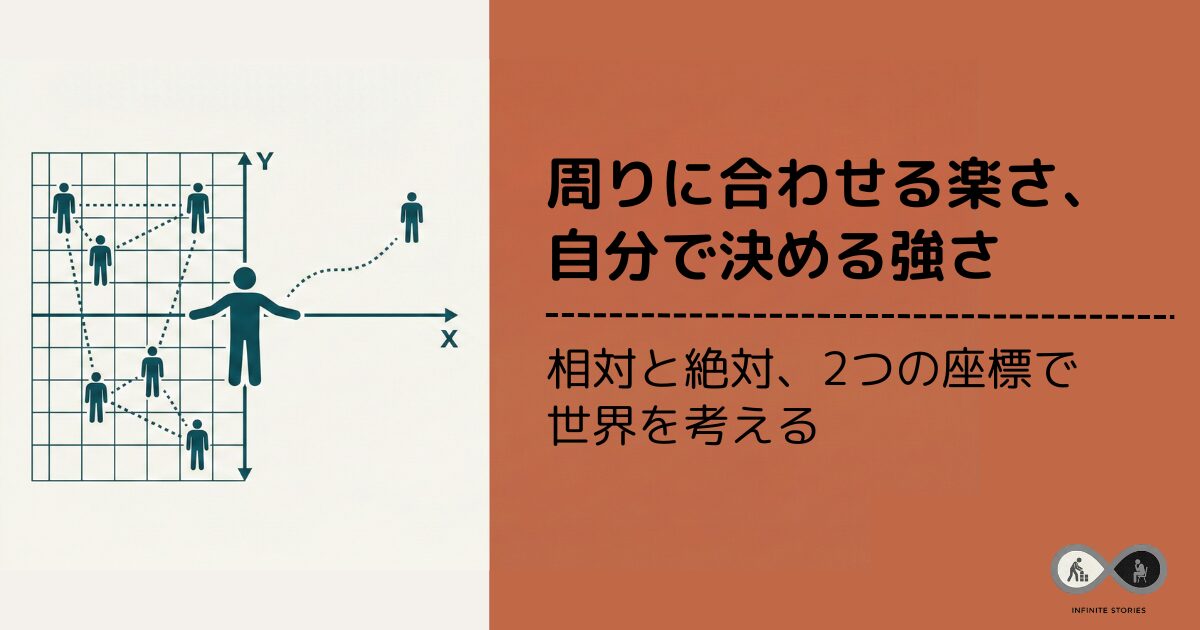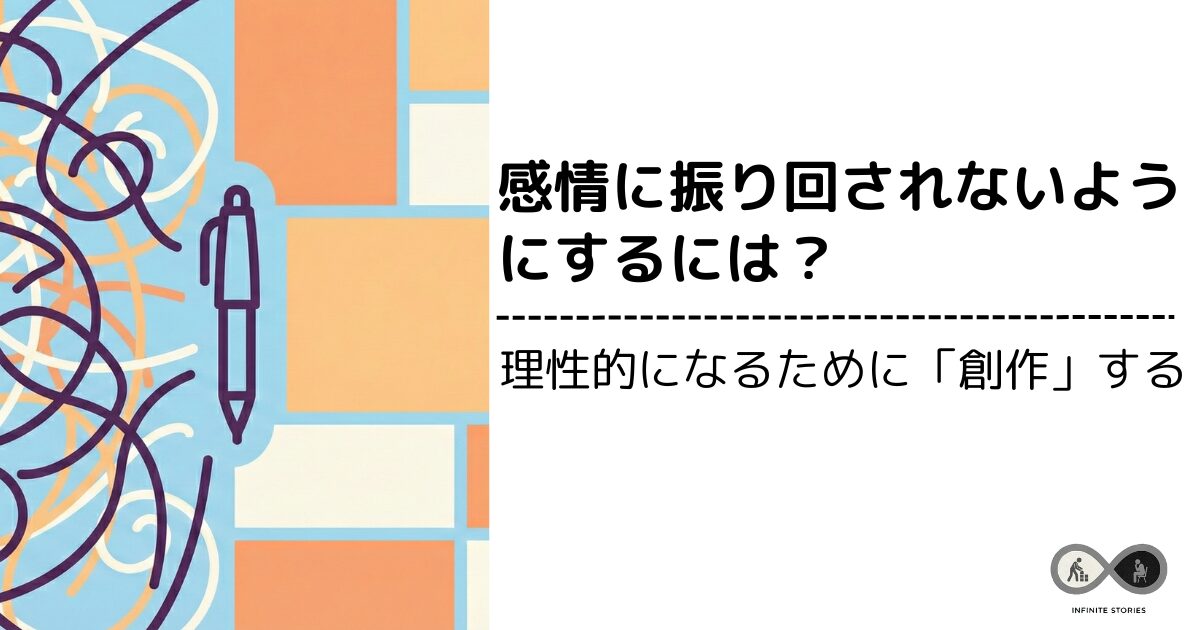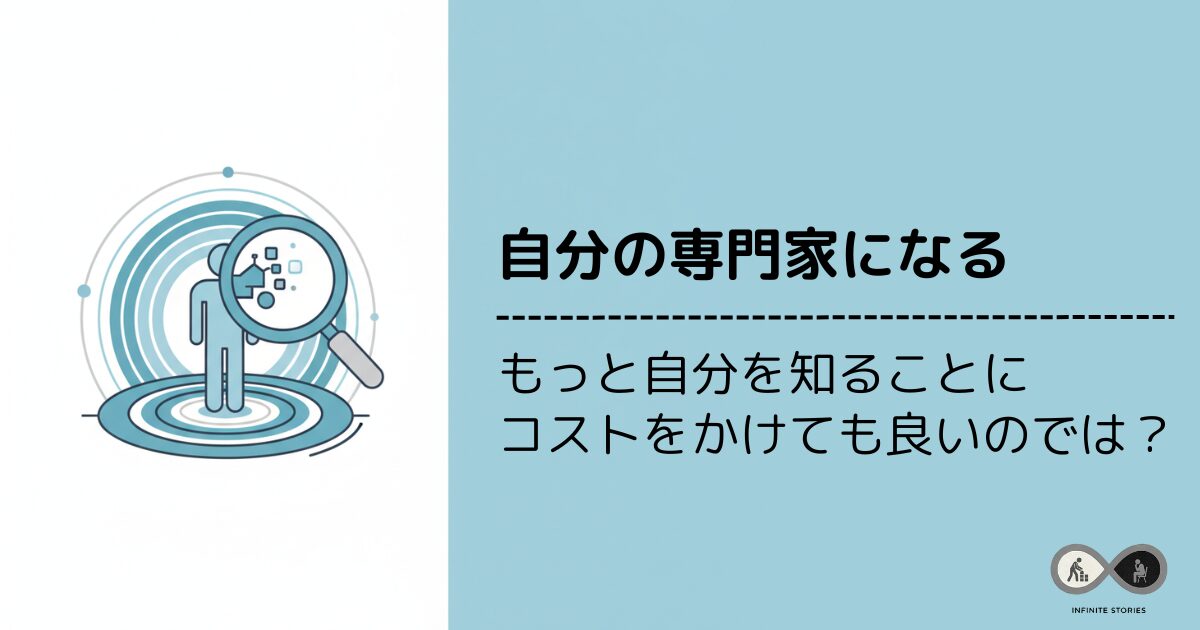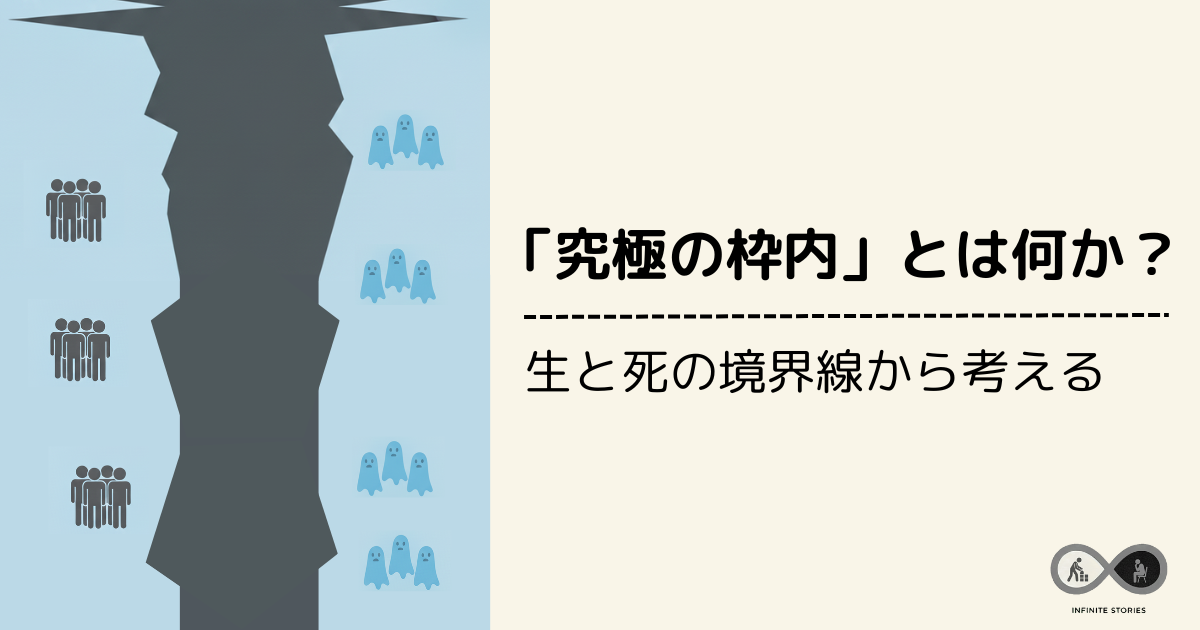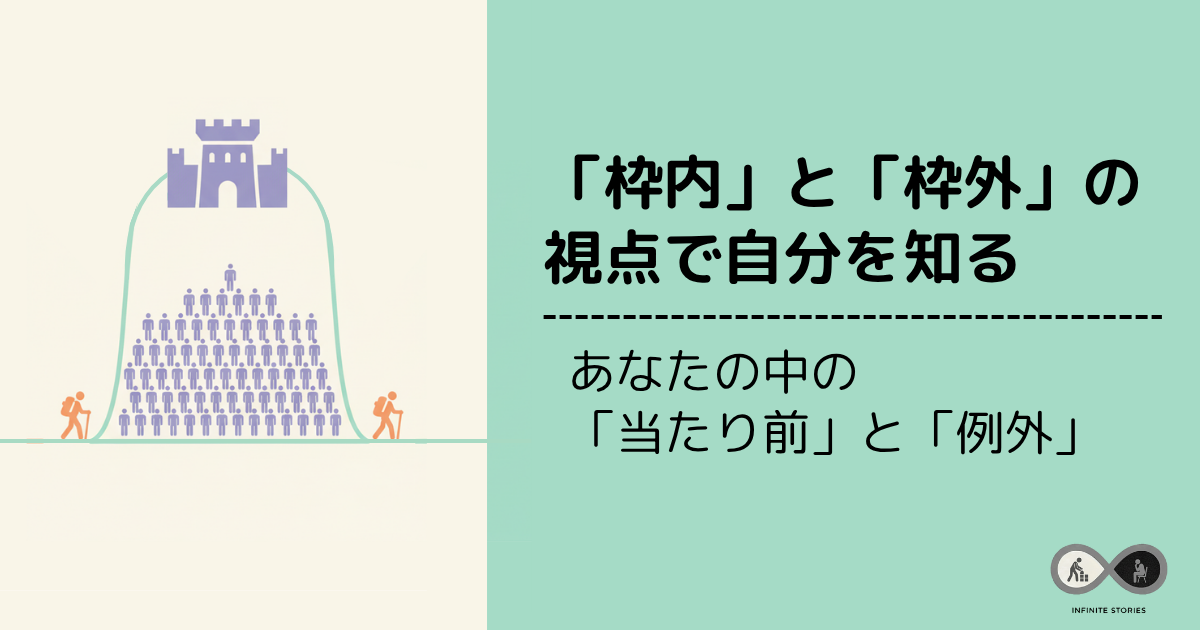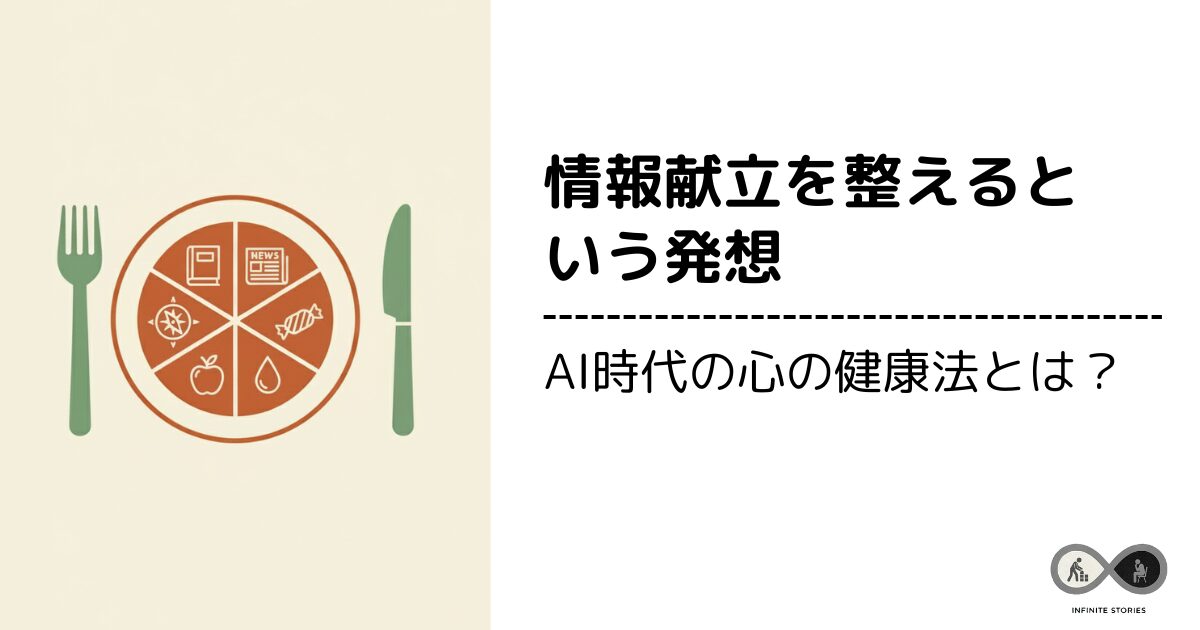心を癒やすための第一歩:「自分の物語を綴る」とはどういうこと?
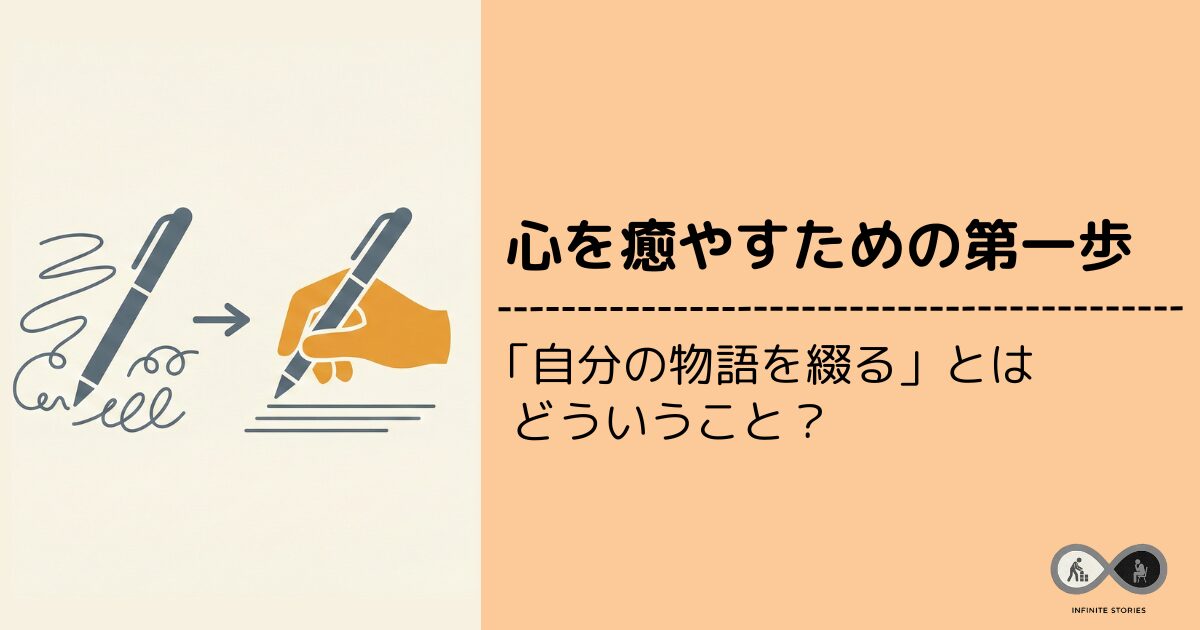
一言サマリー
他者に癒やしを求め続けるリスクを避けるには、自分の物語を意識的に綴り自身を支えることが大切ということを考察したエッセイです。
要点まとめ
- 他者依存のリスク:癒やしを他人にばかり求めると、その心理を利用する人に出会う危険性がある
- 無意識の物語形成:私たちは日常の経験から「世界はこういうもの」という物語を無意識に作り続けている
- ネガティブ偏重の傾向:人間の脳は生存本能から、安全のためにネガティブな解釈をしやすい
- 物語の構成要素:自分の物語は「客観的な事実」と「主観的な解釈」が混ざり合ってできている
- 綴ることの意味:無意識に書かれた物語を放置せず、自分の意思でペンを握り直して書き直すこと
- 上書きの困難さ:ネガティブな物語が積み重なると、ポジティブな出来事があっても受け入れにくくなる
- 実践の重要性:完璧を求めず、身近なテーマから少しずつ自分の物語を意識的に綴り始めることが大切
音声コンテンツはこちら
notebooklmによる音声概要
今回は「癒やしを得るためには、自分の物語を綴ることがとても大切」という考えをお伝えしたいと思います。
私たちはさまざまな状況で癒やしを求めます。ただ、その最中には「つらい気持ちを自分だけでは抱えきれない」「不安で押しつぶされそう」という状況に陥りがちです。
そうなると世界が灰色に見え、「自分は世界にたったひとり」と置き去りにされたように感じることもあるでしょう。
そんなとき、私たちは「誰かに気持ちを受け止めてもらいたい」と強く思います。誰かにそばにいてほしい、寄り添ってほしいと願うわけです。
けれど前回の記事で触れたように、その思いを利用されてトラブルに巻き込まれるリスクもあります。
これは「寄り添ってもらいたい」という気持ちをうまく利用する人が世の中には存在するからです。癒やしを求めたときに、そうした人に出会うのか、本当の意味で寄り添ってくれる人に出会えるのかは、正直なところ“運”の要素が大きいと感じています。
そう考えると、他者にばかり癒やしを求め続けることは、私たちの気持ちを利用されるリスクを上げてしまうともいえます。
そこで「自分の物語を綴ること」が、このリスクを減らすのに役立つのではないかと考えています。ここでは「自分の物語」と「綴る」という、ふたつのキーワードに分けて少しずつ整理していきたいと思います。
目次
自分の物語について
「自分の物語」とは、自分が世界をどのように見ているか、ということを指しています。
実はこの物語は普段、無意識のうちに積み重ねられています。いろいろな経験をする中で、「物事はこういうものだ」という判断が自然にかたちづくられ、それが自分なりの世界観、つまり“物語”になっているのです。
多くの人が共有している常識やルールのような物語もあります。たとえば「人のものを盗ってはいけない」というように、しつけや教育を通して誰もが学んできたものです。
子どもの頃はその物語を持っていないので、友達のおもちゃを勝手に持っていってしまうことがある。そこで怒られて初めて「人のものを盗ってはいけない」という物語が自分のなかに刻み込まれるのです。
一方で、家族に対する思いや仕事観のように、個人差が大きい物語もあります。幸せな家庭で育った人は家族をポジティブにとらえる物語を持ち、そうでない環境で育った人はネガティブな物語を持つこともあるでしょう。
つまり、私たち一人ひとりは、ポジティブな要素もネガティブな要素も含めた、独自の“物語”を持っているわけです。
このような“物語”は無意識に作られていきます。さながら自分の人生という本に対して、ペンが勝手に動き物語を書き上げていくようなものです。
物語には客観と主観がある
自分の物語には「客観的な事実」と「主観的な解釈」が混ざり合っています。たとえば、「親に大切にしてもらえなかった」という物語を持つ人でも、その具体的な背景は異なるかもしれません。
- 経済的には恵まれていたけれど、忙しい親のもとで一人ぼっちだったために「大切にされなかった」と感じる人たち
- 親は近くにいてくれたけれど、経済的理由で進路を諦めざるを得ず「大切にされなかった」と感じる人たち
どちらも同じ「大切にされなかった」というネガティブな物語ですが、その元となっている客観的事実は違っています。このように客観的事実と主観的な解釈が合わさって、それぞれの物語が形作られているのです。
物語を「綴る」ということ、綴らないリスク
自分の物語を「綴る」というのは、これまで無意識に作られてきた物語を、そのまま放っておくのではなく、自分の手で意識的に“書いてみる”ということです。
何かつらいことがあると、私たちの心は深く傷つき、ネガティブな物語が生まれやすくなります。そのままに任せておくと、ネガティブな物語がどんどん書き足され、広がっていきます。
そうなると、そんな物語を読まされる自分がますます苦しくなり、やがては目をそむけたくなるかもしれません。そんなときに、この物語を利用する人が現れるとトラブルに巻き込まれてしまいます。
前回のお話で触れたホストにはまった女性を例にとると、彼女は「自分が悪い」と責める物語を強く持っていました。そこへホストが「そんなことはないよ」と肯定的な物語を書いてくれたため、彼女は心惹かれ、結果的にハマってしまったのです。
こうしたことは、自分の手で物語を綴れず、他の人が上書きした物語に支配されてしまったからこそ起きる問題だと考えられます。
だからこそ「自分で物語を綴る」作業が必要になるのです。
人はどうしてもネガティブな物語を作りやすい
大前提として、私たちの脳はネガティブな物語を作りやすい傾向があります。これは人間が生き延びるために得た本能ともいえるものです。
たとえば、サバンナにいると想定して、遠くの草むらが揺れたら、風だと楽観的に思うよりも「もしかすると肉食獣がいるかも」と警戒するほうが生存確率は上がります。
たとえ本当はただの風だったとしても、警戒しておけば襲われるリスクを減らせますよね。こうした「安全のためのネガティブ思考」が、人類が生き残るうえで重要な役割を果たしてきたのです。
ところが、このネガティブ思考があまりに強いと、「世界は灰色」というような絶望的な見方をしてしまったり、人とのちょっとしたトラブルに敏感に反応しすぎて苦しくなったりします。
たとえば、接客で嫌なお客さんに当たった瞬間に、その人の印象すべてが悪く見えてしまい、ほんの少しの事情もくみ取れなくなってしまうことがあるでしょう。
ただ、その判断自体は決して悪いわけではありません。一度会っただけの嫌なお客さんなら、詳しい事情を考えずに決めつけた物語だったとしても、人生にはあまり影響がないかもしれません。
でも、それが家族との関係など、繰り返し向き合わなくてはならないテーマだとしたら、状況は変わってきます。 あなたのつらい感情をインクとして、さらさらとネガティブな物語がどんどん書き足され、大きな苦しみにつながってしまうのです。
ネガティブに染まった物語を上書きするのは難しい
家族とのつらい経験が重なりすぎると、ネガティブな物語ばかりの分厚い一冊の本ができあがってしまいます。その状態でポジティブな出来事があっても、「そんなわけない」「たまたまだよ」と書き換えてしまい、なかなかそのポジティブな面を認められません。
なぜなら、ネガティブな本にポジティブな物語が入り込むことは違和感があるからです。
すると、「全部がネガティブな物語で埋まっている」という認識が強化されてしまいます。だからこそ「大丈夫、あなたはなにも悪くないよ」と全肯定して無理やり上書きしてくれる人にすがりつきたくなってしまう。そこにトラブルが入り込む余地が生まれてしまうのです。
自分で物語を綴るためのハードル
「自動的に書かれた物語はネガティブになりやすい」と理解したうえで、自分の意思でペンを握り、自分らしい物語を綴ることが大切です。ですが、これは簡単なことではありません。
どこにペンがあるのかすら分からないような状況かもしれません。また目を開ければネガティブな物語が嫌でも目に飛び込んできてしまう。
それでもペンを探し、ときには目をそむけながらも、なんとか自分の物語を綴る必要があります。
さらに、いざペンを握っても、都合のいい物語に書き換えられるわけではありません。悲しみや怒りといったネガティブな黒インクを「なかったこと」にすることはできないからです。
けれど、表現を自分なりに工夫することは可能です。ゆっくりと時間をかけて、自分にしっくりくる言葉を探しながら綴ってみると、ネガティブな出来事も少しずつ受け入れやすくなります。
とはいえ、とても大変な作業であることは間違いありません。場合によっては専門家の手を借りながら、人生をかけて取り組むべき大きなテーマになることもあるでしょう。
それほどの重荷を背負うのはつらいことですが、少しずつ身近なところから始めてみるのが良いと感じています。私自身も「自分の物語を綴るって大事だな」と意識しながら、少しずつ書き続けることを心がけています。
次回は私自身の経験から、「自分にとってベストな睡眠」をテーマに、自分の物語を綴るということを、どのように実践しているか具体的にご紹介できればと思います。
よろしければcodocで投げ銭していただけると、創作時間の捻出にもつながり励みになります。
また感想や共感したポイントがあればXでぜひ教えてください。下のXボタンから共有ポストできます。