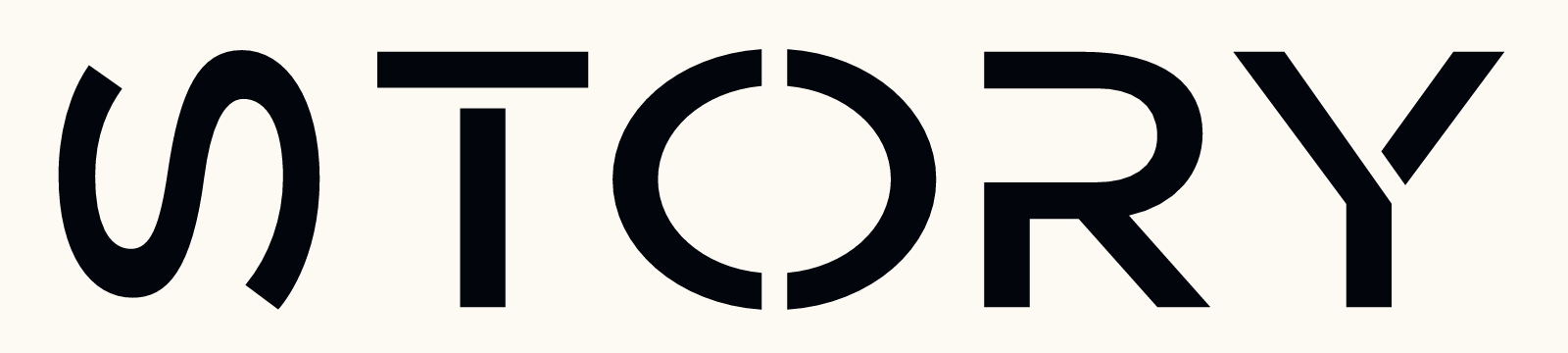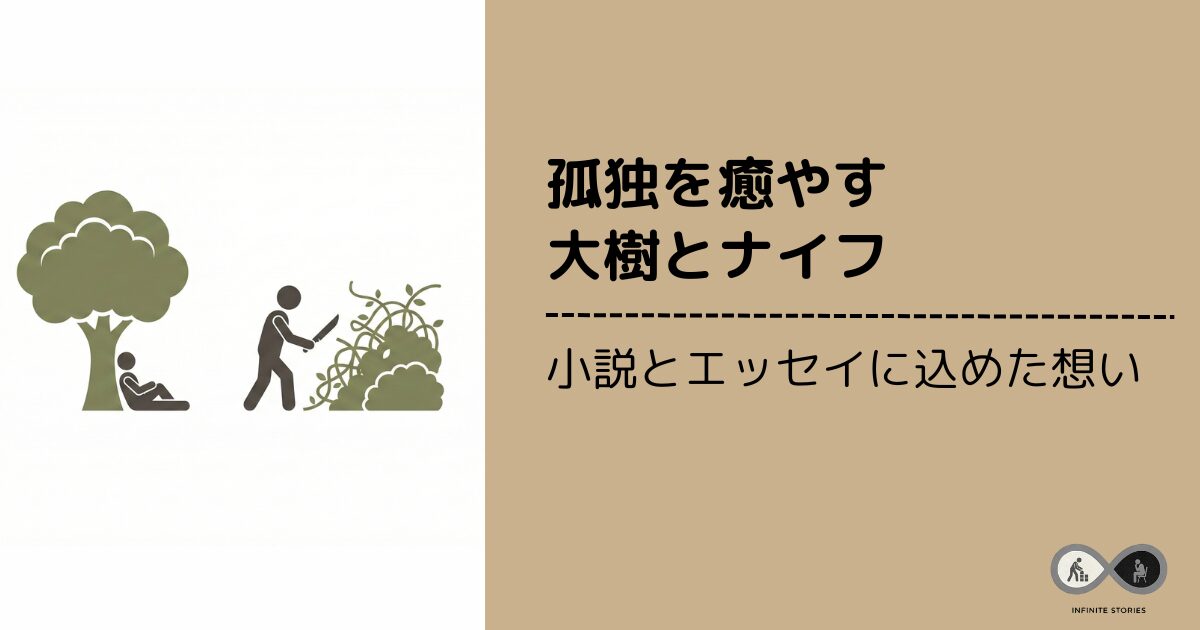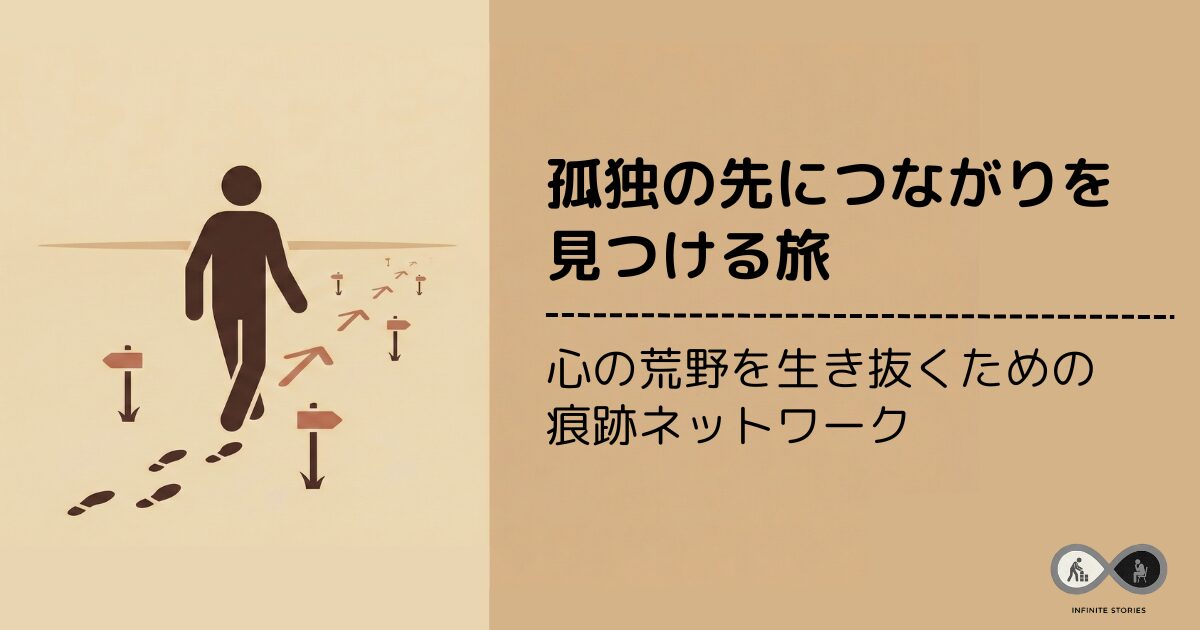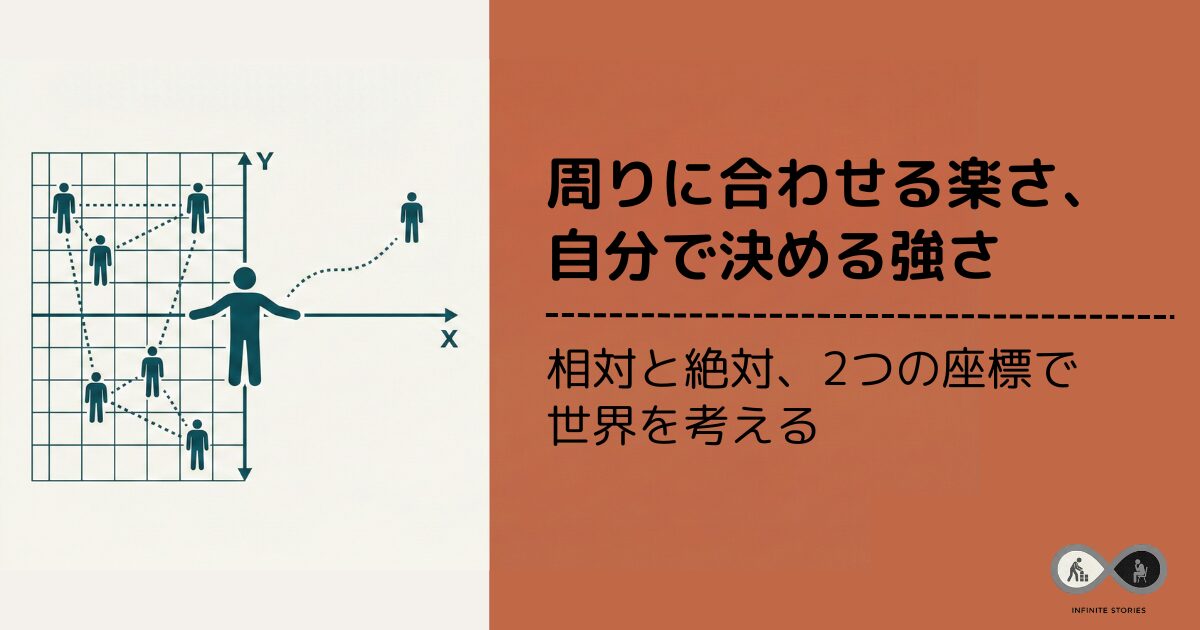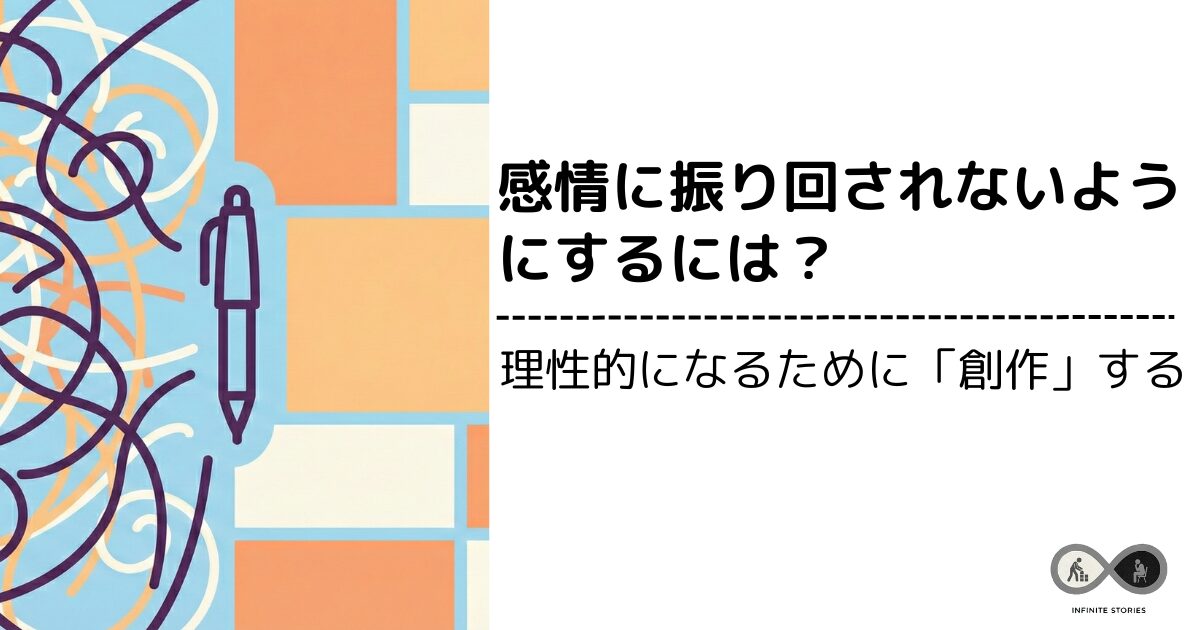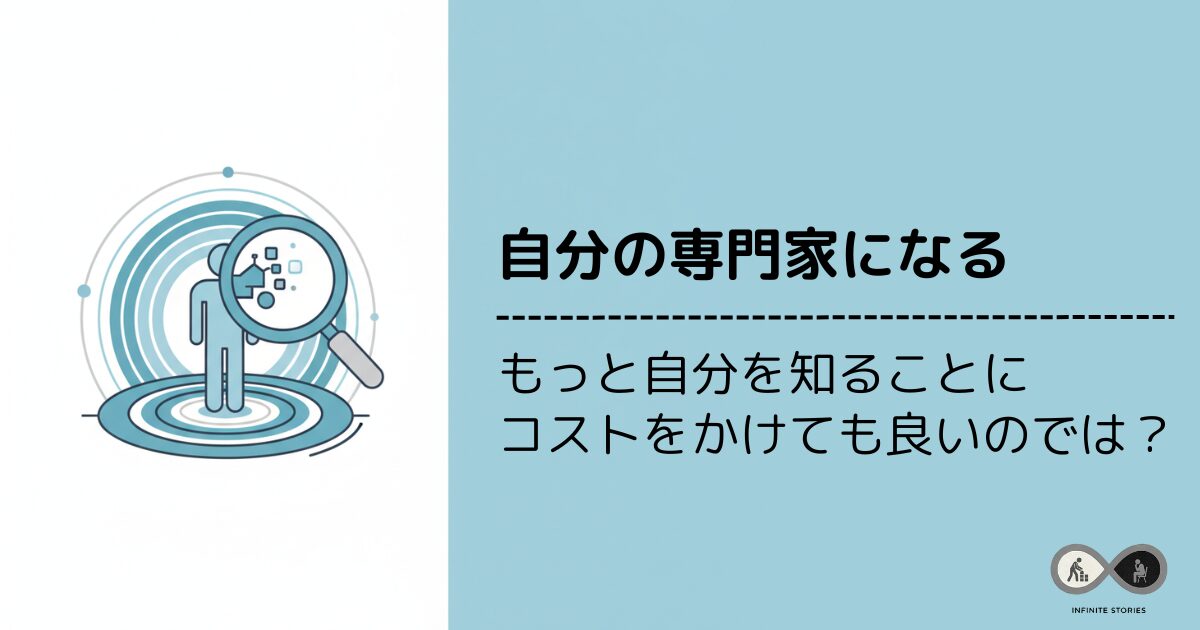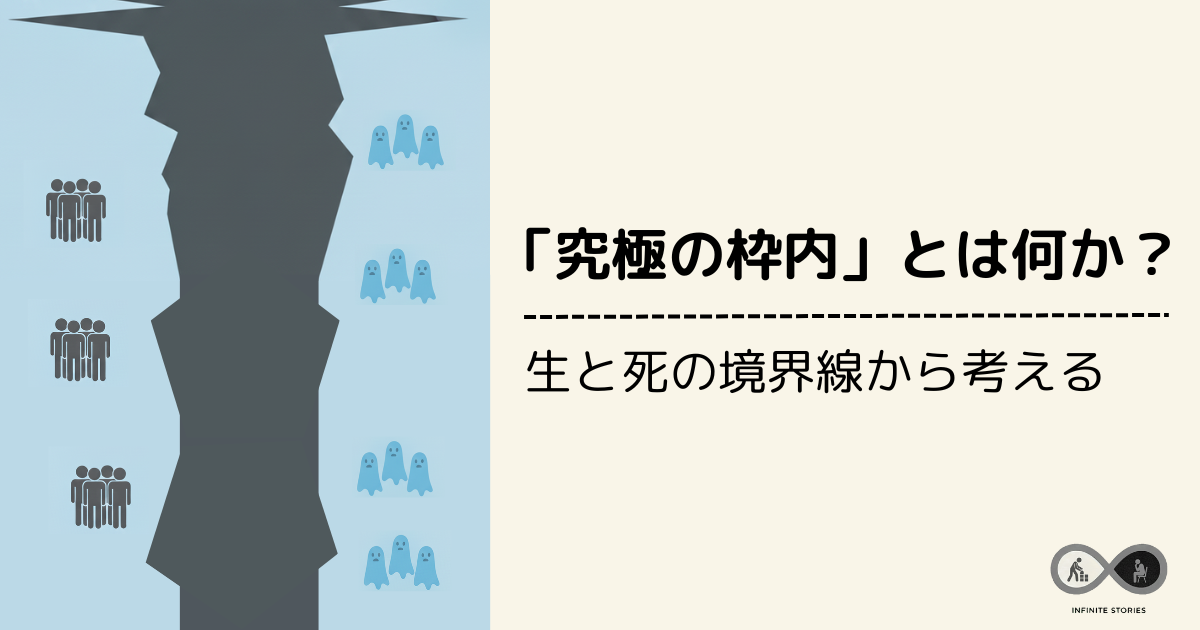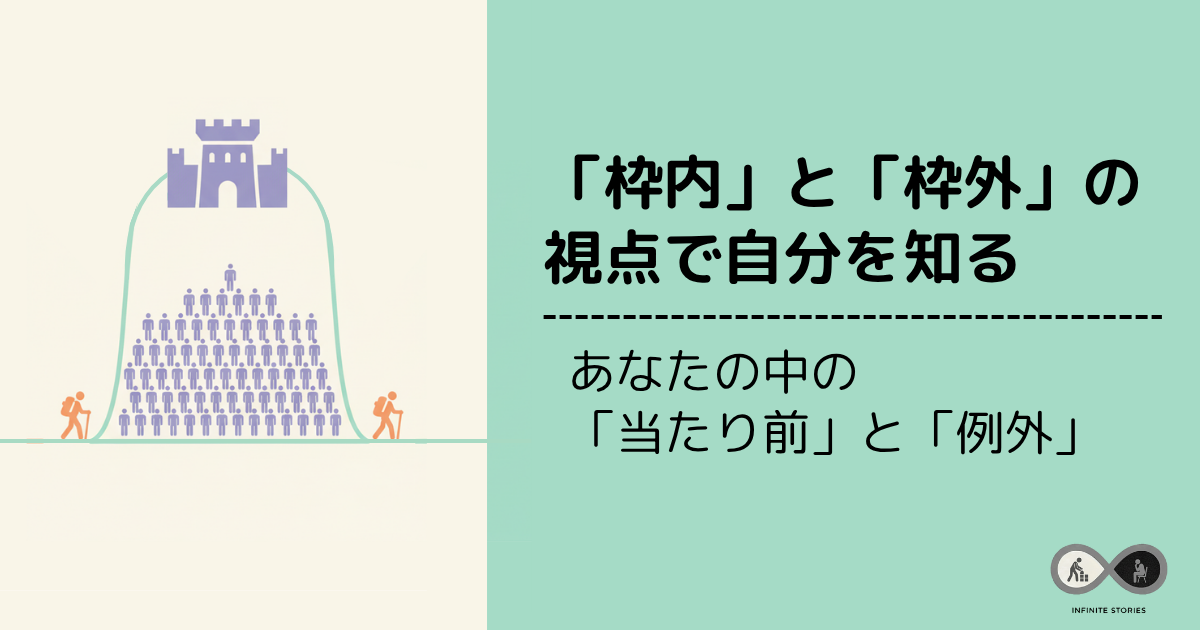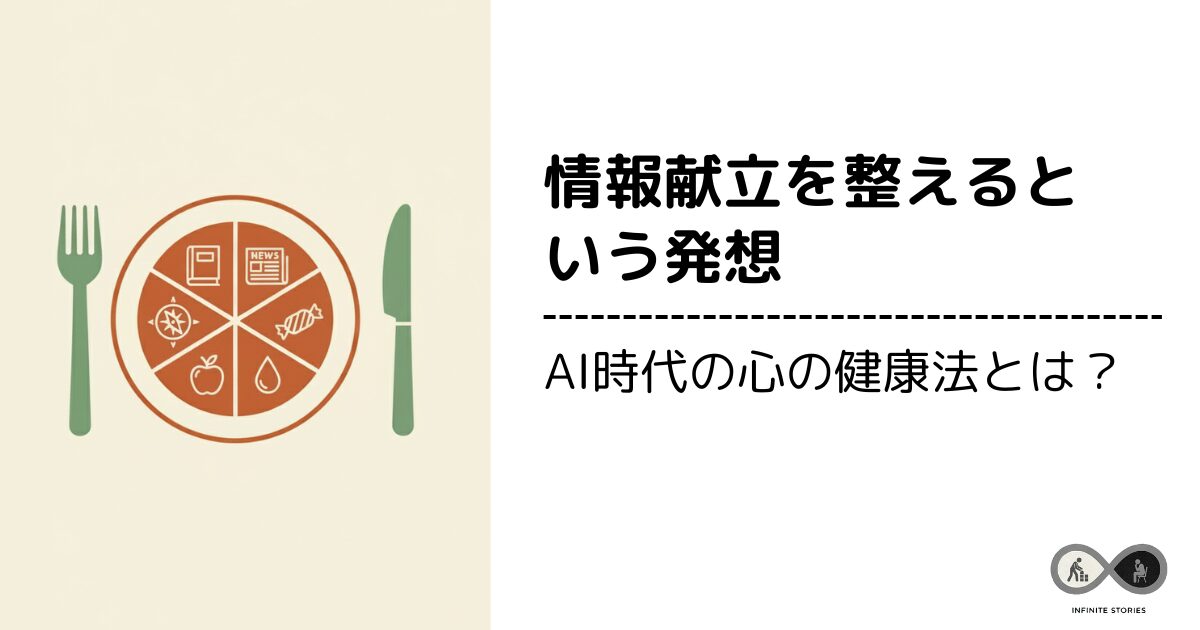複雑さを意識して選ぶ世界観:『非自然』という視点で認知を見つめ直す
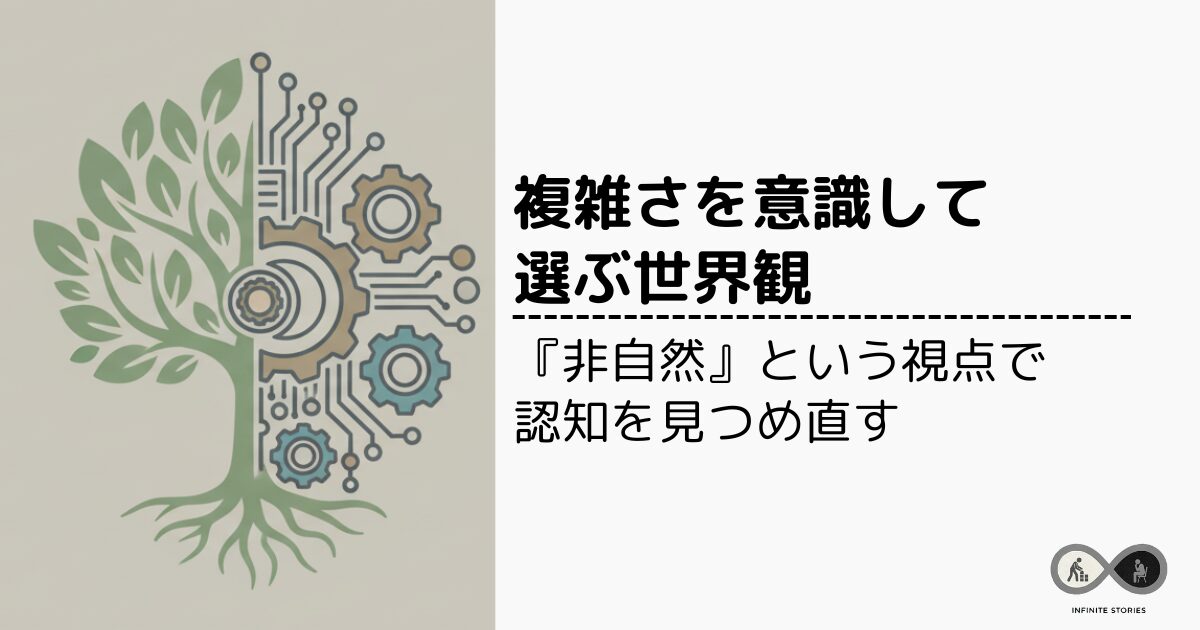
一言サマリー
本能に任せる「自然」と意識的な努力が必要な「非自然」の境界線を探り、現代社会で非自然な努力が求められる理由を解説したエッセイです。
要点まとめ
- 自然=おのずからそうなる/労力が少ない(本能、歩行能力など)
- 非自然=おのずからはそうならない/労力や時間がかかる(ダイエット、運転技術など)
- オマキザルの実験が示すように、不公平への怒りのような複雑な感情も進化の過程で獲得された自然なもの
- 「自分らしく生きる」ことは自然に見えて実は非自然(集団の同質性を重視する本能に反するため)
- 生まれた時点で当たり前に存在していたかどうかで、人によって自然か非自然かの認識は変わる
- 写真やインターネットなど、非自然だったものが時間をかけて自然なものへと変化した例は多い
- 人間の認知は自然な方向へ偏りやすいため、意識して非自然に目を向けることが大切
音声コンテンツはこちら
notebooklmによる音声概要
前回、前々回の記事では、「本能をコントロールする」というテーマを通じて、「内面世界を複雑にする」という考えを紹介しました。
この「本能をコントロールする」スキルは、私たちの世界が「非自然」な方向に向かっている現代だからこそ、必要になるものだと感じています。
ここで言う「非自然」とは、「自然ではない」というフラットなニュアンスで使っている造語です。
一般的に「自然」の対義語は「不自然」ですが、その言葉にはネガティブなイメージがあるため、あえて「非自然」という言葉を用いたいと思います。
目次
自然とは何か
自然とは、「おのずからそうなる」という語源が示すように、意識しなくても手に入るもののことです。
本能はその代表例です。食欲や物事を単純化するといった性質は生まれたときから持っている自然なものです。
さらに興味深いことに、一見高度に見える「不公平なことに対して怒る」という感情も自然に当てはまります。
たとえば、オマキザルを使った実験があります。
同じ作業をさせて片方にはきゅうりを、もう片方にはぶどうを与えると、はじめはきゅうりを喜んで食べていたサルが、隣のサルがぶどうをもらっているのを知った途端に怒りを示すのです。
人も同じように早い段階で「不公平」に対して怒りを覚えます。
このような生得的な反応は、自然なものと言えるでしょう。
複雑な感情でも進化の過程で獲得されたものは「自然」の範疇に入ると考えています。
また歩行能力のように、特別な障害がなければ教わることなく身につけられる能力も自然なものです。
「自然」の特徴は、それを得るために必要な労力が少ないことです。
空腹を感じるのに努力はいりませんし、物事を単純化するのも自然と起こる現象です。
非自然について
対して「非自然」とは「おのずからそうならないもの」です。
たとえば、ダイエットのために食欲を抑えるとか、内面世界を複雑にするためにわざわざ努力して考え方を変える、といった行動は何もせずに勝手に身につくものではありません。
意識的な訓練や時間の投資が必要なので、“非自然な行為”といえるわけです。
この「非自然」という概念は個人的な行動だけでなく、世界に存在するサービスや商品、技術にも当てはまります。
自動車は「自然にそこにあった」わけではなく、人間が意識的に発明したものです。
また運転技術も、教習所で学び練習して初めて身につくスキルで「非自然」なものです。
赤ちゃんは自力で歩き始めますが、車のシートに寝かせても勝手に運転できるようにはなりません。
これが「自然」と「非自然」の違いです。
まとめると:
自然: おのずからそうなる/意識しなくても手に入る/労力が少なく身につきやすい
非自然: おのずからはそうならない/意識的に手に入れる必要がある/労力や時間がかかる
ということになります。
自然か非自然か迷いやすい例
「自然なのか、非自然なのか」一見判断が難しいものもあります。
たとえば「自分らしく生きる」ということは自然な行動のように思えますが、実は非自然なものだと思っています。
多くの生物は本能的に集団の同質性を重視し、「異分子」を排除する傾向があります。
ミーアキャットの群れでは、上位のメスしか子どもを産めないルールがあり、それを破った下位のメスは追放されてしまいます。
こうした例から考えると、“群れを維持すること”のほうが本能的(自然)であり、自分らしく生きるために集団の規範から外れる行為は“非自然”だといえそうです。
だからこそ、集団に属していたほうが安心感を得やすく、逆にそこから出ようとすると不安が強くなるのではないでしょうか。
人それぞれの「自然」
本能が「自然」に分類されるなら、「自然」とは人類共通なのでしょうか?
確かに食欲や単純化などはほとんどの人に共通する自然なものです。
しかし、一部の概念は人によって「自然」か「非自然」か考え方が異なります。
その原因となるのは「生まれた時点で当たり前に存在していたかどうか」です。
たとえば自動車は本来「非自然な発明」ですが、現代では誰もがその存在を自然に受け入れています。
一方、ブロックチェーンや仮想通貨、NFTなどの新しい技術は、まだ多くの人にとって「自然」とは言い難いでしょう。わかりにくさや怪しさを感じる人も少なくありません。
新しい概念や技術は、生まれた当初は「非自然」なものとして捉えられますが、時間をかけて多くの人に受け入れられていくと、徐々に「自然」なものへと変化していくのです。
写真が生まれたばかりのころは「魂が抜かれる」と言われたり、インターネットが登場したときは「アングラな世界」と思われたりしていました。
しかし今では、それらが生活に当たり前のように溶け込んでいます。
このように、「非自然」な発明は、世間に浸透していくことで概念としては“非自然”から“自然”へと変わっていくのです。
だからこそ過渡期には、人それぞれ自然と感じているかどうかが変わるんです。
デジタルネイティブ世代やAIネイティブ世代などがわかりやすい例です。
私たちはスマホやAIなどの技術は「非自然な発明されたもの」として認識しています。
一方で彼らにとって、これらの技術は生まれたときから存在する自然なものと認識していくことでしょう。
「非自然」の価値を見つめる
このように考えると、「自然」も「非自然」も、どちらが優れているということではなく、どちらも私たちの生活に必要なものだとわかります。
自然なものは本能や生存に有利な側面を持ち、非自然なものは現代社会を支える技術やサービスの基盤となっています。
ただ、人間の認知は「水が低いところへ流れる」ように、放っておくと自然な方向へ偏りがちです。
だからこそ、意識して“非自然”に目を向けることが重要だと考えています。
これからのエッセイでも、「非自然」な話題を多く書いていきたいと思っています。
皆さんの「内面世界を複雑にする」一助になるような投稿もしているので、Xもよければフォローしてみてください。