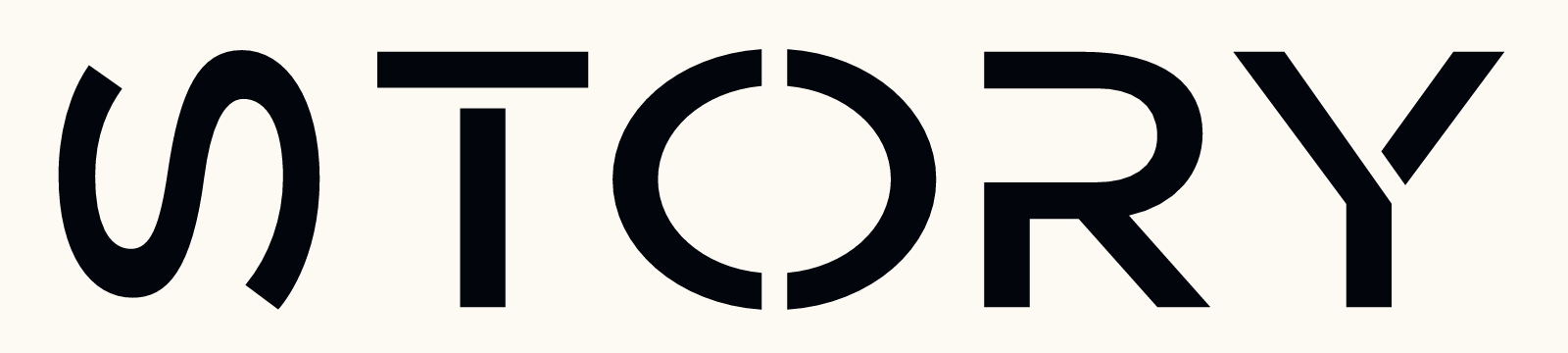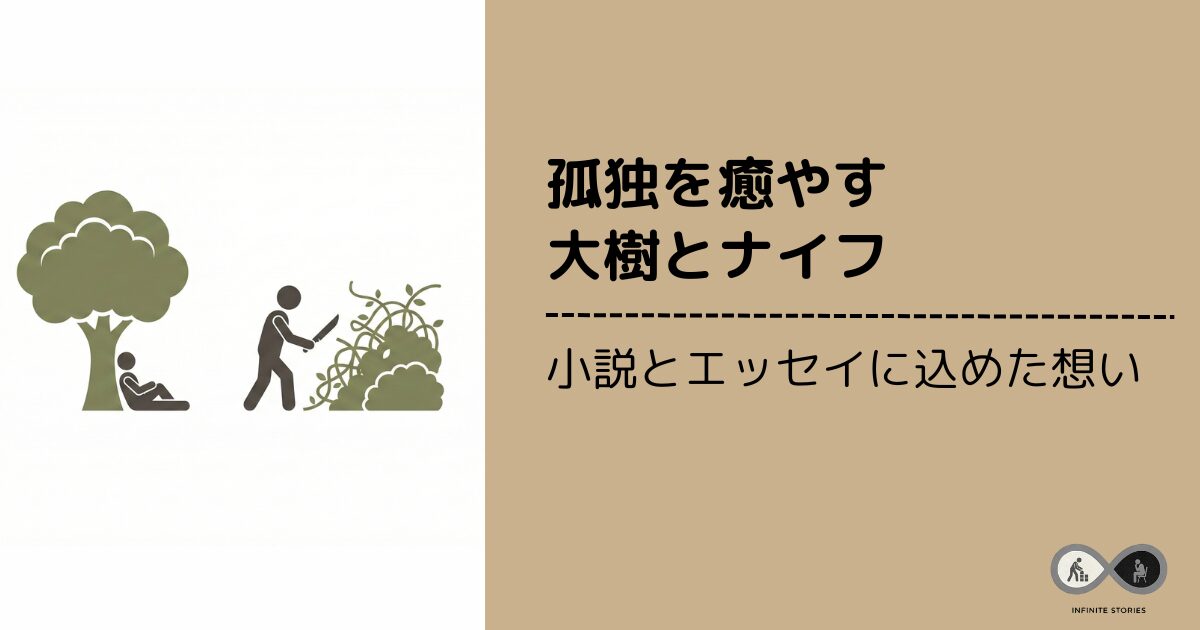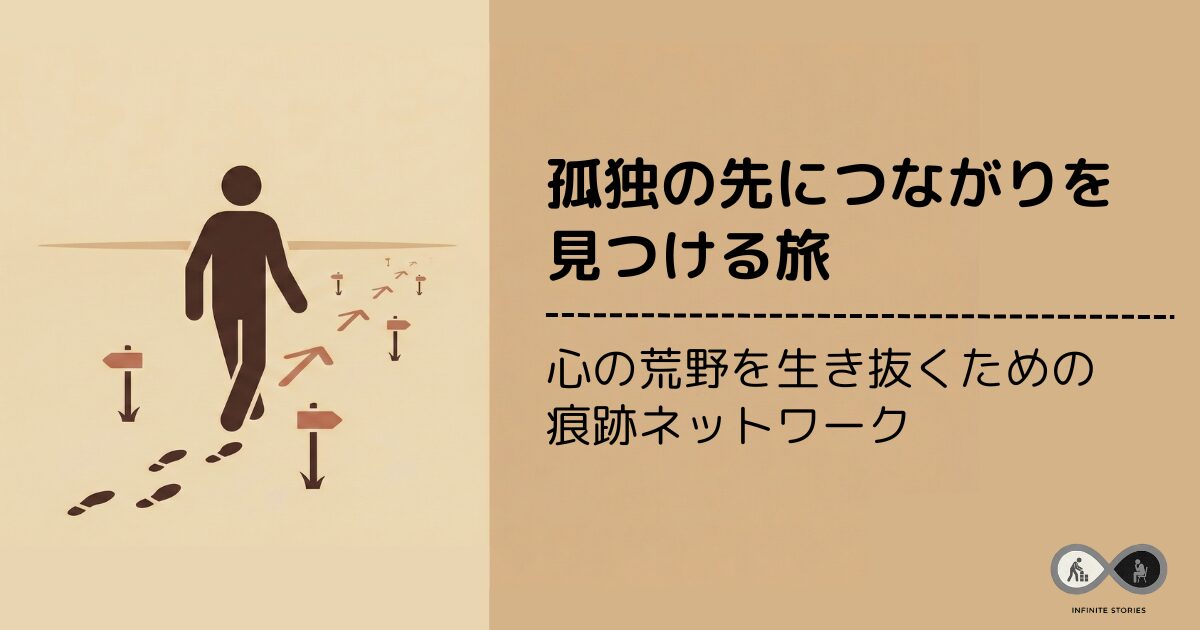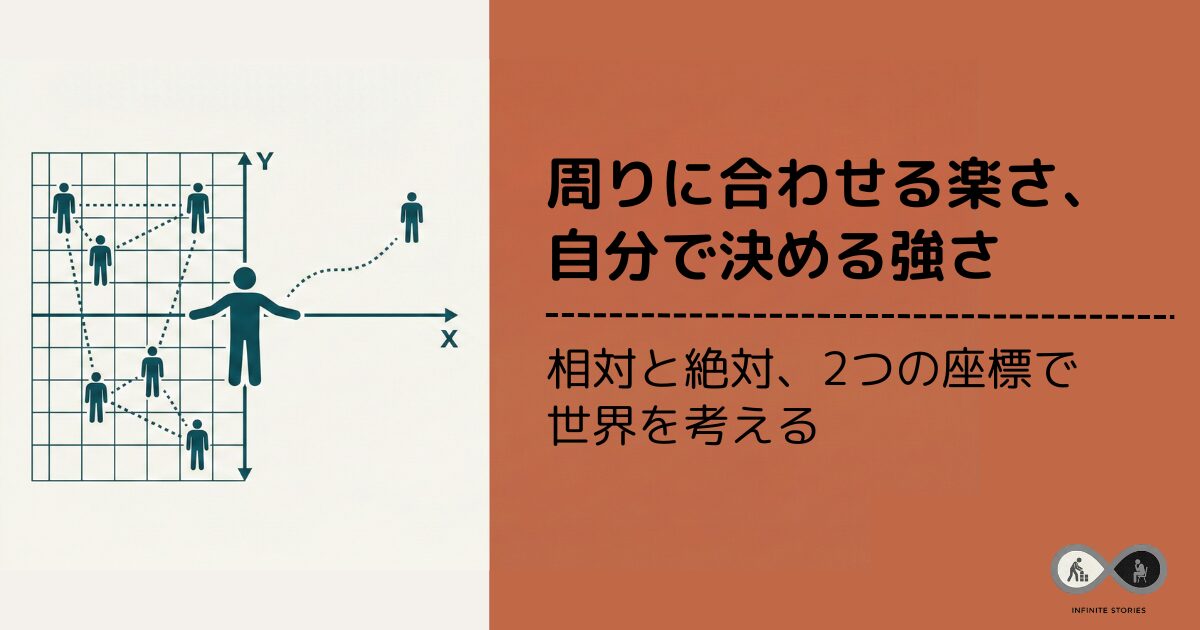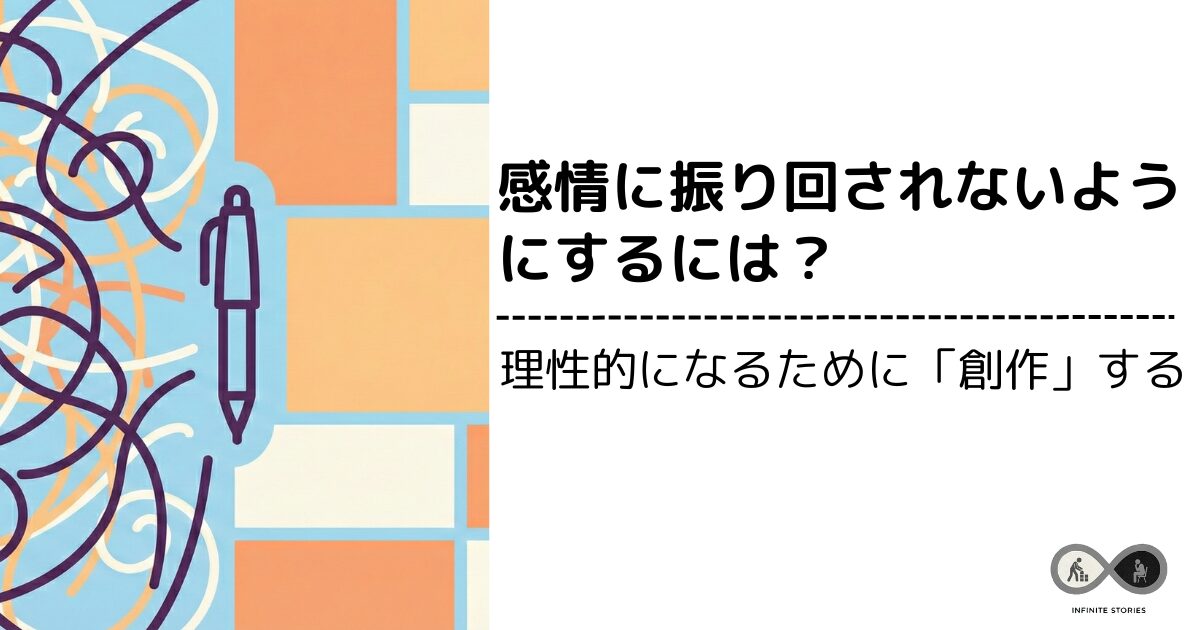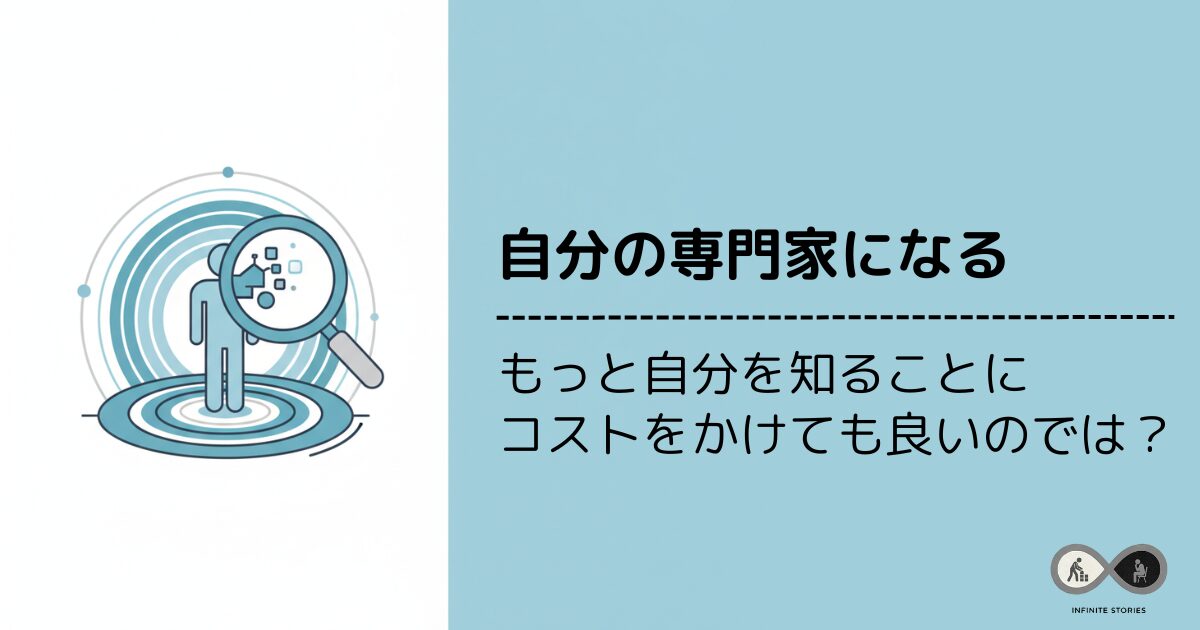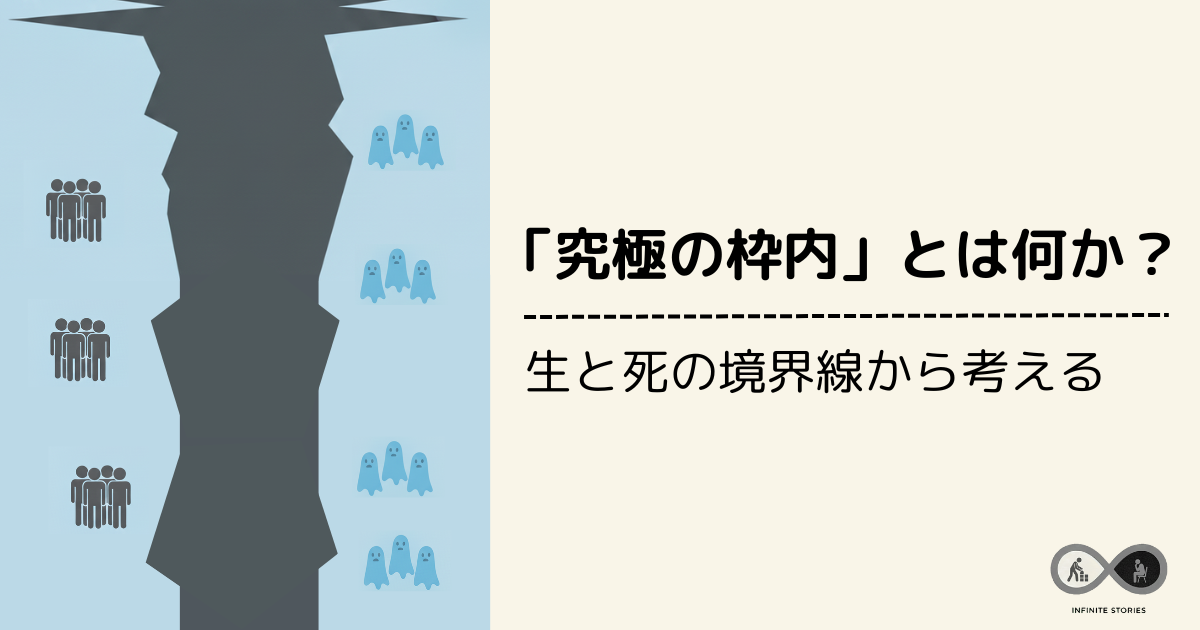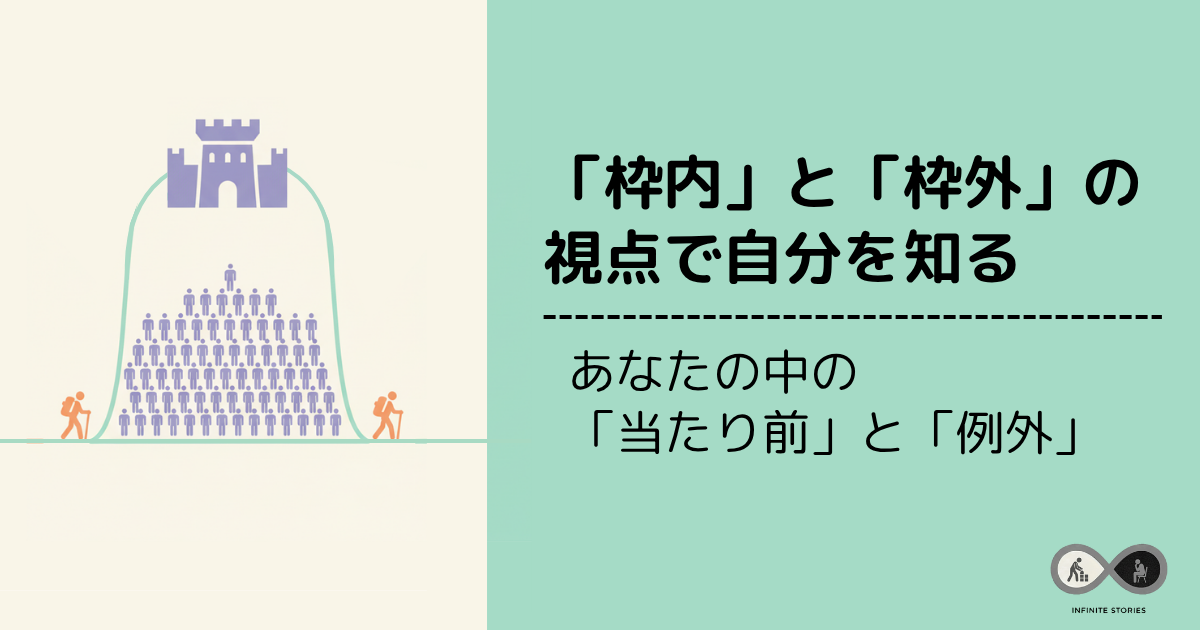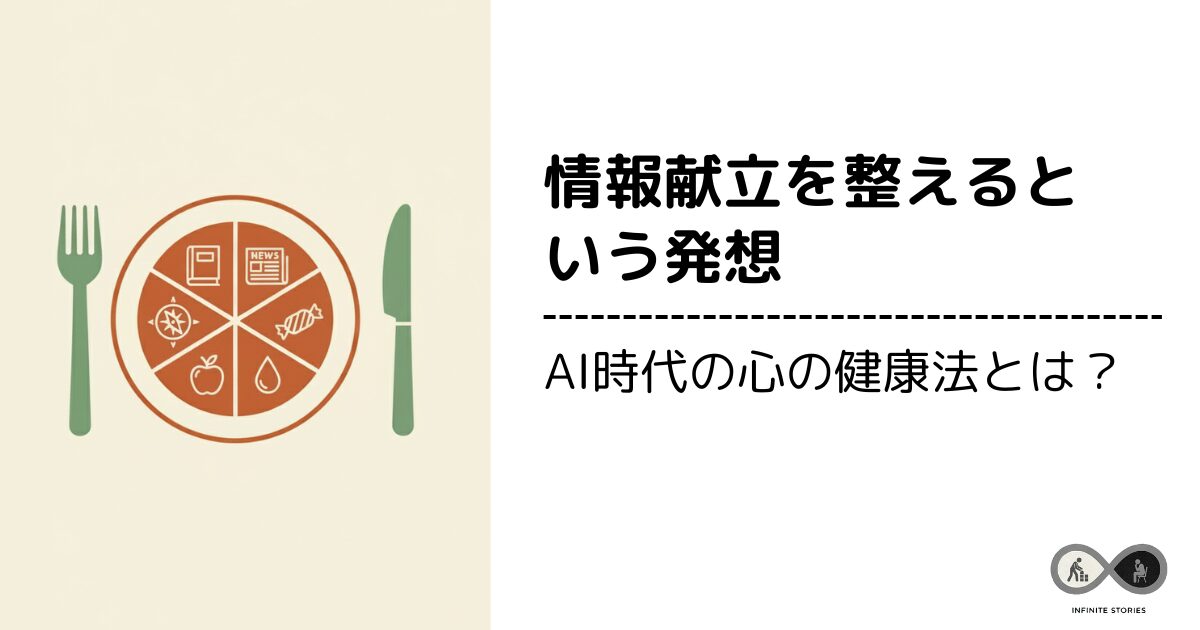なぜ健康に「物語」が必要なのか?:体の健康フレームで考える“心の健康”習慣

一言サマリー
「リアルな物語」や「客観的な指標」という生活習慣病を予防するために必要な考え方を、心を健やかに保つ「内面世界の複雑化」にどう活かせるかを探ったエッセイです。
要点まとめ
- 人が行動を変えるのは「命を落とすかも」といったリアルな物語が生まれたときである
- ただ主観は簡単に嘘をつくため、体重やBMIなど客観的な指標で振り返ることが重要
- 内面世界の複雑化とは、自分自身や外の世界を多面的に見つめる心の健康習慣を指す
- 内面世界の複雑化も同様に、リアルな物語と客観的指標が必要
- たとえばストレスが溜まると無意識にやってしまう行動(食事量、買い物、飲酒量など)を客観的指標にする
- 完璧を求めず、余裕に応じて複雑化と単純化を使い分けることが本当の意味での内面世界の複雑化である
音声コンテンツはこちら
notebooklmによる音声概要
世界を単純に見すぎることが健康に悪く、ときには命に関わることもある。
前回は、それが糖尿病などの体の健康と同じ枠組みで考えられるというお話をしました。
今回は、体の健康を保つための考え方を、心の健康を保つための「内面世界の複雑化」に利用できるのではないか?ということについて考えてみたいと思います。
目次
体の健康習慣について
まずは体の健康習慣はどうやって身につけられるか?ということについて考えてみましょう。
例えば、健康診断で血糖値が高くなりはじめ「このままだと糖尿病になりますよ」とお医者さんに言われたシーンを想像してみてください。
そのあとに「食事を見直して、運動もしてくださいね」とアドバイスされても、すぐに食事や運動の習慣を変えられるでしょうか?
ほとんどの場合は「それができたら苦労しないよ……」って思いますよね。
外食が多くて運動不足。お酒の量も増えて、つまみもついつい食べてしまう――そうした生活習慣が体に良くないのは、頭ではわかっています。
だからこそ健康診断の結果が悪くなってしまっている。
でも、そうした“体に悪い”習慣は、ストレスや忙しさに追われた結果、仕方なく身についてしまった面もあると思います。
「ストレスが多いから、晩酌しないとやってられないよ…」
「仕事や育児に時間を取られて、どうしても自分の食事は適当になっちゃうんだ」
「疲れ切っているから、そこからさらに運動する元気が出ないんだよね」
そんな欲求や習慣が根っこにあるからこそ、頭ではわかっていても健康的な生活ができない。それが実情だと思います。
どんなときに習慣は変わる?
でも、そんな生活習慣が変わってしまうこともあるんです。
それは、“今までの習慣を吹き飛ばすほどの物語”が自分の中に生まれたときです。
これは、ネガティブなパターンとポジティブなパターン、両方が考えられます。
ネガティブな場合とは実際に病気になってしまうケースです。
お医者さんに「このままだと危ないですよ」と忠告されても行動を変えられず、糖尿病になったり心筋梗塞になったりして手術にまで至ってしまう。
すると「次は命を落とすかも」という恐怖の物語が生まれます。
そんなとき、人は生活習慣を変えていくんです。
「もっと早くから節制しておけばよかった」と後悔しながらも、習慣を変えていきます。
それは「命を落とすかも」という物語がリアルに感じられるようになったからなんですね。
反対にポジティブなパターンは、好きな人ができて「振り向いてほしい」「魅力的に見られたい」という気持ちが芽生えたときなどです。
そんなとき人は相手から魅力的に見えるように生活習慣を変えたりします。
そこには「付き合えるかも」という期待の物語が生まれるからです。
だからこそ食事制限や運動をして生活習慣を変える。このとき、その人には悲壮感はないですよね。
むしろドキドキして、付き合えたときの妄想を楽しむこともあるんじゃないでしょうか。
好きな人から「痩せた?」なんて言われたら、天にも昇る気持ちかもしれません。
いずれの場合も、行動が変わるきっかけは“リアルに感じられる物語”が存在することです。
そして実はどちらも「物語」であることに注意が必要です。
「命を落とすかも」「付き合えるかも」というのは物語なんです。
実際に死んでいるわけでもないし、好きな人と付き合っているわけでもない。
絶望や期待の物語が存在しているだけです。
そして物語にリアルさがないと行動は変わらないんです。
物語にリアルさがないと人は変わらない
生活習慣病は少しずつ進行して悪くなっていきます。
そのため最初の段階でも「このままだと命に関わりますよ」と注意されるんですよね。
でも、そこにリアルさがないから生活習慣は変わらない。
また好きな人ができても、その人が高嶺の花で「自分が付き合えるわけない」と思ってしまえば行動を変えません。
「付き合えるかも」という物語にリアルさがないからです。
だからリアルさを伴う物語がないと、人は本能を抑えて行動することはなかなか難しいんですね。
リアルな物語が生まれるだけでは健康にはなれない
ではリアルな物語が生まれて行動習慣が変われば、体は健康になるのでしょうか?
実は、それでもうまくいかない場合があるんです。
それは間違った健康習慣を取り入れてしまう場合です。
人には楽をしたいという本能があって、話題のダイエット法ほど目につきやすいというバイアスも持っています。
だから手軽にできるダイエットに手を出しがちなんですよね。
でも健康的な生活習慣って、実はあまり面白くないし根気のいるものなんです。
「消費カロリーを上回らない適量の食事」「バランスの取れた栄養」「定期的な運動」――言葉にするとこれだけです。でも考えることは多いんですよね。
自分の1日の消費カロリーや必要な食事量は?
バランスのよい食事って具体的にはどんなメニュー?
体を壊さない程度の運動量って週にどれくらい?
健康習慣を取り入れられるように仕事や育児に余裕を持たせられる?
仕事や育児の合間にできる運動はある?
実際は自分に合ったやり方を見つけるために、いろいろと調べたり工夫したりする必要があります。
客観的な指標を作ることの大切さ
リアルな物語が自分の中で生まれ、自分に合った健康習慣も設定した。
あとはひたすら実行するだけで健康的な体になるでしょうか?実はもうひとつ注意することがあります。
それは、人は自分自身に嘘をつくこともあるということ。その嘘で体を壊さないように客観的な指標を用意する必要があるんです。
人はすぐに自分の都合のいい物語を作ってしまいます。
例えば年齢を重ねたり仕事や家庭の環境が変わったりして、最初に設定した食事や運動が自分に合わなくなることが起こります。
そんなときでも最初に丁寧に考えた習慣を「達成しなければ」と、考えを変えられなくなってしまうことがあります。
これは自分が作った物語に縛られている状態です。そうならないためにも客観的な指標を用意しておく必要があります。
以前も書いたことがありますが、人は自分の物語に縛られて拒食症になったり、運動依存症になったりして、逆に体を壊すことがあるんです。
∞TORY


短時間睡眠の落とし穴:『平気』と思い込む前に知るべき主観の怖さ
“平気”の思い込みに要注意! 『短時間睡眠でも大丈夫』…そう自分に言い聞かせていませんか? 実はそれ、心の声を無視する落とし穴かもしれません。頑張るあなたに知ってほ…
だから必ず自分の健康に関する客観的な視点も必要になります。自分にとって適正な体重や体型はどれくらいか。主観を入れない指標が必要なんですよね。
もし最初に設定した生活習慣に固執してしまうなら、1ヶ月のうち何日間、健康的な食事や運動ができたか測る達成率という指標も必要かもしれません。
達成率が50%を下回ったら、今の生活に合った健康習慣でないから考え直す必要があると決めておくなど、主観にだまされないように注意します。
また健康習慣を取り入れたのに、健康診断で数値が悪くなっている。
そうであれば、いくら自分の主観に問題がなかったとしても、何か問題がないかを振り返るようにしましょう。
体の健康のために必要なことをまとめると以下のようになります。
・行動を変えられるような物語を生む。
・適切な健康習慣を考え実行する。
・問題ないかを客観的指標で振り返る。
このように体の健康習慣は、どれも根気よく続けないと維持できないようなものばかりですね。
内面世界の複雑化に当てはめると……
では、ここからが本題です。これらの考え方を、心の健康を保つための「内面世界の複雑化」に当てはめてみましょう。
行動を変えられるような物語を生む
これは、内面世界の複雑化に取り組みたいと思える物語を生み出すことです。
内面世界を複雑化してみようと思うためには、“単純化した世界観では危険かもしれない”とか、“複雑に見たほうが自分にとってメリットがある”といった物語を、自分の中でリアルに感じる必要があります。
リアルさを感じるには自分自身で物語を考える必要があります。
わたし自身、他の記事でも「内面世界を複雑化する方法」についていろいろ書いているので、よかったら参考にしてみてください。
適切な習慣を考えて実行する
内面世界の複雑化において、適切な習慣とはどのようなものでしょうか?
前述したように体の健康習慣に王道はありません。それならば内面世界の複雑化にも王道はないのでしょう。
つまり単純化しないで物事を見ることを繰り返すということです。
もちろん言うのは簡単ですが、実践は難しいですよね。
私自身がやっている方法を例に挙げてみます。それは多面的に自分自身や外の世界を見つめるということです。
自分自身を多面的に見るのは、以前「解像度を上げる」という記事で書いたことがあります。
∞TORY

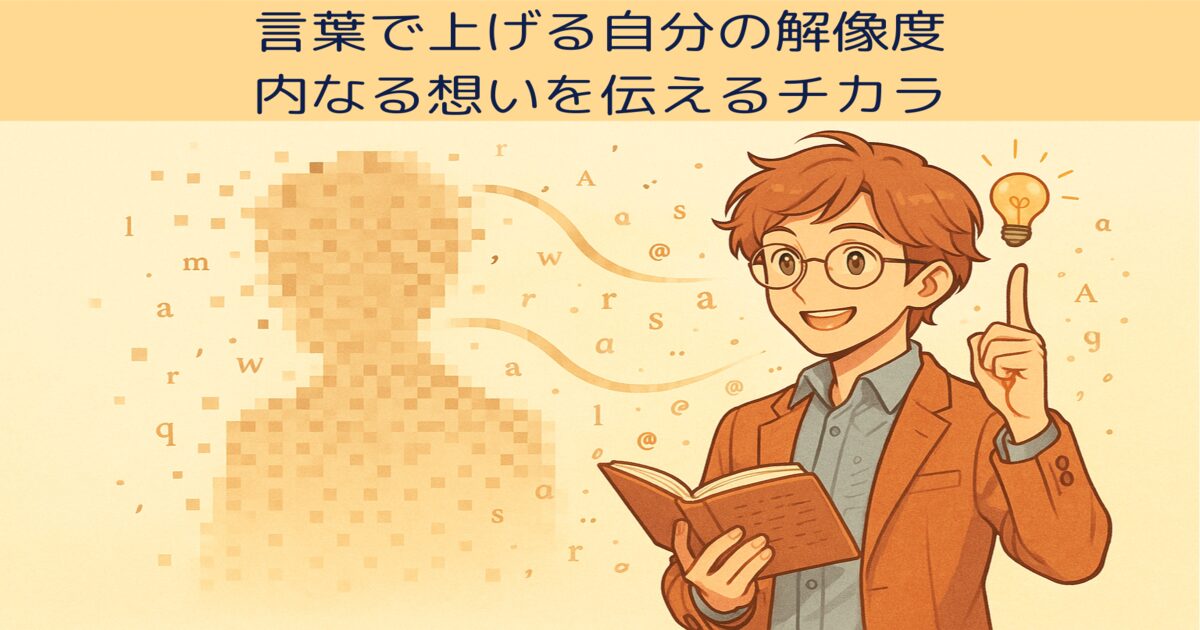
言葉で上げる自分の解像度:内なる想いを伝えるチカラ
自分のこと、ぼんやりとしか見えていない気がしませんか。言葉が心のピントを合わせ解像度を上げる――内なる世界と外の世界をつなぐカギを探る物語です。
自分の好きなことや趣味について、なぜ好きなのか、なぜ趣味としてはまっているのかを掘り下げてみる。
好きなことだけでなく、嫌いなことやつらく感じることも、余裕がある範囲で掘り下げていく。
また外の世界を多面的に見ることは、人のいろいろな考えに触れることだと思っています。
立場が違えば考え方も変わりますよね。ひとりの人間でも家庭と職場では考え方が違うこともあります。
また、ひとつの出来事でも賛成と反対の立場では考え方が違います。
そのようないろいろな考え方という物語を丁寧に集めてみる。
これも地味で面倒くさい方法ですが、内面世界の複雑化に必要な行動だと思っています。
問題ないか客観的指標で振り返る
内面世界の複雑化が間違った方法になっていないか、客観的な指標で振り返ることはできるのでしょうか?
そもそも内面世界の複雑化は心の健康のために取り組んでいます。
視野が狭くなることや孤立を防ぎ、心のストレスを減らすために必要なことだと思っています。
それならば内面世界の複雑化の方法が間違っているときは、心のストレスが増えていくはずです。
でも心のストレスを直接測るのは難しいですよね。
唾液を使ったストレス検査などもありますが、郵送が必要だったり有料だったりと使いづらいものです。
そこで、私が取り入れているのは「ストレスが溜まると無意識にやってしまう行動」を指標にするという方法です。
例えば私の場合は、ストレスが溜まると食事や間食の量が増えてしまいます。
たくさん食べてストレスを発散したいという欲求があるんです。
そのため体重を体の健康指標だけでなく、ストレスの指標にも利用しています。
もし体重がじわじわと増加しているなら、「あれ、実はストレスを溜めているのかな?」と振り返ります。
そのことに気がつくため、毎日体重計に乗って体重の変化を確認しています。
他にもお酒やタバコでストレスを発散している人なら、その消費量を記録するといいかもしれません。
習慣化しているものでも、その消費量の増減を見ればストレスの指標になります。
買い物でストレスを発散する人なら明細の金額を指標に、運動がストレス発散になる人なら運動時間を指標にするなど、いろいろなパターンが考えられます。
それらの情報によって心の平穏が保てているかを確認するんです。
内面世界を複雑化して心の健康を保っているはずなのに、客観的指標が悪化している。
それならば何か無理したり間違えたりしていないか振り返ってみる必要があります。
常に内面世界を複雑にする必要はない
体の健康習慣に必要な要素を、「内面世界の複雑化」に当てはめて考えてみました。
はたから見ると“内面世界を複雑化しよう”なんて考えるのは、ごちゃごちゃしていて大変そうに見えるかもしれません。
でも私自身は、心の健康のために必要なトレーニングのようなものだと思っています。
そのため最後にひとつ付け加えておきたいことがあります。
それは「常に内面世界を複雑化する必要はない」ということ。
余裕がなければ複雑に考えることはできないし、単純化するのは心を守るために必要なことでもあるんです。
それに「複雑化することがいい。単純化はよくない」という考え自体が単純化した考え方でもありますよね。
ダイエットだって疲れ切った日にはうまくできません。
むしろ、そんな日は体を休めたり、好きなものを食べたりしてエネルギーを充電する方が続けやすいものです。
同じように心に余裕がないときは、単純化することも許してあげましょう。
あるときは単純化してしまうし、ある場面では複雑に考える。そのことを自覚したりしなかったり。
そのような自分を受け入れていくことが、本当の意味での内面世界の複雑化なのかなと思っています。
おわりに
「体の健康習慣」と同じフレームで「心の健康」を考えてみると、意外なほど共通点があると思います。
人は“リアルな物語”が生まれたときに行動を変え、本当に必要な習慣を身につけようとする。
そして主観に流されすぎないよう客観的な指標を用意して、柔軟に軌道修正していく。
それらは体の健康を保つためだけでなく、心の健康を保つためにも役立つ考え方なのだと思います。
ただし、どんなに良い方法でも、常にパーフェクトにやり続ける必要はありません。
自分がいまどんな余裕をもっているのか、何を求めているのか。そこを素直に認めながら、ときには複雑に、ときにはシンプルに――そのバランスを楽しみつつ、心と体の健康を育んでいけたらいいなと思っています。
よろしければcodocで投げ銭していただけると、創作時間の捻出にもつながり励みになります。
また感想や共感したポイントがあればXでぜひ教えてください。下のXボタンから共有ポストできます。