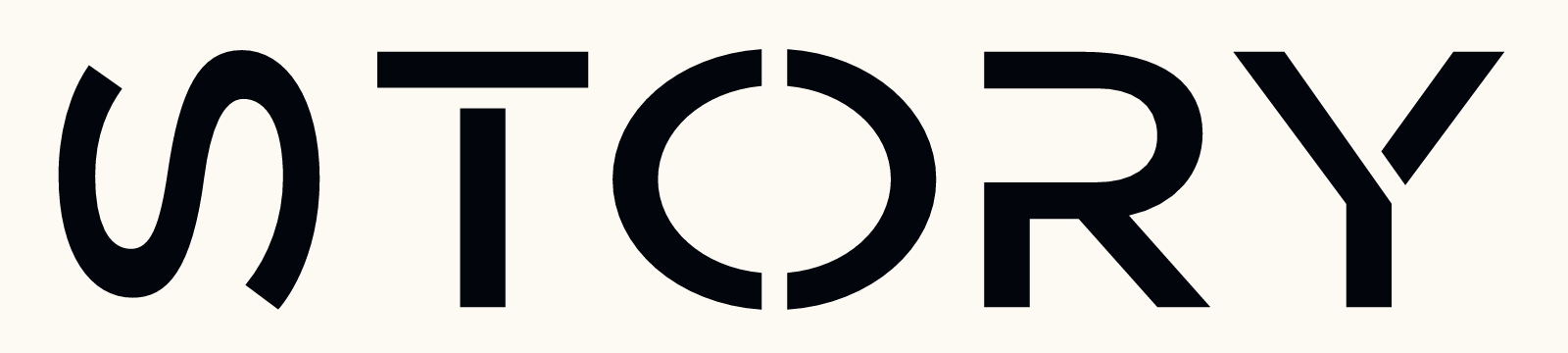第三十四話 デート
忌子は離れの家に置いてある鏡台を覗きこむ。頬の擦り傷の痕もほとんど目立たない。うっすらと痕が残っているだけだ。一瞬、ファンデーションで隠そうかなとも思うが、気を取り直してそのままにしておく。これから行く場所だったら、この痕は隠さずに行くべきだ。そして鏡に全身を映して服装や髪形におかしなところがないかを確認する。机の上にあるつばの広い白の帽子を手に取りかぶり、もう一度鏡で全身を見た。
普段、着慣れないワンピースと帽子に不安を持ちつつも美友紀のお墨付きであることを思い出す。その言葉を信じて忌子は玄関へと向かった。
玄関を出ると、強烈な日光が差してくる。八月に入りすでに夏真っ盛りだ。日傘も取り出し開く。真っ白な傘が日差しを遮る。
日傘で日光を遮っても、夏の暑さは容赦ない。歩きながら少しずつ汗をかいてくるのを感じる。全身に汗がにじむ頃、忌子は龍神橋にたどり着いた。
橋の中央には欄干に腕を乗せ体を預けながら龍神川を眺めている秀俊の姿があった。
「ごめん! 待った?」
急ぎ足で秀俊の元へと駆け寄る。
「大丈夫。今来たところだから」
その言葉に安心しながら、忌子も一緒に龍神川を眺める。あのときの濁流が嘘みたいに今日の流れは穏やかだ。陽の光に反射した川の流れが美しい。
「もう体はなんともない?」
秀俊がこちらに顔を向けて心配そうに尋ねる。
「うん。もうバッチリ。なにひとつ悪いところはないって、かかりつけの先生も太鼓判を押してくれたから」
あとから彼に聞かされた話では神楽を舞った後、橋の上で心臓が止まって倒れていたらしい。
「ありがとう。あのとき助けてくれて」
橋のたもとにある榊に目をやる。そこには裂けるように焦げたひび割れがある。木に雷が落ちた衝撃で倒れたのだろう。
「良かった」
一安心した様子で彼はこちらを見つめてくる。その視線に気恥ずかしさを感じてしまう。
「そろそろ時間だし行こっか」
その気恥ずかしさを隠すために忌子は先導を切って駅の方へと歩き出す。彼も横並びで一緒についてくる。
「今、家の方はどんな感じ? こっちはなんとかやっていけてるけど。まあ母さんは家に帰ってから、ぼーっとしていることが多くなったかな」
秀俊が前を見ながら近況を語り始める。あの日、彼の母親も病院で目が覚めた。体に異常は認められず、すぐに退院できたそうだ。
「こっちも同じような感じかな。龍神様のたたりが起きるかもって父様は結構びくびくしてることが多いけど」
忌子は苦笑しながら話す。その様子に秀俊はちょっと驚いているようだった。しかし忌子はたたりなんて起こるわけがないと思っている。それならあのときに死んでいたはずだ。
清司がつらそうにしているのを見るのは複雑な心境だ。そんな姿は見たくない。元気になってほしい。それは偽らざる本音だ。しかし、あんなひどいことをしたんだから罰が当たって当然。その姿にスカッとしている自分もいる。それも正直な気持ちだ。
「でも氏子さんたちも手伝ってくれてるから大丈夫。今のところ滞りなくできているから」
それに自分には呪いの影響が出てしまうほどの縁が結べている人がたくさんいる。みんな呪いにかかっていたときのことは都合良く忘れていた。自分に向けられた仕打ちはなにひとつ覚えていなかった。でも、それでもいいと忌子は思える。だってそれは呪いのせいだから。そして、それは縁を結んでいてくれたということだから。
「そっか。八乙女さんは強いね」
秀俊がほほ笑むのを見て頬が赤くなる。そして今の言葉を聞いて、忌子は考えていることを伝えようか迷った。しかし、この場で言うのはどうしても恥ずかしくてできなかった。