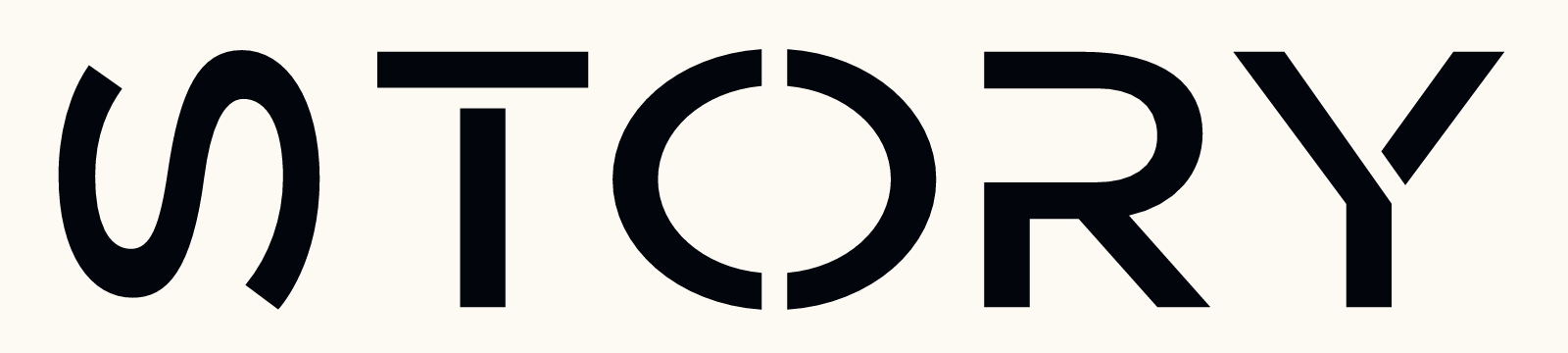第三十話 縁を結ぶ
龍奉神社の片隅にある倉庫。ここは神社で昔から残されている古文書や美術品など歴史的に価値がある資料を保管する場所だ。ときおり博物館に貸し出して展示するようなものも残されている。価値のあるものを保存するため、倉庫は暗証番号によって施錠されていた。
博物館に貸出する際の搬出口が建物の裏手にあった。忌子はそこに向かい暗証番号を入力して中に入る。扉を閉めると自動でロックがかかる。日の光で所蔵品が傷まないように窓はついておらず中は真っ暗だ。手探りで扉の脇にある電灯のスイッチを入れると蛍光灯によって部屋の中が照らされる。中は保存を目的とした空調設定のため、少し埃っぽいが過ごしやすい。
鍵のかかった室内に入ったことで体の緊張が解ける。仲間たちのことは心配だがここで待つしかない。
椅子などはないため地べたに並んで座り込む。雨脚が強くなってきたのか天井に雨が打ちつける音だけが響いていた。しかし突然秀俊がああっと声を上げる。彼の方に顔を向けると頭を抱えていた。
「ごめん。僕のせいだ。儀式を壊したせいで、みんなにも迷惑をかけて」
「そんなことない。来てくれて助かったよ」
後悔する秀俊を慰める。
「そんなんじゃないんだ」
そう言って、彼は体育座りしている膝へ顔をうずめてしまう。彼のその無言の圧力につい口を閉ざしてしまう。
「そもそも僕はここに来るつもりはなかったんだ」
重い沈黙の時間が流れている中、彼がまた話し出す。
「呪いのかかっていない自分に君を助ける資格なんてないと思って」
彼はいまだに呪いが起きていない。それは自分と縁が結ばれていないから。
「それでも本当にうれしかった」
清司と同じ状況なのに、なぜか忌子は今の秀俊に対しては縁が結べていなくてもつらいと思わなかった。彼は一瞬顔を上げてこちらを見るが、すぐ顔をうずめてしまう。
「呪いの原因が自分の母親ってことがわかったとき、自分のバカバカしさに気づいたんだ。あれだけ呪いをなんとかすると思っていたのに、原因が自分の家族だったなんて」
自嘲気味にふっと乾いた笑いを吐いたら、また押し黙ってしまった。
「田島くんは悪くないよ。全部父様がやったことなんだから」
その言葉に胸が痛む。彼を慰めるつもりで言った言葉に自分の心が傷ついていた。
「ごめん。そんなこと言わせるつもりじゃ」
「いいの。だって本当のことだし。でもだからこそ田島くんの気持ちもわかるよ」
自分の家族が自分自身を苦しめる存在。そのつらさを。今、身にしみて感じている。自分自身の一部が失われ、穢れてしまう感覚。そのことで身が引き裂かれるような思いがする。
清司は忌子のためと言っていた。産まれたときの穢れを浄化するために龍神に嫁がせようとする行為。それは愛ゆえになのだろうか。
清司は呪いの影響を受けていない。その事実が、忌子を苦しませていた。
「儀式をめちゃくちゃにしたのも自分の憂さ晴らしだったんだ。君のお父さんと、自分の家族がだぶって見えてきて」
その言葉を聞いて、忌子は彼の母親、愛美の姿と自分の父親である清司の姿を重ね合わせる。そして彼の過ごしてきた環境に思いをはせた。
今の自分のような心境で彼は長く苦しんでいた。それはいつからなのだろう。彼の父親が亡くなったとき? いやもしかしたらもっと前からかもしれない。そんな様子は微塵も感じなかった。彼はいつも飄々としていたが、その裏にこんな気持ちが隠されているとは思いもよらなかった。おそらく知られないよう必死に努力していたのだろう。
「憂さ晴らしでもなんでもいい! だって私はそれで救われたんだから」
顔をうずめたまま話す秀俊に対して必死に声をかける。これ以上、彼に自分を責めてほしくなかった。その姿に自分自身を重ね合わせていた。
忌子の突然の大声に秀俊は顔を上げて、こちらを向く。しかし視線はわずかにそれて忌子と合っていなかった。その姿がいつもの秀俊であることに気がつく。
彼はいつも目線をわずかにそらしていた。おそらく誰とも目線を合わせることはなかったのだろう。忌子は腰を上げて秀俊に近づき、目の前にしゃがみこんだ。手を伸ばして彼の両肩に置く。
「田島くんがどんな気持ちでいたって関係ない。それがどんなに自分のためだったとして、私のことなんてどうでも良かったとしても。それでも私は田島くんが取ってくれた行動に救われた。家の事情が知れてしまっても。お母様が私に呪いをかけていたとしても。それでも私はあなたに救われたって気持ちは変わらない」
しゃべっていくうちに両手に力が入っていき、彼の両肩を強くつかむ。その力とともにこの言葉が彼に届いてほしいという祈りを込めて。
「八乙女さん……」
その瞬間、彼と目が合う。黒い瞳の表面が蛍光灯の光で反射していた。その瞳から一筋の涙があふれ出したとき、彼は突然忌子の両腕を振り払いうずくまる。体を丸めて、こちらに背中を向けたまま彼は苦しそうにうめき声を上げている。
「田島くん?」
突然様子が変わってしまった彼の背中に手を伸ばそうとしたとき。
「触るな!」
彼は腕を伸ばしながら、こちらを振り向く。その伸ばした腕に自分の手がぶつかり振り払われる。手に痛みが走り思わず顔をしかめた。手をさすりながら秀俊に目をやると、彼は立ち上がりこちらに近づいてくる。そのときの表情を見て忌子は恐怖を覚えた。
彼の口元は笑っているのに、瞳が笑っていない。目に光はなく感情が失われていた。
秀俊は忌子の胸ぐらをつかみ意味がわからない言葉で怒鳴る。その声量に思わず耳をふさぐ。
「やめて!」
強くつかまれた巫女装束で胸が絞まる。彼の指は赤くなるほど強く握られており、忌子の力では指一本解くことすらできなかった。