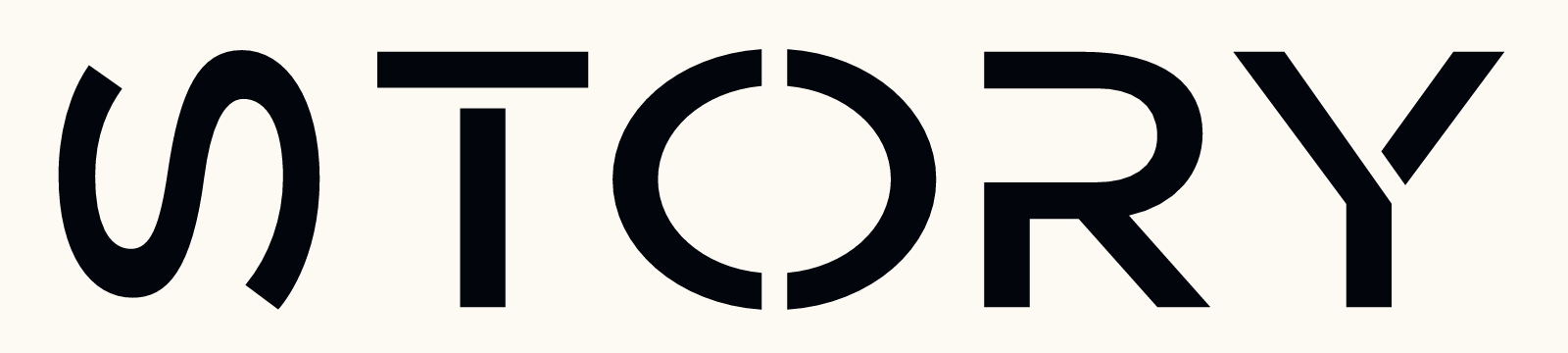第二十二話 儀式
「さあ入りなさい」
涙を拭った清司が忌子に内陣に入るように促す。内陣は基本的に宮司しか入れないため、ここには初めて足を踏み入れる。外陣までしか入ったことがない忌子にとって本殿は気持ちを落ち着けることのできる場所だった。しかし内陣から発せられる威圧するような気配に初めて忌子はこの場所に気後れする。
しかし清司の言葉に導かれるように忌子は内陣へと入っていた。
「忌子、龍神様にご挨拶を」
言われるがままに忌子は正座して頭を垂れる。しかし頭の中では今の状況を理解しようと思考を続けていた。
清司の感情がわからない。忌子にとって彼は完璧な存在だった。神事に対する向き合い方、穢れに対する潔癖さ、そのどれもが忌子以上に徹底しておりその姿は目標でもあった。感情をあらわにすることは忌子の記憶にある限り一度もない。
そんな清司が涙を流していた。しかし、今はいつものように神様への挨拶として祝詞を読み上げている。その抑揚の効いた独特な話し方に震えは感じられず、先ほどまで涙を流していたとは到底思えない。隣から聞こえる彼の声からはいつもの清司の姿しか思い浮かばない。
そのとき忌子の脳裏にかすめるものがあった。それは愛美の姿だった。あのとき。仲間たちとともに秀俊の家に入った後。彼女は秀俊から呪具を奪い返し、神棚に祀り直した。そしてすぐに彼女は儀式を始めた。そのときに吐いていた言葉には聞き覚えがあったことを思い出す。
あのときは仲間がすぐに止めてしまったため考える時間がなかった。
今思うと、あれは祝詞だった。
頭を垂れながらも忌子は清司の祝詞に耳を傾ける。今、唱えているのは一般的な奉仕の際に唱える祝詞で彼女が唱えていたものとは違う。しかしどこかで聞き覚えがあった。必死に記憶をたどる中でついに忌子は思い当たる。
それは祭りのとき、清司が唱えていた祝詞と同じだった。
神楽の前に清司が刀を持ち、忌子に対して振り下ろしながら周りを回るときに唱えていた祝詞、それと愛美が唱えていた言葉が一緒だった。
忌子はたまらず立ち上がる。なぜ愛美が唱えていたものが神楽の祝詞と一致するのかわからない。その得体のしれなさが清司からも発しているように感じられ自然と距離を置いた。
「忌子。座りなさい」
祝詞を中断した清司がたしなめるように言う。その有無を言わさぬ言い方であっても忌子は座りなおすことはできなかった。
「父様。呪いの言葉が、神楽と」
頭の中で浮かんだことがそのまま口に出た。その要領を得ない言い方なのに、なぜか清司は理解したかのようだった。そして眉をひそめる。
「忌子。龍奉神社の歴史を勉強しなさいとあれほど言ったじゃないか。だから神楽もきちんと舞えないんだ」
清司が居住まいを正してこちらに向き直る。
「このままじゃ龍神様に失礼だ。忌子。聞きなさい」
清司はにらみつけるように忌子の顔を見た後、龍奉神社の歴史を話し始めた。