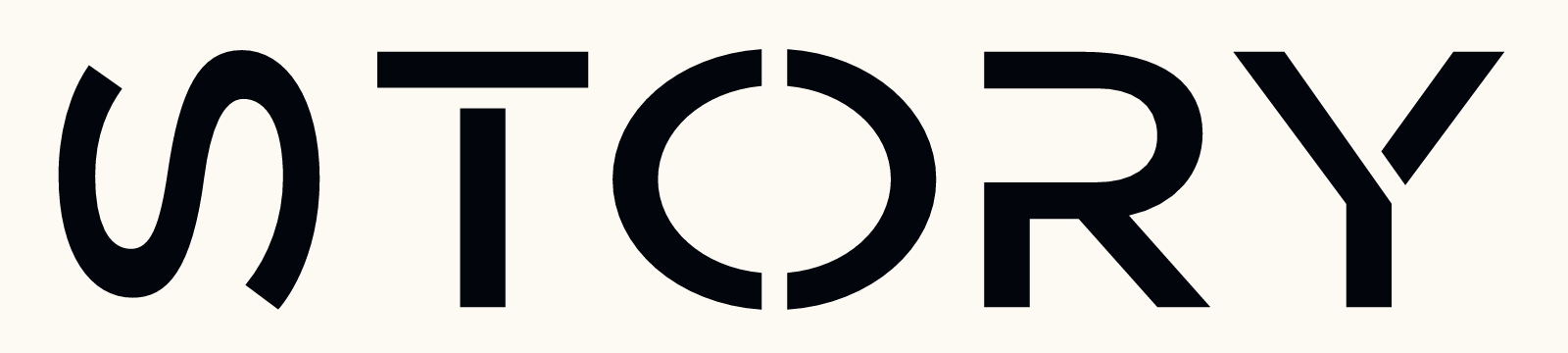第十五話 異変
予備校はここから電車で一駅の繁華街の中にある。そのため楠本の運転する車で移動することになった。自分が普段過ごしている世界とは真逆の喧騒の多い世界。繁華街まで足を伸ばしたことがめったにない忌子にとって、ほとんど未知の体験でありこんな状況にもかかわらず少しばかり興奮していた。しかし、一方で清司に嘘をついてまでこんな場所にいる罪悪感に胸が締め付けられる思いも同時にしていた。
「ここで合ってるかい」
仲間が繁華街の一角にあるビルの前で立ち止まり問いかけてくる。見上げるとビルから道路上に突き出た予備校の名前を冠した看板が目に入った。
「たしかこんな名前だったと思いますけど」
秀俊から昔聞いた予備校を思い出そうとする。しかし大学受験を考えたこともない忌子にとっては自信がなかった。
「まず間違いないんじゃないかな。医学部を目指す人とかがよく通う予備校だし」
楠本が医者ならではの目線で太鼓判を押してくれてほっと胸をなでおろす。
「ならあそこのカフェなら入口を見張れるな」
仲間が指さした先は道路を挟んで向かい側の建物だった。そこの一階はテラス席もあるチェーン店のカフェになっている。そのチェーン店のロゴを見て、昔美友紀と行ったことを思い出す。あのときはたまたま課外学習の帰り際に寄り道をしようと美友紀が無理やり誘ってきた。そのときも良心がとがめつつも初めて行く場所にドキドキしたのを覚えている。
そんなことを思い出すと美友紀からされた仕打ちも呼び水のように思い出されつらくなった。
店の中に入るとさまざまなドリンクメニューが載っている。あのときはさすがに甘いものを飲む勇気は出ず、気が引けて紅茶を頼んだはずだ。しかし今は、あのとき美友紀が頼んでいたキャラメルマキアートを注文する。
少しでも彼女の気持ちを知りたいと思った。あの出来事は呪いのせいだと思いたい。でもまだ忌子は美友紀が本心であんな行為をしたのではないかという想像が頭から離れなかった。彼女のことを今からでも知りたい。それがこの飲み物から得られるのではないか。
テラス席に着き口をつけると想像以上の甘さに舌が驚く。普段、甘いものをあまり口にしない忌子にとっては衝撃的な甘さだった。
「どれくらいで出てくるんだい」
「そんなのわからないよ。午前だけならお昼までには出てくるだろうけど、そこまでは調べても書いてないね」
楠本はスマホで夏期講習について調べているのか、画面を眺めながら仲間の質問に答える。その後は時折今後の相談をしつつも秀俊が出てくるのを待っていた。見逃さないようにするには、あまりしゃべることもできずビルの入口にひたすら目を向けていた。
「おい。出てきたぞ」
お昼近く、日差しがテラスへと届くようになり汗ばみ始めた頃に仲間が声を上げた。秀俊はリュックを背負っていてビルから出ると、そのままひとりで駅の方へと向かっていった。
「行くぞ!」
仲間はすぐに立ち上がり秀俊の方へと向かっていく。忌子も立ち上がるが、テーブルの上に残ったグラスに目を向ける。
「片付けてすぐ追いかけるから、仲間さんと一緒に行ってあげて」
楠本が追いかけるように促した。忌子は頭を下げて礼を述べた後、仲間の元へと駆け出す。
すぐに信号待ちをしている仲間と合流できた。横断歩道を渡ると秀俊の背中が見えてくる。
「田島くん!」
声をかけると秀俊が振り返り目をみはる。
「八乙女さん……」
「どうした。なにがあったんだい。あれだけ乗り気だったのに」
仲間は詰問するかのように畳みかける。
「心配したんだよ。おうちに訪ねても予備校に行っちゃったって言われるし」
忌子も率直な気持ちを伝える。すると秀俊はさらに驚いたようで固まってしまった。
「よく考えたら呪いなんて馬鹿らしいことに時間かけてられないなって」
しばらく黙った後に口を開いた秀俊の声色は低く冷たかった。
「どういうこと?」
「だから君たちにかまける時間はないってこと」
それで話は済んだかのように振り返り歩を進めようとする。突然の変化、それはまるで美友紀のときと同じだった。血の気がさっと引く。これも呪いのせいなのだろうか。もしかして離れの惨状も彼の仕業なのだろうか。そう思った瞬間、秀俊の姿が急に穢らわしく感じられる。
「なにがあった。あれだけ熱心に調べてくれたじゃないか」
仲間が表情を曇らせながら秀俊の肩をつかむ。
「調べたからこそ馬鹿らしいって思ったんですよ。今どき呪いなんて。さすがに本気で信じる方がどうかしてますよ」
振り返り薄ら笑いを浮かべる彼の存在を見て視界がぼやけていく。自分の身に起きたことの原因がわからず、どうしたらいいのかわからない不安さ。その中で仲間たちは道しるべを与えてくれた。その言葉を否定されたことによって、忌子の感情はまた振り出しに戻されていく。
「そうか。もういい。変なことに巻き込んですまなかった」
仲間が秀俊の肩から手を離す。彼はしばらく立ち止まったままこちらを見ていたが、踵を返して駅の方へと歩き出した。
「彼のこと見つけられなかった?」
追いついた楠本が道端で立ち尽くすふたりに駆け寄ってくる。
「何かあったの?」
うつむいている忌子に気がつき彼は心配そうに声をかける。
「とりあえず彼は元気そうだったよ。もう協力はしてくれないみたいだがな」
仲間は怒りと悲しみがないまぜになったかのような声色で答える。
「ごめん。ちょっと状況が見えないんだけど」
道路脇に移動して今起きたことを仲間が楠本に話す。
「それは変だね。もしかして呪いの影響?」
「どうだろう。ちょっと今までと質が違うような気がするんだが」
「たしかに……うわっ!」
突然楠本が声を上げたため顔を上げる。楠本が顔を向けている方を見ると秀俊が走り去っていく姿が見えた。
「今のって彼だよね」
追いかける間もなく姿が人混みに紛れてしまった。仲間も状況が理解できていないようでぼうぜんとしている。
「何かされたのか」
「いや。お尻のポケットに何か突っ込まれたみたい」
楠本がポケットを探り取り出すと、そこには一枚の紙が握られていた。罫線が書かれた紙の一部が欠けている。どうやらノートから一枚破り取った紙切れのようだ。
紙を広げると楠本が驚きこちらへと見せてくる。
「さっきはごめん。夜中に行くから、そのときに説明させて」
そこには殴り書きのように書かれた内容が書かれていた。