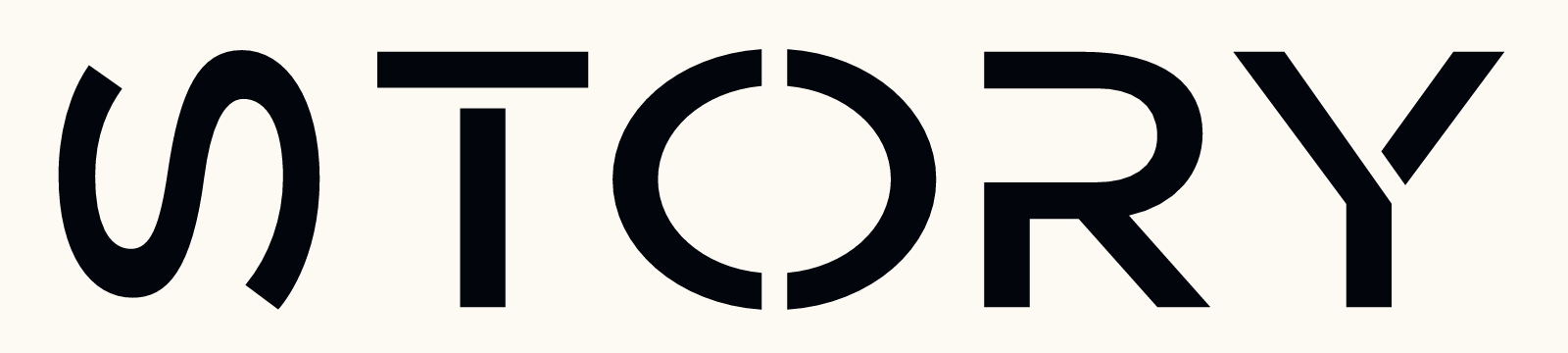第十四話 門前払い
「僕はやめた方がいいと思うけど」
楠本が玄関周りを掃除し終えて戻ってきた後、居間で先ほどの方針を伝えると彼は難色を示した。
「どうしてだ?」
仲間が不機嫌な声を出す。
「だって彼に近づくなって警告してるんでしょ」
「それなら近くまでは一緒に行って、後は私が確認すればいいじゃないか」
「それこそどうやって? 家族の人がいたら僕たちのことどうやって説明すればいいのさ」
楠本にたしなめられて、仲間は勢いを失っているようだ。
「やっぱり、私が行きます」
ふたりのやりとりに対しておずおずと自分の考えを提案する。
「でも……」
楠本が渋い顔をする。
「たしかに、こんな手紙が送られて怖い。でも彼のことが心配なんです」
秀俊は昨日また会いに来ると言っていたのに現れなかった。正直まだ自分に警告が送られてくる恐怖感は強い。それでも忌子はじっとしていたくなかった。それは、あのときの失敗を繰り返したくなかったからだ。
脳裏に浮かぶのは血まみれの男性の周りで心臓マッサージをする楠本や秀俊たち。それを遠くから眺めている自分自身。自分にとっては心に刺さった棘のような思い出。もしあのときに駆け寄れたら、こんなことになっていなかったんじゃないか。
「そうだぞ。秀俊くんのことは心配じゃないのか」
仲間が横から援護射撃してくれる。
「そんなわけないじゃないか」
そう言いながら、楠本は目を閉じてうなるような声を出しながら考えている。
「わかった。でも何かあったらすぐ撤退するよ。特に仲間さんは気をつけて」
楠本の忠告に仲間は口をとがらせながらも、秀俊の家に向かうことが決まった。
清司には体調が優れないため離れで休む旨を伝える。嘘をつくことに慣れてきた自分に罪悪感を覚えながらも今はこれが最優先であると言い聞かせる。
さすがに巫女装束で出歩くわけにはいかないため寝間着からワンピースに着替えて仲間たちと家を出た。
秀俊の家は住宅街の中にある一軒家だ。白い外観の二階建ての建物は他の家より広い。しかし門と玄関の間に生えている草木は荒れていて、あまり手入れはされていないようだった。以前、清司と訪れたときのことを思い出して秀俊の心配が強くなる。
深呼吸して、インターホンに指を伸ばすが、その指が震えていた。意を決してインターホンを押すと呼び鈴がなる。少し待つと女性の声が聞こえてきた。
「はい。あら八乙女さんちの。」
その声は秀俊の母親の声だった。
「忌子です」
「ちょっと待ってて」
インターホンが切れてしばらくすると門の向こうの扉が開き愛美が姿を現した。そのときに忌子以外にも人がいることに気がつきぎょっとする様子を見せていた。
「こんな時間にどうしたの?」
楠本たちに視線を送りながらも忌子に問いかける。
「はい。あの秀俊くんはいらっしゃいますか?」
「あの子なら予備校に行っちゃったけど」
「え?」
「夏期講習に行ってるんだけど、もしかして何か約束でもしてた?」
「えっと……」
想定外の返答のため答えに窮する。
「実は私、民俗学の研究家で今彼女の神社を調査しているんです」
仲間が横から割って入る。
「はあ」
彼女の勢いに押されて愛美は呆けた声を出す。
「そのときに彼も調査を手伝ってくれると言ってくれたんですが、昨日は約束の時間にいらっしゃらなかったので。もしかしたら体調でも優れないのかと心配になってしまって。それで失礼を承知でお見舞いに伺ったのですが」
忌子は心の中で舌を巻く。この絶妙に嘘を言っていない言い方は今まで仲間が培ってきた処世術なのだろう。
「あら。そうだったの。でもごめんなさいね。別にあの子は元気だからお見舞いはいらない。それにあの子にとって今は大事な時期だから、そのお手伝いも難しいと思うわ」
「と言いますと」
「今は受験に向けて大事な時期でしょ。だから勉強以外に手が回らないと思うの。だからお手伝いにも伺えなかったんじゃないかしら。できない約束なんてしちゃだめなのに。本当に申し訳ありません。私からも注意しておきますから」
そう言って深々とお辞儀すると声をかける間もなく彼女は家へと戻ってしまった。
「どういうこと?」
楠本がつぶやく。秀俊は予備校に行ったと母親である愛美は言っていた。それが当然とでも言うように。たしか彼は難関大学を目指していたはずだ。だから彼は祭りに来ることも最初は渋っていた。忌子は祭りに誘われていたときの秀俊の様子を思い出す。
しかし前日の彼はわざわざ予備校に行く前に資料を渡しに来てくれたのではなかったのか。それならば何も言わずに予備校に行っているのは不自然だ。
心配だからという理由で、普通なら胡散臭いと一蹴するような呪いを信じてくれた彼の姿。その姿と何の連絡もなしに予備校に行く彼の姿は一致しない。理由があるのなら、あらかじめ伝える気づかいが彼にはあるはずだ。
「予備校に行ってみませんか?」
気がついたら口にしていた。今の状況ではむしろ彼の方が心配になる。警告文が頭をかすめるが、それでもこのわけのわからない状況を放置したまま帰る方が忌子にとっては耐えられなかった。