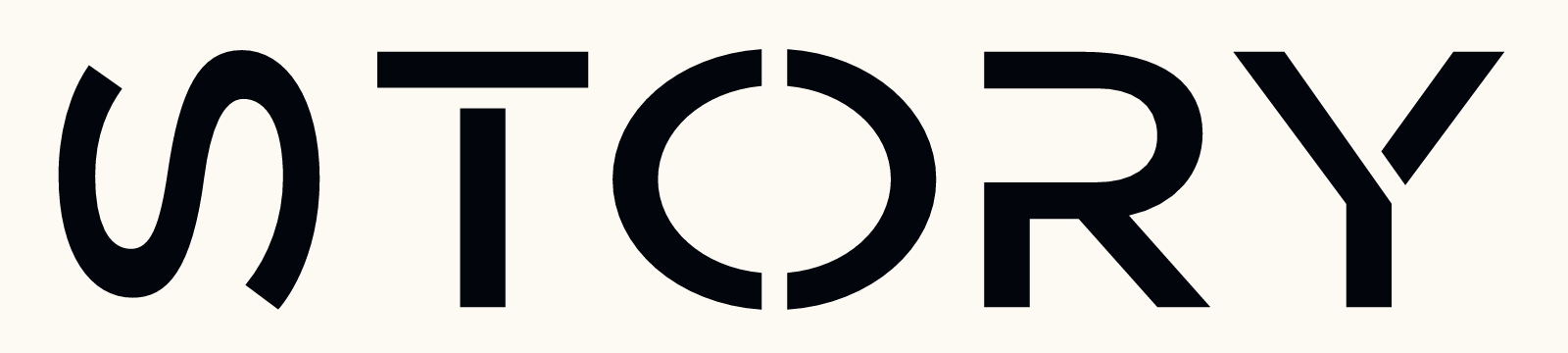第九話 信頼構築
playsinline >
「信頼って呪いがどうこうって話をですか?」
結局この胡散臭い話になるのか。でも目の前にいる彼が霊感商法のようなことをするとは思えない。昨日の診察を受けたときの医師としての姿を思い出して悩む。
「もちろん怪しいのはわかってる。でも何かを売りつけようなんて思っていないし、なんならお父さんを呼んできてもらってもいい。それでもいいからとりあえず彼女の話を聞くだけでもしてくれないかな」
頼み込むように頭を下げる彼の姿を見る。もし何か詐欺のようなものだったら、家族を呼ぶようにお願いするだろうか。その真剣さに心が少し動く。
「ねえ八乙女さん。お父さん呼んでこようか?」
秀俊が声をかけてくる。彼の提案に乗るか迷う。普通に考えれば呼んだ方がいい。でも勝手に神社に来たことを怒られるかもしれないと不安になる。
それにさっき自分には呪いの雰囲気があると言われた。その言葉を信じるなら、自分自身が穢れているようなものではないか。だったらそんな話はむしろ聞かれたくはない。
「話なら私だけで聞きます。ただちょっと場所を移してもいいですか」
神社の中で話していて清司に見つかるのだけは避けたかった。
「田島くん。かばん持ってきてくれてありがとう」
秀俊の方を振り返ってスクールバッグを受け取ろうとする。正直、血で穢れたかばんなんて受け取りたくもないがそうも言ってられない。しかし、手を差し出しても秀俊は考えるようにうつむいていて動こうとしない。
「田島くん?」
声をかけると秀俊が顔を上げる。
「八乙女さん。さすがにひとりだと危ないよ。お父さんの代わりにはならないかもしれないけど、一緒に話を聞くよ」
「でも……」
秀俊の申し出は意外なものだった。ひとりで聞こうとするのは自分の勝手なワガママだ。ただ不安がないと言ったら嘘になる。ひとりになる不安と彼を巻き込むことへの申し訳なさを頭の中の天秤にかける。
「ありがとう。良かったら一緒に来てくれる?」
結局、秀俊にも来てもらうことに決めた。
「じゃあこっちに来てくれますか。えーっと」
「僕は楠本優一、こっちの女性は仲間侑香里」
名前がわからず口ごもっているところで、すかさず楠本が自己紹介をする。
「楠本さん、仲間さん。こちらです」
改めてふたりに声をかける。
「協力してくれてありがとう。ちなみに君の名前も教えてくれないか」
「八乙女忌子と申します」
仲間の質問に答える。
「忌子? 巫女さんらしい名前と言えば名前だけど」
仲間が眉をひそめながらつぶやく。
「はい。お父様が名付けてくださいました。まあ友達からはキコって呼ばれたりもしますけど」
言いながら美友紀のことを思い出して心が痛くなる。
「キコ。いいあだ名じゃないか」
仲間が顎に手を当てながらうなずいている。
自己紹介が終わったところで歩き出す。せめて境内から出て話をしたいと思い鳥居の方へ向かった。歩きながら仲間が言っていたことを改めて考える。彼女は呪われていると言っていた。
そもそも呪いなんてものがあるのだろうか。呪われた人形をお祓いしてほしいと清司がお願いされているところを見たことがある。祓いの儀式をするときも穢れるからと実際に立ち会うことはなかった。
しかし儀式が終わった後の清司の口ぶりからは決して呪いが本当に存在しているとは思っていない様子だった。呪いがあるというよりは、そう思い込んでいる人の不安な気持ちを取り除くために儀式をやっている。忌子はそんな風に受け取っていた。
鳥居をくぐり抜けて参道を歩いていく。もう少し歩けば東屋があるはずだ。そこならある程度人目につくし、何かあればすぐに逃げ出すこともできる。忌子はそこで話をすることに決めていた。
「危ない!」
突然、仲間の声がかかり振り返ると彼女が目の前にいた。気がついたときには視界が仲間の体によって遮られ、勢いに押されて倒れ込む。仲間が覆いかぶさってきたと気づくと同時に急に鼻のつく臭いが漂ってきた。
「仲間さん!」
楠本の声が近づいてくる。また「八乙女さん!」と秀俊が駆け寄ってくる声も聞こえる。仲間が離れ、その姿を見て驚く。彼女の全身は生ごみにまみれていた。彼女の後ろにはポリバケツを抱えた巫女姿の女性がこちらをにらみつけている。
その女性はさっき見かけたバイトとして来ている子だった。彼女はいつも優しく参拝客に対応しているし忌子に対しても親しく話しかけてくれることが多かった。
しかし、そんな彼女が今はこちらをにらみつけている。しばらくすると彼女はポリバケツを放り投げて、神社へと戻っていった。
「大丈夫かい?」
生ごみにまみれながら彼女は心配そうにこちらを眺めている。
「ありがとうございます」
お礼を言いながらも忌子は生ごみまみれの仲間に近づくことはできなかった。
「とっさのことだから止められなかった。申し訳ない」
状況を鑑みるに、あのバイトの子が忌子にめがけて生ごみをぶちまけに来たのを仲間がかばったということだろう。仲間の姿が今の自分の姿だったかもしれないと思うと意識が飛びそうになる。
「さすがにこのままじゃ話はできないか。服も着替えないといけないし、また日を改めた方が良いかもしれないな」
顔をしかめながら自分の体を見て仲間は言う。そのとき忌子の脳裏にはある光景がよみがえる。人が倒れていたのに駆け寄れない自分。あのときの後悔が襲ってくる。
「あの。私の家が近いので、そこで着替えませんか。お風呂場や服を貸すこともできますので」
気がつくと忌子は彼女たちを離れへと招待していた。