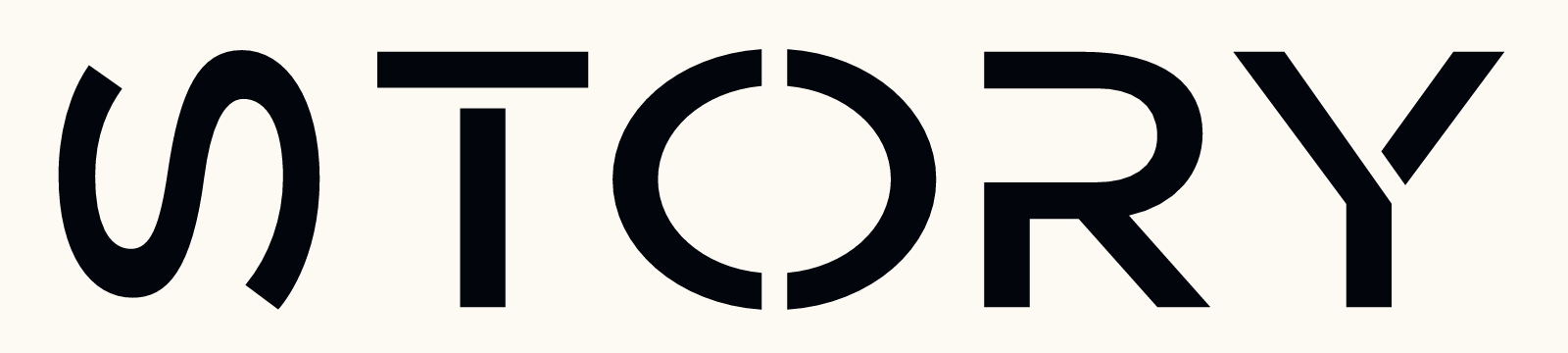第三十三話 解呪達成
全身が震えるほどの轟音が響き渡り、その音で秀俊は目の前に楠本がいることに気がついた。彼は全身がずぶ濡れで、秀俊の体の上に馬乗りになりながら両手で秀俊の腕を抑えている。しかし彼は空を見上げていた。
「楠本さん……」
声を上げるとはっとした顔でこちらを向き抑える力が強くなる。
「なにがあったんですか?」
降りしきる雨が自分の顔にかかり、冷たさを感じながらも秀俊はなにが起こっているのか理解できなかった。
「良かった! 元に戻ったんだね。仲間さんが追手を引き受けてくれたから、僕が車を手に入れて倉庫まで来たんだ。そうしたら君に急に襲われて……」
楠本がほっと安心した様子で秀俊の上から降りる。
秀俊は体を起こしてあたりを見渡した。周りに木々が生えていてすぐ近くには道がある。林に入ってすぐのところで秀俊は楠本に押さえつけられていたらしい。
立ち上がり周囲を見渡すと倉庫が目に入った。さっきまであそこの中にいた。秀俊の記憶がよみがえってくる。あそこで彼女と一緒に楠本たちが車をよこしてくるのを待っているはずだった。それなのになぜ今、自分はここにいるのだろう。
「八乙女さん!」
あたりを見渡すが彼女の姿は見当たらない。なにが起きたか思い出そうとすると、頭の中に痛みが広がっていきおもわず顔をしかめる。しかしその痛みが走った瞬間に彼女の瞳が脳裏に浮かぶ。初めてしっかりと彼女の瞳を見た。その黒く透き通った瞳に吸い込まれたと思った瞬間に自分の記憶は飛んだ。
そして次に思い浮かんだのは、彼女の胸ぐらをつかみ怒鳴っている姿。自分の感情や行動が制御できない感覚。
そうだ。呪いにかかったんだ。
呪いにかかったと気がついても、自分の体は勝手に行動しようとする。それをなんとか振り払いながら外に出たことだけはおぼろげながら覚えている。しかし、そこから先の記憶はなかった。
倉庫の入口に慌てて駆け寄る。扉は完全に閉まり切っておらず、わずかに開いているのを見て嫌な予感がする。もしかしたら他の呪いの影響を受けた人たちがなだれこんだ後なのかもしれない。
意を決して扉を開くが、中には誰もいなかった。
そのとき頭の中に存在しない記憶が思い浮かんだ。降りしきる雨の中、橋の上で踊っている忌子の姿を。
気がついたら秀俊は走っていた。
鳥居をくぐり抜け龍神川へと走る。土砂降りの雨で視界がぼやけ、雨の音だけが鳴り響く。水を吸った衣服のせいで体がどんどん重くなった。まるで行く手を阻むかのように雨は降りしきっている。
橋にたどり着いたとき秀俊はその場で立ち尽くしてしまった。
彼女は橋の真ん中で横たわっていた。橋の向こう側を向いていて顔は見えない。しかし身じろぎひとつせず横たわっている彼女が普通の状態ではないのは明らかだった。
気がついたときには彼女のもとに走り寄っていた。倒れている彼女のもとにひざまずき体をこちらに向けて仰向けにする。彼女は目を閉じて反応を示さない。
「八乙女さん!」
肩をゆすりながら声をかけるが反応はない。どうすればいい? 顔を上げてあたりを見渡すが、この雨の中では誰も見当たらなかった。
彼女の顔や服は泥まみれで、頬に擦り傷があり血も流れている。その血を見たときに彼の頭の中に、ある情景が思い出された。
血まみれの中で心臓マッサージしている自分を。
そうだ。あのときの楠本の行動を思い出す。自分の顔を彼女の口元に近づけつつ、手首に触れる。呼吸はしていない。脈も触れない。その事実にひるみそうになるが、秀俊はあのときの楠本の動きを思い出しまねる。
彼女の胸に手を添えて押し込み、そして緩めた。その行動をリズム良く繰り返す。それでも彼女に反応は見えない。
「行っちゃだめだ!」
腕が悲鳴を上げるまで続けても彼女は変わらず横たわったままだ。必死に呼びかけながら心臓マッサージを続ける。
「田島くん!」
どれくらい続けていただろう。後ろから楠本の声が聞こえた。心臓マッサージを続けながら、顔だけ振り返る。楠本と一緒に仲間も駆けつけていた。
「楠本さん! 救急車を呼んでください。仲間さんはAEDを!」
それだけ伝えたらまた秀俊は心臓マッサージを続けた。龍神の元へと行ってしまった彼女をこの体へと押し戻すために。