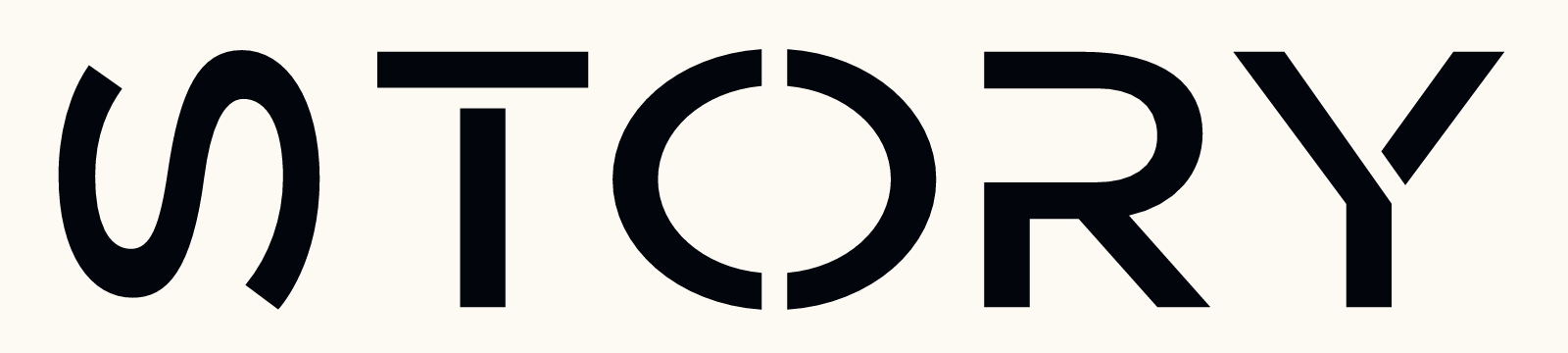第二十七話 破壊
清司の再度の呼びかけにも秀俊はうつむいたままだった。しかし突然顔を上げると中へと無言で入ってくる。その表情からはなんの感情も忌子は読み取れなかった。
「何をしてる!」
清司が声をかけても無視して、秀俊は儀式のための祭壇へと歩を進める。すると彼は祭壇に置かれている円鏡や御幣をなぎ倒した。静寂な本殿に物が倒れる音が響き渡る。彼は床に落ちた円鏡を拾い上げた。おもむろに両手でつかんだ鏡を高くかかげると勢いよく床へとたたきつけた。ガラスが割れる音が響き渡り破片が床へと散らばる。その音に思わず耳を抑え、顔を隠す。
「やめろ!」
慌てて清司が秀俊のもとに近づき肩をつかむ。それを振り払い秀俊は両手で清司の体を突き飛ばした。よろめきながら後退りをする清司が秀俊の顔を見る。
「もう嫌だ!」
足元に散らばる鏡の破片を蹴飛ばしながら秀俊が叫ぶ。今度は三方に置かれた神饌をなぎ倒すと鯛が床に落ち、りんごが転がっていった。瓶子を手に取り床へとたたきつける。お神酒がまき散らされ、水分を吸った木の板の色が変わる。おそるおそる忌子は秀俊の顔を見ると、彼は涙を流していた。
壁際に飾られている真榊や四神旗をなぎ倒したところで彼は動きを止めた。肩で息をしながら袖で涙を拭うと彼はその場で立ち尽くす。忌子があたりを見渡すと儀式のために用意されたものはすべて壊されていた。
その光景を見たとき、忌子は彼の中に自分自身を感じた。こんな風にすべてを壊したかった。呪いについて真相を聞かされたとき。龍神の元へ生贄として捧げられるとわかったとき。そんな儀式はすべて壊したかった。
「田島くん!」
楠本が秀俊のもとに駆け寄る。仲間もややためらいながらも内陣の中に入ってくる。
「大丈夫かい?」
楠本が彼の背中をさすりながら問いかける。
「すみません。どうしても我慢できなくて」
彼は時折しゃくりあげながら答える。楠本は彼の言葉を待つかのように彼の背中をさすり続けていた。
「もうたくさんだったんです……。わけのわからないことで振り回されて、家の中もめちゃくちゃにされて」
彼が言葉を途切れさせながらも話し出す。
「俺はただ普通に暮らしたいだけなんだ。家では学校のことを話して、学校では友達となんの後ろめたさも感じず一緒にいられる。そんな生活がしたかった」
彼の言葉を聞いているうちに忌子の目から涙があふれてくる。彼の思いに触れたとき、その中に自分自身が見つかった。呪いにかかってから気がついたこと。今までの暮らしにどれだけ戻りたかったかを。
「呪いなんて俺にとってはどうでもいいんだ……」
あたりは静寂に包まれていた。しかし、それは先ほどまでの均整の取れた静けさではなく、すべてが壊された後に残る乱暴な静けさだった。