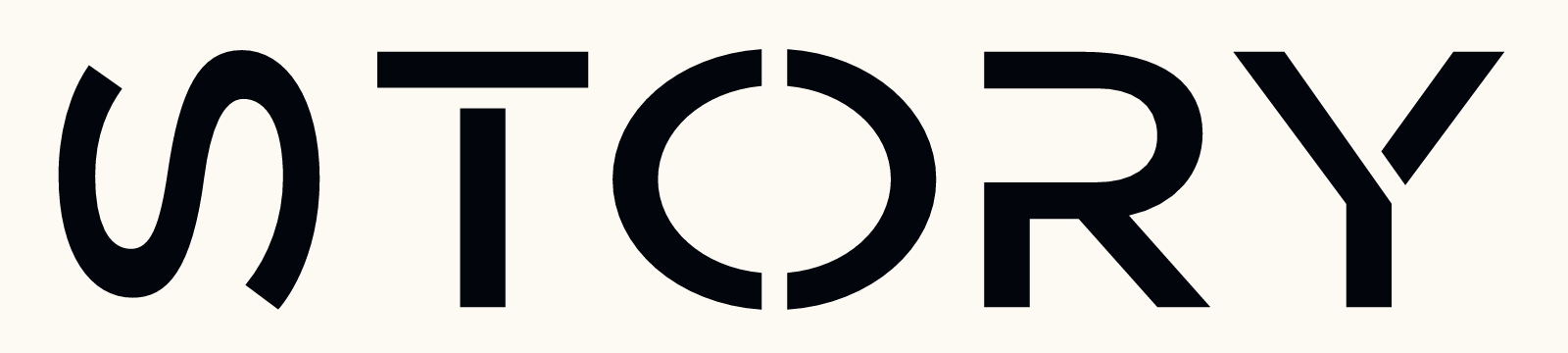第二十五話 真実
「そんな……」
忌子は清司から聞かされた歴史を聞いて驚愕していた。神楽を龍神に捧げる。舞いによって楽しませる。巫女としての役割を自分なりに理解して、これまでも神楽に臨んでいた。でも実際の歴史はもっと複雑だった。龍神に捧げられる生贄の身代わりとなり、その上で神楽によって龍神を満足させる。それがこの街に残されている歴史だった。
「じゃあ父様が」
そして忌子にとってもっと大事なことは、その歴史の中に伝えられている呪いについてだ。それは今まさに自分自身が置かれている状況と一致している。
「父様が私に呪いをかけたんですか?」
「呪いをかけたのは、あの女だ。私がそんな穢らわしいことするわけないだろう。それに龍神様の元へ嫁がせるために準備も必要だからな」
忌子が最も聞きたくない言葉を清司は吐く。彼はすべてを知っていた。娘を龍神へ捧げるために秀俊の母親を使って自分に呪いをかけさせた。
「想定外の事態も多かったが、ようやく準備が整った」
「なんで私が龍神様と!」
「今更、何を言っているんだ。君が産まれたときから決まっているじゃないか」
清司が当然のように語るが言っている意味がわからない。
「いつも言っているだろう。忌子。君の名前が持っている意味を」
その言葉は常日頃から言われていた。親友がキコと呼ぶとき。忌まわしいという字面から名前を名乗ると眉をひそめられたとき。そのときには必ず自分がこの名前をつけられた意味を説明していた。
「神に奉仕する娘」
忌子は斎女とも表し、大嘗会などの祭祀の際に奉仕をする清らかな娘という意味を持っている。清司はことあるごとに名前の由来を説明してくれた。だからこそ私は自分の名前を気にいっていた。まさに神社で巫女として産まれた自分にふさわしい名前であると。
しかし清司にとっては、そこにはもっと深い意味が込められていた。それは奉仕のために龍神様に生贄として捧げる。忌子という名前にそこまでの意味が込められていた。
「恵理が亡くなり君が穢れの中で産まれたとき、私は痛感したんだ。龍神様が満足されてない。だから私に罰が下ったのだと」
清司の真に迫った眼差しに忌子はただ見返すことしかできなかった。
「恵理の神楽は本当に素晴らしかった。誰が見たって龍神様は満足してくださると。でも君を身ごもってからは神楽を奉納することはできなくなった。それがお気に召さなかったんだ」
清司が天を見上げ、懇願するように話す。
「もうあんな思いはこりごりだ。どうすれば龍神様を満足させられる。彼女ほどの神楽を舞える巫女はいないのに。そのとき閃いたんだ。あれはまさに龍神様からの天啓と言っていい」
清司は一息でしゃべると顔をこちらへと向けた。
「龍神様は昔のように娘を所望されたんだ」
「それが私……」
「ああ。私と恵理の娘なら文句のつけようがない。君は龍神様のために産まれてきたんだ」
清司は今まで見たことのないほど高揚していた。それが彼の本当の姿なのだろうか。いつも落ち着き、神事に尽くす姿は見当たらない。
忌子はもう何を信じればいいのかわからなくなっていた。
「いや」
立ち上がれずにいざりながら後退する。
「なにを言っているんだ。君は放棄するというのかい。大切な役割を」
清司の目つきが鋭くなる。それは今まで自分に向けられたことのない表情だった。しかしなんども見たことがある表情だった。祭りで血を吐いて倒れた男性の話をしたとき。境内でごみが捨てられているのを見たとき。
それは彼が穢らわしいものを見るときの顔だった。
その表情が自分に向けられているとわかると忌子は抵抗する気力を失った。清司にそういう風に見られたくない。だからこそ呪いのこともひた隠しにして動いてきた。自分が最も避けたかったことなのに、彼は今自分のことを穢らわしい存在のように見ている。
元凶は彼のはずなのに嫌われたくない。その矛盾した気持ちに向き合えなかった。
「キコくん!」
そのとき後ろから聞き慣れた声が聞こえた。振り返ると仲間たち三人が内陣の入口に立っていた。