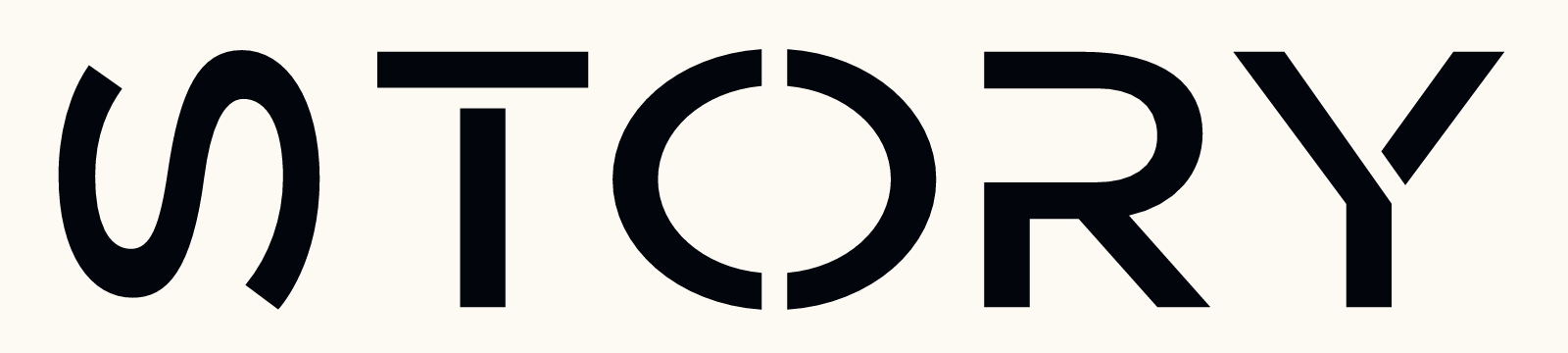第二十三話 神話
「まあ、あまり気を落とさない方がいい」
運転席から声をかける仲間の声を秀俊は後部座席でうつむきながら聞いていた。仲間は自分の母親が入院することを気づかっているのだろう。しかし秀俊の頭の中では忌子のショックを受けた顔が浮かんでいる。
呪具を見つけた時点で母親が呪いをかけていることは覚悟していた。
そして、なにも知らなかったとはいえ呪いに加担していた。もう遅いかもしれないが、そのことを三人に知られたくない。
母親が行う儀式には自分でも辟易していた。祈りの言葉、それは今思えば呪いの言葉だったのかもしれないが、それも適当にやっていた。だから呪いをかけるほどの効果はない。頭の中の忌子に向かって、ずっと言い訳を続けていた。
「呪いの正体を調べないとな」
仲間が助手席の楠本に声をかける。母親が言っていた呪いの正体。忌子と縁が深い人ほど、呪いの影響が強く出る。だからこそ呪いの影響が出ていない、この車内にいる三人は何か思惑があって忌子に近づいているにすぎないと言っていた。
楠本たちに思惑があるかは知る由もない。しかし自分に関しては、呪いの正体を母親の口から聞いたとき妙に納得してしまった。だからこそ否定できず彼女もショックを受けたのだろう。しかしこんな環境で縁を結べるはずもなかった。
「まずは部屋を片付けて入院に必要なものを準備するのが先だよ」
楠本が仲間をたしなめる。しばらくすると自宅近くの駐車場にたどり着いた。秀俊はドアを開けて外に出る。空が明るくなり始めているが今日は少し雲が多い。朝日に照らされた入道雲も見える。
自宅に戻ると改めて家の中の惨状が目に入る。食器棚から机の引き出し、テレビ台の中まであらゆる戸が開けられ、そして中に入っていたものが床の上に散乱していた。おそらく一階だけでなく、二階の部屋も、そしておそらく自分の部屋も同じような状態になっているのだろう。
秀俊は神棚に置かれた木箱に目をやった。それもこれもこの呪具を探すためだったのだろう。それだけ執着をしていたということになる。なぜそこまでして忌子に呪いをかけたかったのか。そもそも彼女と接点はない。自分の交友関係でも美友紀や晴雄の名前の方が彼女よりは話題に上がっていたはずだ。それなのになぜ母親は彼女に狙いを定めたのだろう。
「半紙をもらえるか?」
仲間が神棚に手を伸ばし呪具を机の上に置いた後、こちらを振り返って言う。リビングを見渡して自分のリュックを手に取り中から半紙を取り出し渡す。
穢れが行かないようにする神棚封じ。自分が行うはずだったのに結局なにもできなかった。夜中に自宅の明かりが煌々とついてたのを目にした時点で自分の心は折れていた。
だからのこのこと逃げ帰って忌子を傷つけ母親も入院する。自分がもっとうまくやっていれば。そもそも呪具だって持ち出さなければ。別に写真を撮って見せるだけで良い。わざわざ持ち出したから母親も感づいてしまった。自分の行動の浅はかさに嫌気が差す。
なにをしても無駄だと思っていたはずなのに。
仲間が神棚封じを行う姿を見ながら改めて余計なことはしないと心に誓った。
「これで呪いが解けてくれればいいが」
仲間が神棚を眺める横で楠本が部屋を片付け始める。
「いいですよ。自分でやります」
これ以上、迷惑をかけたくない気持ちで声をかける。
「さすがにひとりでやるのは無理があるよ。遠慮しないで」
楠本は意に介さず床に散らばった本を本棚に収めていく。仲間も一緒になってリビングを片付け始めた。申し訳なさに秀俊は立ち尽くしてしまう。
「さすがに寝室とかは片付けられたくないだろうから、そっちをお願いしてもいいかな」
楠本が気を使って声をかけてくれる。自分の家のことなのに、なぜか他人である楠本が率先して指示を出してくれた。自分自身の無能さに腹が立ってくる。
楠本の指示に従って二階に上がると、そこも予想通りリビングと同じような惨状だった。自分の部屋も母親の寝室の扉も開け放たれ、廊下にも物が散乱している。自分が夜中に家を抜け出して、戻ってくるまでそんなに時間はかかっていなかったはずだ。それなのにこの惨状であるということは、なにも頓着せずにただひたすら呪具を探し続けていたということだろう。
廊下に散らばっているものを片付けたら秀俊は自然と母親の寝室へと向かった。普段はほとんど入ることのない彼女の部屋に足が向かったのは、これまで起きた出来事の理由を知りたかったからかもしれない。
寝室にはベッドとクローゼット、それにベッド近くにナイトテーブルが置いてある。テーブルの上には鏡や化粧品などが並べられており、ただの物置として使われているようだ。その化粧品の一部は床に散乱している。クローゼットも開け放たれ衣服も散乱していた。とりあえずベッドの足元に散らばった衣服をまとめてから抱え上げベッドに放り投げる。そして部屋の奥にあるナイトテーブルへと向かった。飛び出した引き出しを閉めようとして目を疑う。引き出しの中には藁人形が入っていた。藁人形の顔の部分には顔写真が貼られており、それが釘で撃ち抜かれている。
その顔写真の人物は自分の父親だった。
藁人形が放つ禍々しさにたじろぐ。母親はことあるごとに父親に対する恨み言を聞かせてきた。しかし、これほど直接的なものだと意味合いが異なる。父親は先月亡くなった。それはつまり彼女が自分の夫を呪い殺したという証明だった。
その事実を改めて認識すると、心に鉛のようなものが押し込められたような重さを感じる。自分も決して父親に強い愛着を持っていたわけではない。ただ死を望むほどの関係でもなかった。しかし母親にとっては死を望むほどの相手になっていたのだろうか。そんな憎しみの中に産まれたという思いによって、自分自身の存在意義が揺らいでくる。
「秀俊くん! 来てくれないか!」
階下で仲間が呼ぶ声が聞こえて意識が現実に戻ってくる。急いで引き出しを閉め仲間の元へと戻っていく。
「どうしたんですか?」
リビングの片付けはまだ全然終わっていない。しかし仲間は本を手にしながらこちらを見ていた。
「ちょっとこれを見てくれないか」
リビングの机の上には以前、仲間に渡した呪いや龍奉神社についてまとめた秀俊の資料が広げられていた。その横に仲間が手にしていた本を置く。タイトルから見て、この地域の歴史についてまとめてある本のようだった。
「これがどうしたんですか?」
「この本はそこの本棚にあった。これを読んだことはあるか?」
仲間に問われて首を振る。そもそもそんな本があったことすら知らなかった。
「キコくんがいる龍奉神社の歴史を知っているか?」
仲間が質問を続ける。
「えっと。龍神様を祀っているんですよね。近くの川がよく氾濫するのを鎮めるために」
机の上の資料を見て龍奉神社の歴史をまとめたときにサイトに書いてあったのを思い出す。
「それをどうやって鎮めているかは?」
「神楽ですよね」
神様を楽しませるから神楽。字面を見て妙に納得したのを覚えている。
「そうだ。それは君がまとめてくれた資料に書いてあったことだ。ただこっちを見てほしい。ここにはより詳しい神社の歴史につながる内容が書いてある」
仲間が本を開き指さしたページに秀俊は目を通した。
「……毎年のように龍神川の氾濫が起こり生活もままならなくなった村人は龍神を鎮めるために生贄を捧げることになった。村の中央で白羽の矢を飛ばし、矢が刺さった家の娘が選ばれる。生贄は龍神へと嫁ぐ名誉なこととして捧げられていた。生贄の儀式が始まってからは川が氾濫することは無くなった。しかしある年、娘の家族が生贄に捧げることに抵抗した結果、また川が氾濫し村に被害が出た。そのためなんとしてでも生贄を途絶えさせない方法が編み出された。それが呪いである。生贄の身内が抵抗しないように、生贄と縁があり、その縁の深さに応じて憎しみが生まれる呪いが生み出された。そうすることで生贄はまた滞りなく捧げられるようになり、しばらく生贄により村は安定を保っていた。しかしある年、村に立ち寄ったひとりの女性が、村の慣習に心を痛め生贄に名乗りを上げる。今年は村の娘を出さなくて済むと安心した村人たちは心置きなく女性を龍神の元へと捧げた。龍神が女性の元へと訪れたとき、彼女は見事な舞いを持ってして龍神の心を鎮め、それからは舞いを奉納し龍神を満足させることで川は氾濫しなくなった。それが現在の龍奉神社へと残る神楽の歴史となっている」
「これって」
内容が内容だけに戸惑いを隠せない。
「ああ。この呪いの部分。彼女の身に起こっていることと見事に一致している」
縁が深いほど憎しみが生まれる。それは忌子が陥っている状況、そして母親が言っていた情報と合致していた。かつて生贄を捧げるときに家族が抵抗したことから呪いが生まれたとこの本は記している。生贄に捧げるのを止めようとするほど縁の深い人物が呪いの影響を受けたらと想像すると背筋に寒気を覚える。
「これが呪いを解く手がかりになるんじゃ」
「だが詳細がわからないんだ。この呪いにかかった人たちがどうなったのかということは書かれていない。もし生贄が捧げられた後に呪いが解けるんだとしたら、それは彼女にとってはなんの救いにもならない」
生贄に捧げられると呪いが解ける。そのときの家族の姿が想像された。最も守りたかった人を生贄に捧げ、すべてが終わった後に正気に戻った姿を思うと伝承の話なのに胸が苦しくなる。
「でもこんな時代に生贄なんて」
「ああ時代錯誤もいいとこだ。でも実際に呪いは起きている」
話しながら仲間は思い出したかのようにスマホを取り出して電話をかけ始める。
「だめだ! 彼女が電話に出ない」
しばらくスマホを耳に当てていた仲間の声には焦りが見えた。