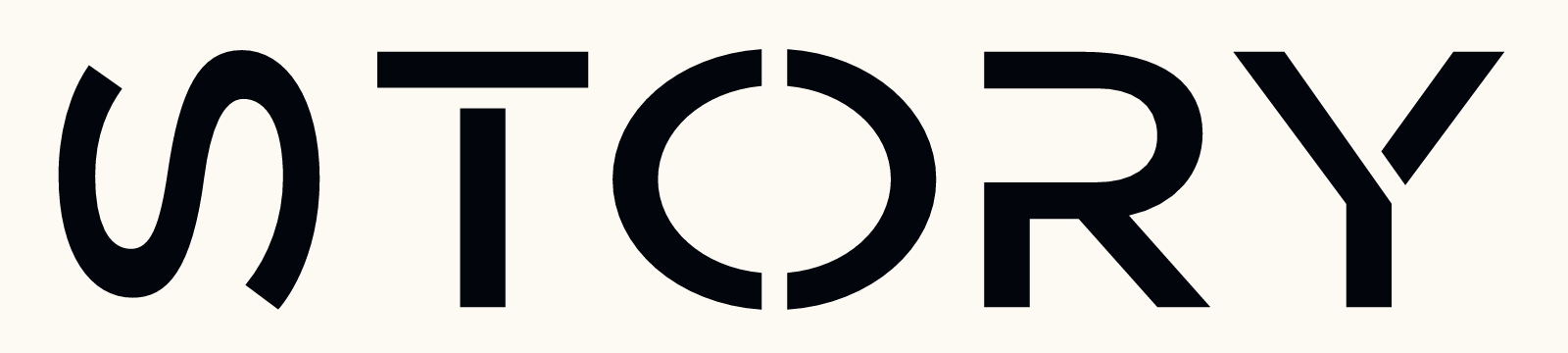第二十一話 八乙女家の歴史
風呂場で体を清めた後、巫女装束に着替えて龍奉神社へと向かう。外は晴れ間は覗いているが雲の多い空だった。西には巨大な入道雲が見えていて、夏もどんどん本格的になってきている様相だった。
神社へとたどり着くと鳥居の前で百人一首に出てくるような出で立ちの男性が立っている。それは黒の冠をかぶり橙色の袍服を来た清司だった。その姿を見て驚く。最高の儀礼服と呼ばれる袍服は忌子も数えるほどしか見たことがなかったからだ。
「忌子、待っていたよ」
聞きたいことが山ほどあるはずだった。しかし厳かな雰囲気をまとっている清司に対して黙ってうなずくことしかできなかった。
「こっちにおいで」
清司の言葉に促されて忌子は神社の中へと入っていく。本殿への道すがら清司は一言も言葉を発さなかった。
本殿へと入り清司がいつも祈祷している内陣の中に案内されると忌子は固まってしまった。四十畳ほどの広さの板の間には、机状の台である案が並べられている。その上には白磁器の瓶子に入ったお神酒、鯛や果物、餅などが鏡餅を供えるときにも使われる三方に乗せられ神饌として供えられていた。
周囲には榊に五色布を垂らした真榊や朱雀などの霊獣が描かれた四神旗も並べられている。中央には白い布がかけられた祭壇があり、そこには木で彫られた雲形台に円鏡が乗せられた神鏡と御幣が置かれていた。その奥の木製の扉は内々陣へと続いており、そこには御神体が祀られている。
忌子はここに並べられていたものに見覚えがある。それは神前式で婚姻をする際に使用するものだった。もちろん一般の人は本殿に入ることはできないため本来は拝殿で用意するものだった。
「父様。これは……」
ようやく口を開いた忌子だったが、なにを言えばいいかわからず結局黙ってしまった。
「呪いは龍神様が解いてくださる」
「でも」
清司の言葉と目の前にある状況がつながらず理解できなかった。龍神様。それはこの地を治める氏神様だ。神が呪いを解く。巫女である忌子にとってもこの言葉の意味は想像できる。神道と祓いの儀式は密接に関わっているからだ。しかし問題は婚礼の儀を執り行うための準備だ。
隣から鼻をすする音が聞こえて忌子はまた驚く。清司は黙ったまま両目から涙をあふれさせていたからだ。
「忌子。立派になったなぁ」
震える声で話す清司はうれしそうに忌子の肩に手を置いた。
「君が産まれたときは本当に大変だったんだ。恵理は血の海の中で亡くなってしまうし」
清司の話には聞き覚えがあった。自分が産まれたときのこと。それは清司にとってはつらい思い出だからか直接聞くことはなかった。しかし氏子である地域の人たちから断片的に聞くことで、ある程度のことを知っている。
忌子の母である恵理は妊娠中に突然の腹痛を訴え大量に出血した。すぐに救急車で病院に運ばれたが助からず、そんな中かろうじて自分だけは命を得た。
「それもこれも私のせいだ。私がちゃんと龍神様に対して奉仕ができていなかった。そのせいで忌子、君を穢れの中で生まれさせてしまった」
その顔は今まで忌子が見たことのない、つらそうな表情をしていた。