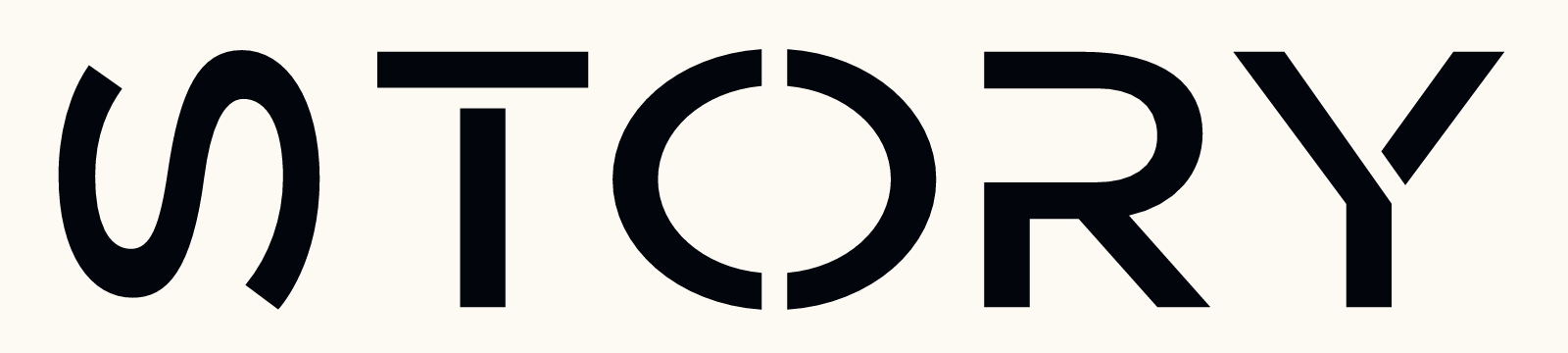第二十話 儀式の始まり
仲間が運転する車で離れに戻った忌子たちは居間で楠本からの連絡を待っていた。仲間は椅子に腰掛け黙ったまま目を閉じている。最初は考え事をしていると思っていたが、どうやら呼吸の感じから寝息を立てているようだった。
この状況でも寝られる仲間の精神力に驚きつつも忌子はひたすら待ち続けた。しかし時計の音と仲間の寝息だけが聞こえる空間では、忌子の頭の中には嫌でも呪いのことが頭に浮かぶ。
自分と縁が深い人ほど呪いの影響を受けて豹変する。
それが愛美の言っていた呪いの正体だった。それなら納得がいく部分は多い。自分にとっては一番仲の良かった美友紀の仕打ちが一番つらかった。神社の人がしてきた仕打ちもつらいものではあったが美友紀と比べると軽い。それが縁の深さによる違いと言われたら納得してしまう。
だからこそ寝息を立てている仲間の姿を見て不安が募る。これだけいろいろと自分のために行動してくれている彼女と自分の間に縁は結ばれていないのだろうか。彼女も楠本もまだ会って数日だ。縁を結べていないという可能性はあるかもしれない。
でも自分はふたりを信頼していた。自分の一方的な思いだけで、ふたりは縁を結んでいる気持ちなど微塵もなかったのだろうか。だからこそ呪いの影響を受けていなかったのだろうか。差し伸べた手を、目の前で振り払われたような絶望感が忌子の心に広がっていく。
一方的な思い。その言葉をきっかけに秀俊の姿が頭の中に浮かぶ。彼も態度が変わらないひとりだった。しかも仲間たちと違って中学生の頃からの付き合いにもかかわらず。
それに彼に対する思いは特別だ。それは美友紀とはまた違う憧れのような存在。だから彼が手伝いを申し出てくれたとき、励ましの言葉をかけてくれたとき自分の心は救われていた。
もし縁を結べていないとしたら、それは今までの思い出がすべて否定されたようなものだった。手伝いを申し出たのも自分を心配したからではない。愛美が秀俊にそう呼びかけたとき彼は反論してくれなかった。
忌子は周りを見回す。目の前には仲間がいる。それなのに忌子は安心できず、ひとりぼっちであると感じていた。
カーテンの向こうが明るくなり始めた頃、机の上にある仲間のスマホに着信が入る。目を覚まして仲間が着信に出た。横で聞いていると彼女の声色は暗く悪い想像をする。
「どうでした?」
通話を終えた仲間に聞く。
「まだ目が覚めないそうだ。命に別条はないそうだが検査でも原因がわからないらしい。そのまま入院することになったみたいだ」
その言葉を聞いて忌子はどう思えばいいのかわからなかった。
「ふたりはこっちに来るんですか?」
「とりあえず入院の手続きをしたら、彼の家にいったん戻るそうだ。だから私は彼らを迎えに行こうと思う」
その言葉の後に彼女がこちらを見つめてくる。それは言外に君はどうする? という問いが込められていた。
「すぐに行ってあげてください。今は彼の方が大変だろうから。私はちょっと休みたいので残ります」
一息で早口に言う。
「たしかにとんでもない一日だったからな。落ち着いたらまた戻ってくるよ」
仲間は立ち上がり家を出ていく。扉が閉まる音がしてひとり残った忌子は自室に戻り布団を敷く。体を横たえるが休まる気がしなかった。ただ時計の音だけが忌子の耳に響いている。
呪いについてぐるぐると頭の中で考えていると着信音が鳴り響き思考が中断された。仲間が出ていってからそれほど時間はたっていないと思ったが時計を見ると三十分は経過していた。無意識に導かれるように受話器を手に取る。
「忌子。大丈夫かい」
受話器の向こうから清司の声が聞こえてきた。
「父様!」
「これまで大変だったろう。でも呪いを解く用意ができたんだ。神社に来てくれるかい?」
清司の言葉に耳を疑った。なぜ呪いのことについて知っているのだろう。それに呪いを解けると言っていた。
「どうして?」
「神職の私が気がつかないわけないだろう? 詳しいことはこっちに来たら話す。いつもの装束で来るんだよ」
それだけ言うと清司は通話を切ってしまった。通話が切れたことを示す無機質な機械音が受話器から聞こえてくる。清司の言っていた意味を考えようとするがもはや頭は回らなかった。受話器を置いて言われるがままに巫女装束を手にする。呪いによってあの三人とは縁を結べていないことがわかった。今の自分にもう頼れるのは家族しかいない。そのまま忌子は風呂場へと向かっていった。