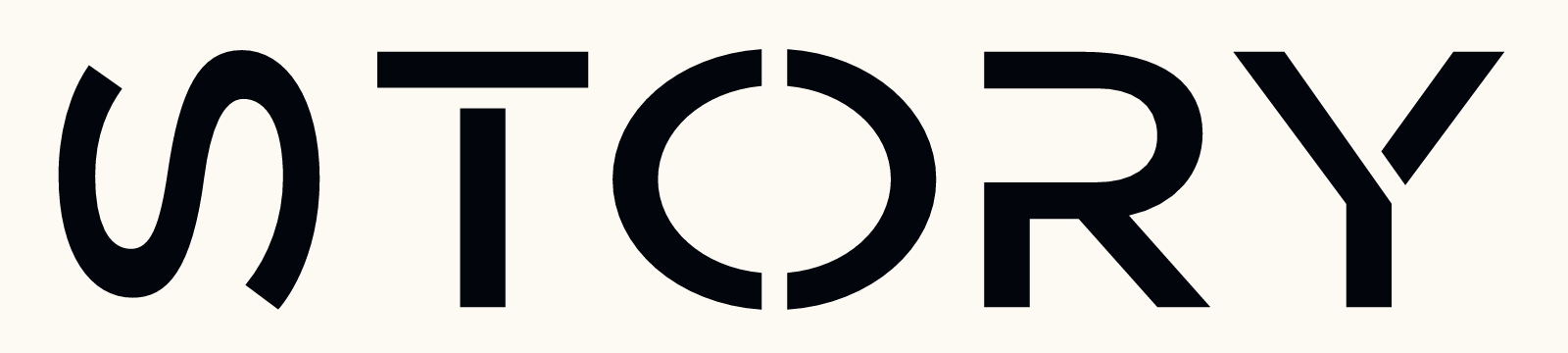第十七話 田島家
楠本のレンタカーに乗り込んで四人は秀俊の家へと向かう。夜中になると日中よりは暑さは和らいでいる。しかし日増しに蒸し暑さは強くなっていて夏が本格的に近づいているのを感じた。車内で移動中は忌子も含めてみなずっと無言だった。
家から少し離れた場所の駐車場に止めると秀俊が車から降りる。一度、こちらを振り返り不安そうな表情を見せるが、前を向き自宅へと向かっていった。
これで呪いが解けるかもしれない。そう思うと、まだ不安は残るにしても少し希望を感じる。しかし数分もしたら秀俊が慌てた様子で戻ってきた。
「どうしたの?」
運転席の窓を開けて楠本が問いかける。
「家中の明かりがついてて、どうやら母さんが起きてるみたいで」
楠本は後部座席に振り向き、仲間とうなずきあう。なにもわからない忌子にとってはまた不安が広がっていく。
「どうしたんですか?」
「お母さんが起きてるってことは、彼がいないことも、もしかしたら呪具が無くなっているってことも気がついた可能性がある」
楠本が忌子の質問に答える。
「母親が寝ている間にこっそりできれば良かったが、さすがに今の状態で彼ひとりで向かわせるのは危ないな」
仲間が楠本を引き継ぐように説明すると、そのまま後部座席のドアを開けて外に出る。忌子も慌てて扉を開けて外に出る。彼の母親が起きているということが、どういうことを意味しているか遅れて理解した。今までの彼に対する母親の仕打ちを思い出すと、どんな目に合わされるかわからない。
もしかしたら自分はここで待っている方が安全かもしれない。しかし忌子にとってひとりで残るという選択肢はすでになかった。
車から出てきた忌子に対して仲間は無言でうなずいた。楠本は心配そうにこちらを眺めていたが、何も言わずに秀俊の方へと向き直る。
「家に案内してくれるかな」
秀俊がうなずき歩き始める。
真夜中に外を出歩く経験は忌子にとって初めてのことだった。これから呪具があった家に行くにもかかわらず、つい周囲を見渡してしまう。
呪いにかかってからは初めての連続で、ほとんどがつらいものだった。しかし、こういう非日常感で心が浮つく瞬間が、つらい経験の隙間に滑りこんでくることがある。それは今までの生活では気がつくことすらできていない思いだった。
秀俊の家が見えてくると、彼の言った通り部屋中の電気がついているようだった。二階建ての家の窓すべてから明かりが漏れている。この時間だと住宅街の家々は電気がついていないか、ついていたとしても一部だけのことがほとんどだった。そのため彼の家だけ異様な明るさを放っていた。
しかし家の前まで近づくと、異様なのは明るさだけではなかった。何か物が倒れるような音や、ぶつかる音。決して大きい音ではない。家の前まで来ないと気がつかない音。しかし、外に漏れ出てくるほどの音は、この閑静な住宅街には似つかわしくなかった。
秀俊が振り返ると、顔が青ざめている。どうやら彼もさっきは、この音には気がついていないようだった。
「鍵を開けてくれ」
仲間の声かけに、秀俊が扉の鍵を開ける。扉が開くと騒音がより鮮明に聞こえてきた。秀俊の後に続くように家の中へと入っていく。音はリビングから聞こえているようだ。リビングの先には秀俊の母親がいるはずだ。日中に会ったとき特段変な印象はなかったが、呪いをかけている張本人かもしれない。そしてこんな夜中に家中の電気をつけて騒音を出し続けている。そんな異常さに自然と声や足音を忍ばせるようになっていた。
「母さん?」
秀俊が恐る恐るリビングにつながる扉を開けると、ドアノブを握ったまま秀俊は固まってしまった。同時に騒音が止まる。リビングの中を確認した仲間たちもその場で固まってしまった。三人の隙間を縫うように視線をリビングの中へと向けると忌子は息をのんだ。
リビングは荒れ放題になっている。床一面に物が散乱していて、本棚に入れてあったであろう本もすべて床の上にありからっぽになっていた。台所の引き出しもすべて開けられ食器も外に出されている。放り投げたりしたのだろうか。一部は割れて破片が散らばっている。
私服を着てリビングの真ん中にたたずむ愛美が、こちらを振り向いたとき忌子は思わず三人の影に隠れた。目は血走っていて肩で呼吸するさまは日中の落ち着いた様子とは別人だった。