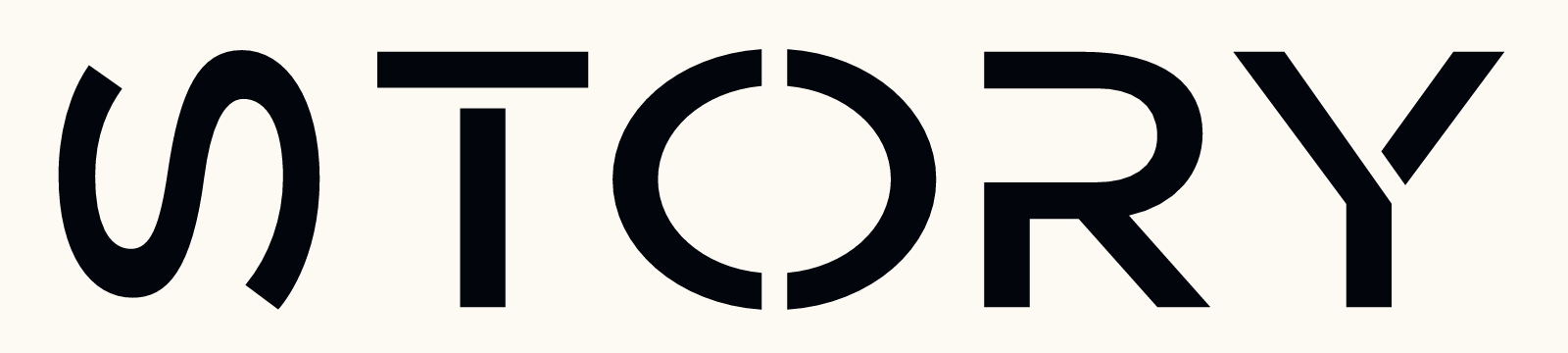第十三話 再警告
朝、目が覚め忌子は体を起こした。時計を見ると時刻は普段起きる朝五時を示している。窓から陽の光は差しておらず、カーテンを開けると空は曇り空だった。起きて真っ先に秀俊のことを思う。結局彼が訪ねてくることはなかった。普段、学校ですぐ会えるため彼の連絡先を控えていない。
仲間と連絡先を交換した時ついでに彼の電話番号を聞いておけば電話をかけられたのにと、ふがいなく感じる。次会ったときは連絡先を交換しておこう。そんなことを考えながらまた脱衣所へと向かった。そして廊下に出たタイミングで忌子は足を止める。
郵便受けに白い封筒が入っているのが目に入ったからだ。おそるおそる近づいて郵便受けから封筒を取り出す。また宛先も何も書かれていない封筒だった。心臓の鼓動が速くなるのを感じる。昨日と同じように居間へと移動して封を開けると、一枚の折りたたまれた紙が入っていた。中を開いた瞬間に忌子は昨日と同じ様に紙を放り出した。
「田島秀俊に近づくな」
書かれている文面は昨日と同じ、そして真っ赤な文字で書かれているのも同じだ。しかしひとつだけ異なることがある。それは小さな文字で紙を埋め尽くすように同じ文言が繰り返して書かれていることだった。
手紙がある居間にいることが耐えきれなくなり自室へと駆け込む。受話器を手にとって仲間の電話番号へと連絡する。
「どうした! 何かあったのか」
数コールで出るやいなや仲間が声をかける。
「あの。また手紙が入っていて」
「そうか、わかった。すぐに向かう。君は家でじっとしていてくれ。誰か来ても絶対に出るんじゃないぞ」
電話が切れたことで、またひとりの静寂な時間が戻ってくる。忌子は布団にくるまり自分の体を抱える。せっかく味方ができたのに、それなのにたった紙切れ一枚でこれだけ自分の心がかき乱されてしまうとは思わなかった。
仲間たちを待つ三十分程度の時間が今の忌子にとっては永遠にも感じられた。玄関のインターホンが鳴る。おそるおそる居間へと向かい、手紙が視界に入らないようにしつつインターホンを見た。画面には仲間たちの顔が映っていてほっとする。しかしふたりは目線を落として周りを気にしている様子だった。
「仲間さん」
「無事で良かった。ただそれよりも……。ちょっとこっちへ来てくれないか」
インターホンで応答すると仲間は忌子に外に来るように呼びかけた。不安に思いながら玄関へと向かう。鍵を開けて外に出ると、異臭が鼻につき思わず顔をしかめる。
臭いの原因は玄関の周りにまかれていた生ごみだった。夏の暑さが影響して臭いが立ち上り強い悪臭を放っていた。
たまらず玄関から離れる。扉が閉まると臭いは漂ってこなくなった。しかし鼻腔に残る臭いのせいで家の中まで生ごみが侵食してきた感覚に陥る。
「大丈夫か」
仲間たちが扉を開けて入ってくる。
「なんですか、あれは?」
声が震えながらも仲間に問いかける。
「わからない。私たちが到着したときにはあの状態だった」
そう言われて愕然とする。昨日の時点では何もなかった。つまり夜の間に誰かがごみをまいたことになる。
「さすがにあのままにしておくのはまずいよ。掃除する道具とかあるかな?」
楠本が横から口を挟む。本来なら自分が片付けないといけない。しかし忌子にとって外に出て、あの悪臭が漂う空間でごみを片付けることはできそうにもなかった。
「庭の方に回ってくれれば箒やちりとりがあります」
「わかった」
楠本はうなずくと外へと出ていった。
「それで届いていた手紙っていうのは」
仲間を居間に案内して手紙を拾い上げて渡す。内容を確認した仲間は顔をしかめる。
「何か怨念めいたものを感じるな。あの後、彼から連絡はあったのか?」
忌子は黙って首を横に振る。
「そうなると彼の身も心配だ。彼の家は知ってるか?」
「知ってますけど……」
「じゃあ住所を教えてくれるかい」
「でも!」
自然と目線は手紙へと向かっていく。これだけ秀俊に会わないように警告を繰り返されているのに、それなのにわざわざ会いになんていったら。なにが起きるかわかったものじゃない。
「大丈夫。場所さえ教えてくれれば私が会ってくる。君はここで待っててくれればいい」
そう言われて先ほどの孤独な心細さが思い起こされる。あのままひとりで待ち続ける。それは自分にとって耐えられない選択肢だった。
「私も一緒に行きます」
声は相変わらず震え、すがるような眼差しで仲間へと訴える。
「そうか。直接案内してくれるなら助かるよ」
仲間は忌子の顔つきを見て、普段より柔らかい声色で受け入れた。