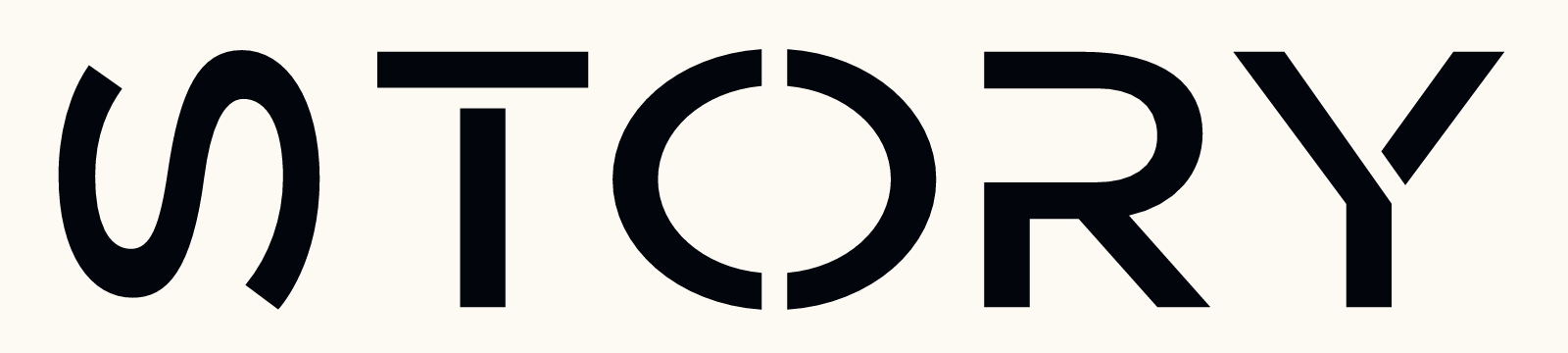第十話 呪いの話
忌子たちは龍神川を越えて離れへと向かっていた。日差しが照りつける中、足早に向かう。離れへたどり着いたが忌子はそのまま仲間を家へと招き入れるのは抵抗があった。自分から誘ったにもかかわらず、穢れを家に持ち込んでしまうという思いが浮かんでくる。
「ちょっと準備するので待っててください」
三人を玄関前で待ってもらうように伝えて急いで準備する。新聞紙を入口から風呂場へと続くように敷き詰め、ごみ袋を取り出して脱衣所に置いておく。
「おまたせしました。汚れた服は脱衣所に袋を置いておいたので入れてください」
せめて汚れが家につかないように準備する。それが忌子にとってぎりぎり許容できる対応だった。
「ありがとう。さすがの私もごみまみれでいるのはつらいからな」
そう言いながら仲間は脱衣所へと入っていく。
「あの楠本さんと田島くんもどうぞ」
ふたりを一階の居間へと案内する。四人がけの食卓に置いてある椅子に座るように促す。
「ご家族の人にメッセージ送っておいたら? 家に帰ってきて知らない人がいたらさすがに驚いちゃうんじゃない?」
楠本が提案する。
「ここは私だけで暮らしているので問題ないです。それにスマホは持ってないので」
「お父さんやお母さんはここに住んでいないの?」
彼は状況が理解できないという表情をする。たしかに他の人からしたら自分のいる環境はわけがわからないだろう。
「母はいないです。私が産まれたときに亡くなったので。父様は神社の方にある自宅に住んでいます」
「えっ。じゃあ別々に住んでいるの?」
「はい。神社は神聖な場所なので。学校を卒業して本格的に神社に奉仕できるようになるまでは穢れを持ち込まないように外で暮らしているんです」
忌子の話を聞いて、楠本は黙り込んでしまった。しばらくすると風呂場からシャワーの音が聞こえてくる。
「そうだ。着替えを用意しないと」
二階の自室へと上がり、タンスから着替えに使えそうな服を探す。しかし仲間の背は高かった。もしかしたら百七十近くはあったかもしれない。百五十台の自分の服だと到底入りそうにない。
どうしようかと考えていると巫女装束が目に入る。まだこちらの方が着られるはずだ。それに生地が厚いからもし下着まで汚れていたとしても問題ない。脱衣所に入り仲間に声をかける。
「すみません。サイズの合いそうな着替えが巫女装束しかないので、とりあえずそれを着てもらっていいですか。着方は私が教えるので」
「キコくん。ありがとう。まあとりあえず着られればなんでもいいよ」
突然、あだ名で呼ばれてびっくりする。彼女なりの親愛の表し方なのだろうか。
風呂場から出てきた仲間に巫女装束を着させて、リビングへと戻る。いきなり巫女姿の人物がひとり増えた影響か楠本も秀俊も目を丸くしていた。
「いやはや。仲間さんも巫女さんの姿に見ればそれだけでおしとやかに見えるんだね」
楠本が苦笑しながら話しかける。
「馬鹿なこと言ってないで、さっさと話を始めるぞ」
おもむろに仲間は忌子の方へと向き合う。
「君は呪いにかかっている」
巫女姿による風格のせいか先ほどよりも説得力がある。
「その呪いってなんなんです? そんなものが実際にあるんですか?」
「信じてもらうのは難しいかもしれないが、私には見えるんだ。さっきの巫女さんだって別に仲が悪いわけではないんだろう。おそらくあれも呪いの影響だ」
そう言われると、何も言い返せなくなる。彼女に何か気に障るようなことをしてしまった覚えはない。呪いのせいだと言われた方が、まだ納得できるかもしれない。
「私は生まれつき呪いが目に見えるんだ。普段は民俗学の研究をしている傍ら、呪いがかかった人の手助けをしているんだ」
忌子は先ほどのかばってくれた姿を思い出した。あのようなことを普段からしているのだろうか。
「君は祭りの日に神楽を舞っていたな。あのときは呪いの気配なんてなかった。だから呪いにかかったのはその後の可能性が高い。ここ数日で君の周りでおかしなことが起こったはずだ」
クラスで起こったことを思い出してぎくりとする。しかもそのタイミングすら言い当てている。
「どうやら図星のようだな。どうだ話してくれないか」
黙っている様子を見て仲間はひとり納得した様子だ。学校で起こったことを話してみてもいいか思い悩む。
巫女という姿になったおかげで親近感が湧いたのかもしれない。自分をかばってくれたり、楠本とも知り合いだったことが影響したのかもしれない。はたまたさすがに自分ひとりでこの問題を抱え続けるのが限界だったのかもしれない。
忌子は意を決してここ数日で起こったことを話すことにした。
「美友紀がそんなことを」
秀俊が信じられないといった様子でこちらを見ている。
「そっか。それで昨日診療所に来たんだね」
楠本もうなずいている。彼は今までの出来事につながりを得たのか納得している様子だった。忌子自身も話したことで、そしてそれを聞いてもらえただけで、心が少し軽くなる。
「あのとき手助けができなかったから。だから美友紀に嫌われたのかもしれないと思って」
口に出すと、そのことが現実になった気がして気分が落ち込む。
「誰だって血を吐いた人が倒れたらなかなか近づけないよ」
楠本が慰めてくれる。
「それに美友紀はそんなことを気にするような性格じゃないよ」
秀俊も助け船を出してくれる。旧知の仲である秀俊に言ってもらえたことで、美友紀を信じたいと思っていた気持ちに少し自信が持てるようになる。
「もし仮にこれまでのことが呪いのせいだったとして、誰がなんのためにそんなことを」
すがるような気持ちで仲間に話しかける
「それはわからない。あくまで私がわかるのは呪いをかけられていることだけだ。どんな呪いを誰がかけたまではわからないんだ」
仲間が申し訳なさそうに頭を下げる。
「じゃあどうすれば」
すがった先でも、まだ救いは得られず忌子は落胆する。
「それには原因を見つけないといけない。呪いをかけるには儀式が必要だ。その現場かもしくは儀式に必要な呪具を見つける必要がある」
「それは見えないんですか」
「あいにく千里眼があるわけじゃない。呪具が目の前にあれば判断できるが。そのためにも君に協力させてくれ」
改めてこちらに向き直り彼女は頭を下げる。完全に信じたかというと、まだ疑いはある。でも彼女が冗談で言っているようにも見えない。
「どうすればいいんですか」
その気持ちを表すためにただうなずくのではなく質問を続ける。
「キコくん。君は誰かに呪いをかけられるようなことをしたり恨みを買った覚えはないのかい?」
「そんなことはない! ……と思いたいです」
自覚としてはまったく心当たりはない。しかし実際に呪いをかけられているのであれば、誰かから知らない間に恨みを買っていた可能性はあるのかもしれない。
「さすがにそれはないと思います。クラスで陰口をたたかれているのを聞いたことないから。僕自身も付き合いはそれなりにありますけど、人の恨みを買うような人じゃないと思います」
秀俊が横から口添えしてくれる。その言葉を聞けただけでも心が救われる思いだ。
「そうか。それだと手がかりとしてはないといったところか。まあ逆恨みみたいなこともよくある」
逆恨みだったとしたら見当もつかない。周りにいる誰もが犯人かもしれないと思うと外に出ることが怖くなる。
「地道に調べていくしかないだろう。とりあえず神社が怪しいかもしれないな。呪いとの親和性が高い場所ともいえる。キコくん。学校はしばらく休む予定なのかい?」
「いえ。今日で期末試験が終わってしまったので試験休みに入りました。来週の終業式の日までは休みです」
「だったら好都合だな。早速、いろいろと調べたいところだが、さすがにこの格好で、うろつくわけにはいかない。とりあえず今日は退散して、あしたから本格的に調べようじゃないか」
気がついたら一緒に調査する約束を取り付けられてしまう。しかし、すでに忌子の中では戸惑う感情はだいぶ小さくなってきた。
「じゃあ僕は車を取ってくるよ。ホテルに戻れば着替えもあるだろ?」
そう言うと楠本は立ち上がり離れを出ていく。
「田島くんもありがとう。いろいろと」
かばんを持ってきてもらった中で、変なことに巻き込んでしまった。しかし彼がいなかったら仲間たちの話を落ち着いて聞けていたとは思えない。知り合いがひとりいるだけでもこんなに心強いとは思わなかった。
「あのさ……。もし良かったら僕も協力させてくれないかな?」
「協力って?」
「だから八乙女さんの呪いについて。クラスメイトのこととかなら僕の方が仲間さんたちよりいろいろと調べやすいだろ」
「それはそうだけど……」
こんなわけのわからないことに巻き込んでしまって良いのだろうか?
「いいじゃないか! 神社に呪いの原因があるとは限らないんだし」
仲間がうれしそうに賛成する。
「でも……」
「もし呪いの影響でクラスのみんながおかしくなったままだと僕自身も困るから。だったらこれは僕の問題でもあるわけじゃん」
その発言を聞いて、巻き込んでしまうという申し訳なさが減る。
「ありがとう」
忌子はほほ笑みながらうなずいた。ここまで言ってもらえて申し出を断る理由はない。これからどうなってしまうのかという不安はあるが、昨日までのひとりっきりの状況からはだいぶ前進したと思えた。