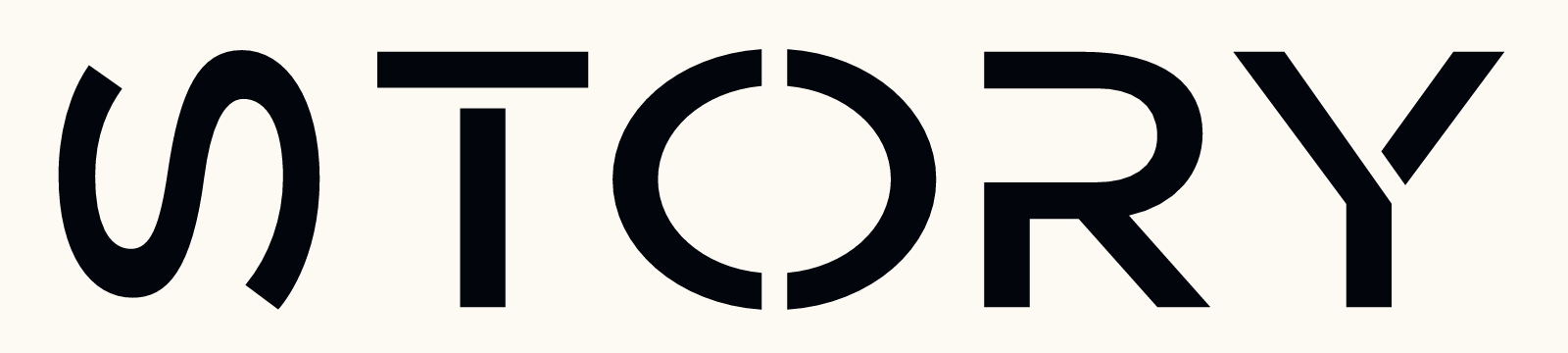第七話 体調不良
「なんで都内からわざわざこんなところの夜間診療所に?」
楠本優一が診療所のマニュアルに目を通していると、看護師が後ろから声をかけてきた。
「日中は観光してSNSに投稿、夜間は小児科医として働く。そんなバイトが今はあるんですよ」
そうなんですかと看護師はなんとなくわかったような口調で返事をする。具体的にはワーケーションという形で勤務している。医師不足はどこでも叫ばれているが、特に夜間の診療所は人手が足りない。医師会や大きな病院から派遣されることもあるが、それでも人手が足りないときは求人サイト経由で依頼が入る。
なるべく人に来てもらうように市からの依頼で日中は観光してもらい、夜間は診療所で働くというワーケーションの形で求人が作られるようになった。
市としては夜間の診療所の人手は確保できるし、観光地の宣伝にもなる。医師としても交通費や宿泊代は負担してもらって、なおかつバイト代も得られることから一石二鳥のバイトとして人気があった。
「どこに行かれたんですか」
「土日はちょうどお祭りがあったので龍奉神社に行きました。でもそこで人が倒れて心肺蘇生しなきゃいけなくて大変でしたよ」
それは大変でしたねぇと笑いながら看護師は隣の部屋へと戻っていく。
ひとりになって部屋を見回す。患者が座る椅子と、すみに付き添いの人が座る丸椅子、それに診察用のベッドが一台あるだけの簡素な部屋。机の上には喉を見るための舌圧子やライトが置かれている。
この地域の夜間の混雑具合はわからないが、一次診療としての夜間診療所は軽症の患者がやってくる。保育園から戻ってきたら熱が出た。そんな子どもが受診することはよくある。夏の時期なら手足口病の子が多いだろうか。最近は夏にRSウイルスが流行することもあるが、今年は今のところ流行はきていない。
そんなに忙しくなることはないかな。そう思いながらマニュアルに目を通す。
「先生、十七歳の女の子は診れますか?」
マニュアルも読み終わりパソコンで仕事をしていると先ほどの看護師から声がかかる。
「十七歳ですか。基本は内科の先生ですけど、もしかして忙しいですか?」
ここの夜間診療所は二診体制で隣の部屋では内科の先生が診察している。一般的に小児科は中学生まで、つまり十五歳までが診察の対象になることが多い。ただ長期に診ている人であれば大人になっても診察することはあるし、軽症の患者であれば十五歳を超えていても診察することは小児科医でもままある。
「いえ。患者は全然いないんです。それに来た子のかかりつけがちょうど診察してくれる先生のところだったから、むしろそちらで見てもらった方がいいんですけど」
看護師の釈然としない様子に訝しむ。たしかに普段クリニックで診られている子ならば、バイトで来ている自分が診るよりよっぽどいい。
「でもなぜか私は診ないの一点張りで。いつもは優しい先生なんですけど」
看護師は困り果てた様子で恐縮しながら頼んでくる。診療を断るというのはあまりない。単に虫の居所が悪いのかなと解釈する。
「いいですよ。ちなみに主訴はなんですか?」
「ありがとうございます。えーっと、腹痛ですね。予診票には今日から痛くなったと書いてます」
腹痛か。婦人科系が疑わしかったら紹介しないとだな。明らかに下痢や嘔吐があって胃腸炎が疑わしいなら、そこまで困らないが、単に腹痛だけだといろんな疾患の可能性が増えるから診察が難しくなる。検査もほとんどできない夜間診療所だと疑わしきは紹介の方がいい。まあなんでもかんでも紹介されると病院の医師が困るため、ある意味腕の見せどころでもあるが。
予診票を受け取り名前を確認する。八乙女忌子。読みはやおとめいむこ。字面を見て少し警戒する。忌むという言葉に良いイメージはない。そもそも忌まわしいという字を名前につけることは可能なのか? 親ももし一緒に来ているのなら少し注意が必要かもしれない。
椅子から立ち上がり診察室の扉を開ける。待合室の隅には髪の長い女性と、隣に父親とおぼしき男性が座っていた。他に来ているものはいなかった。
「八乙女忌子さん。こちらに入ってください」
声をかけるとふたりは立ち上がり診察室へと向かってくる。女性の表情は少し暗いが歩いて診察室に来られることに安心する。歩くのも難しいほどの腹痛だと、中等症以上と考えた方がいいからだ。
診察室の椅子に彼女を座らせる。
「どうぞお父様もお座りください」
父親が後ろで立っていたので隅にある丸椅子へと促す。父親は失礼しますと一声かけて座る。思ったより真面目そうなお父さんだなと心の中で考える。
「おなかが痛いみたいだけど、いつ頃から痛くなったかな?」
問診する際は、今日はどうされましたとオープンクエスチョンで始めた方がいいとは言われているが、楠本の場合は予診票があるときはクローズドクエスチョンで始めることにしている。たまに問診票に書いてあるだろと怒る患者もいるからだ。
「えっと、夕方に寝ちゃって起きたらおなかが痛くなってました」
か細い声でうつむきながら話す。
「吐き気とか気持ち悪いとかはあるかな」
「いえ」
首を振りながら彼女は答える。そうなると胃腸炎の可能性は下がるか。腹痛の鑑別疾患である胃腸炎の順位を頭の中で少し下げる。ただ胃腸炎はまだ上位に入る。腹痛の患者では胃腸炎が圧倒的に多いからだ。
「あの? 生理の可能性ってありますか」
後ろから父親が口を挟む。生理という言葉を聞いて訝しむ。父親から生理を心配する声を聞くことはあまりない。
「妊娠の可能性はありますか?」
女性による腹痛の場合、妊娠の可能性もかならず挙げる。いきなり質問することはあまりないが、父親から生理について聞かれたため先に確認する。もし妊娠による腹痛だったら小児科でも内科でも対応できず婦人科のある病院に送る必要があるからだ。
「いえ。そういうわけではなくて。うちは神社なんですが、生理があると巫女として働いてはいけないんです」
父親の言葉に少し拍子抜けするとともに、また家族への警戒度が少し上がる。生理と巫女の関わりはよくわからないが、父親の態度からは娘というよりは仕事ができるかどうかを心配しているように思えたからだ。
「どうかな? 生理は来てる?」
流れで彼女に質問する。デリケートな質問だから身体診察のときに聞こうと思っていたが、父親が心配しているなら聞かないわけにはいかない。
「いえ。ピルも飲んでいるので、この時期はないと思います」
特に彼女の表情は変わらない。ピルを飲んでいるということは普段から生理が重いのだろうか。
他にも既往歴や家族歴など、父親がいないと聞けないことを確認しつつ頭の中で鑑別疾患のリストを更新していく。
「じゃあ診察させてくださいね。お父様は待合室でお待ちください」
促されて父親は診察室から出ていく。少し不安そうに彼女は待合室を振り返るが、扉が閉じるとこちらに向き直った。
聴診器を取り出して心音と呼吸音を聞こうとする。彼女が服を上げようとしたので「そのままで大丈夫」と声をかける。
左鎖骨の下あたりに聴診器を当て滑りこませ大動脈弁の閉じる音である第二音を聞く。
「じゃあ深呼吸して」ついでに肺尖部の呼吸音を左右で確認する。
「少し服を前に引っ張ってもらえるかな」
自分のシャツの裾を前に引っ張って同じようにしてもらうように指示する。
今度は服の下から聴診器を入れて心尖部の音を聞く。
「今度は後ろを向いて」
同じように服の下から聴診器を入れて背中から肺全体の呼吸音を確認する。
「またこっちを向いて口を開けてくれるかな」
振り返った彼女は指示通りに口を開ける。診察室にあるライトを取り出して喉の奥を照らす。咽頭の腫れはない。
「次は首に触るね」
首回りのリンパ節を確かめる。ついでにつばを飲み込むタイミングで甲状腺に触れる。どちらも腫れはない。
腹痛が主訴のため、これらの診察はスクリーニング的なものだ。明らかな異常がないことを確認するのも大事だが、むしろこれから診察を始めますよという儀式的な意味合いが強い。
いきなりおなかに触り始めるよりは少し距離がある聴診器で診察を始め、徐々に触れていく方が安心してもらえることが多い。
「じゃあ今度はおなかを診るからベッドに横になってくれるかな」
彼女は靴を脱いでベッドに上がり横になる。そのタイミングで看護師が足元にタオルをかける。
「すこし膝を曲げてくれるかな」
おなかの緊張を減らすために足を体育座りのように曲げてもらう。おなかを出して皮疹がないかをさっと確認したら聴診器を当てる。おなかが動く音もよく聞こえ、腸蠕動音は特に亢進も減弱もしておらず正常だ。
「おなかが痛いのは具体的にどこらへんかな」
彼女がみぞおちのあたりを指差す。心窩部ならどちらかというと胃や十二指腸の痛みか。痛みが感じるところを最初は避け、婦人科疾患でよく痛む下腹部や、虫垂炎のときに痛む臍周囲や右下腹部を押してみる。
「痛いところはあるかな」
彼女は首を振る。
「じゃあみぞおちのところを押すね」
軽く触れるくらいでは痛みを感じる様子はないが、少し押してみるとわずかに顔がゆがむ。
「じゃあ今度は押した後にぱっと離すから押したときと離したときの、どっちが痛いか教えてくれるかな」
みぞおちをぐっと押してからすぐに離す。
「押したときの方が痛いです」
反跳痛はない。痛みの強さからも腹膜炎の可能性はまずないだろう。
「今痛いところは胃のあたりなんだけど、ごはんとかは食べられてる?」
診察しながら声をかけると忌子は首を振った。
「そういえば朝ごはん食べてから、なにも食べていないです」
「そうなの? その巫女の仕事とかで忙しかった?」
「いえ。今日は期末試験で学校に行ったんですけど……」
そういって言いよどんでしまう。もしかして試験の結果があまり良くなかったのだろうか。もし厳しい家庭なら、それはストレスになってもおかしくはない。
「そっか。高校生だと試験も難しいよね」
答えても、彼女は曖昧な様子でうなずく。診察している間、彼女はずっと素直に応じてくれていた。その様子からは何か隠していることがあることが伝わってくる。
おそらく緊急性の疾患の可能性は低い。軽い胃炎か、ストレスによる腹痛の可能性が高いだろう。あとはその原因まで踏み込むべきか。
夜間診療所は緊急性の疾患の有無を見極める場所だ。問題なければ最低限、夜間を乗り切れる程度の薬を処方する。そうしないと夜間診療所を病院代わりに利用してしまう患者が増えてしまうためだ。
そのためにやるべきことは緊急性がないということを伝え安心させること。そして夜を乗り切る方法を伝えることだ。そうすれば夜間診療所の医師としての役目は終えられる。
「何か大変なことでもあった?」
しかし、つい口をついて聞いてしまった。それくらいの話を聞いても問題ないだろう。幸い診療所は混んでいないし、なによりかかりつけの医師が診察しないことが気にかかっていた。症状が続くときは翌日にかかりつけに行くように伝えるが、それがこの子に関しては難しい気がした。
「えっと。大丈夫です」
この子は嘘がつけないんだなと確信する。本当になにもなければ素直になにもないですと答えることが多い。大丈夫ですという言葉の裏には、何か大変なことがあるけど耐えられるという本音が垣間見えていた。
「そっか。とりあえず重い病気があるとかではないから安心してね」
だからこそ、掘り下げることはできなかった。嘘はつけないが、言いたいわけでもない。その心理がさっきの返事から伝わってきてしまったから。
「お父さんを中に入れても大丈夫かな?」
ほっとしたような表情を見せて彼女はうなずく。家庭というよりは学校によるストレスが影響していそうだなと見当をつけた。
父親を診察室に呼び込み説明を始める。
「可能性が高いのは胃が荒れたりなどの消化器系による痛みです。ピルを飲んでいるということと、おなかが痛がる場所からも生理とか婦人科系の疾患の可能性は低い。もちろん初期症状の可能性は否定できませんが。あとは盲腸の初期という可能性もゼロではないです。その場合は右下の方に痛みが移動してくることがあるので、そのときは夜中でも救急病院に行ってみてください。痛みの経過がマスクされないように痛み止めではなくて胃薬を出しておきます。次の日まで症状が続くようなら必ず日中に病院に行ってくださいね」
来たときよりは彼女の表情は少し和らいだ印象がある。診察を受けたことで、少しでもストレスが緩和されればいいが。
ただ夜間診療所の医師にできるのはここまでだ。翌日以降は地域の医師たちが彼女のことを見てくれるだろう。
「忌子、あすは無理せず学校を休みなさい」
声をかけながらふたりは診察室を後にしていった。
「先生、ありがとうございます。助かりました」
看護師がお礼を言う。
「他に患者は来ていないですか」
「ええ。電話連絡も特にないですからゆっくりしていてください」
そう言われて聴診器を机に置く。
「ちなみにあしたはどこに観光されるんですか?」
「実はまた龍奉神社に行くんです。友人と一緒に来ているんですが、どうしてもまた行きたいと言われてまして」