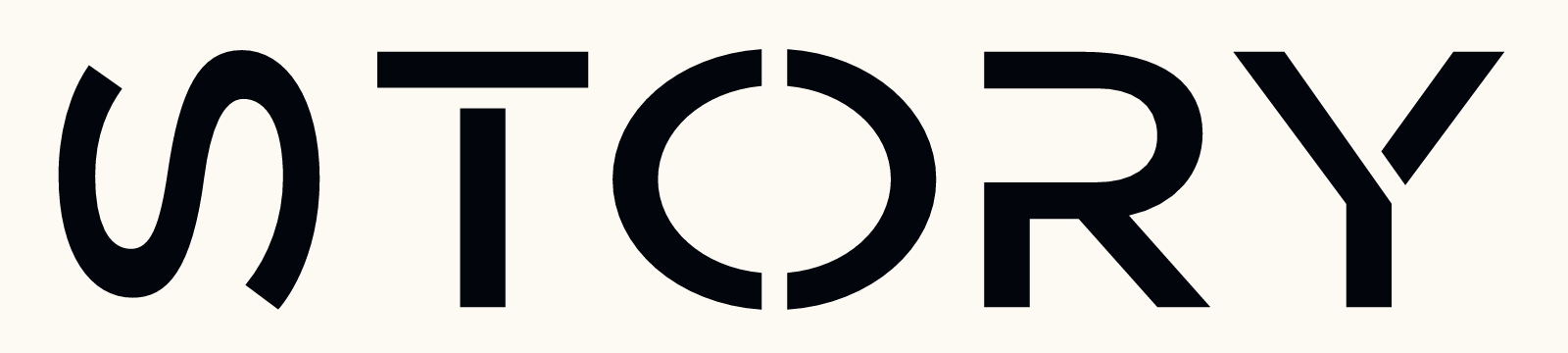第三話 急変発生
声が聞こえてきたのは先ほどまで鏑矢を放つ儀式が行われていた拝殿の前の広場からだった。急いで向かうと広場に横たわる人と、それを取り囲むように遠巻きに見る十人ほどの人が見える。駆け寄ると忌子の姿に気づいた女性が声をかけてきた。
「あの! 急に男の人が血を吐いて倒れてしまって」
それは巫女姿の忌子に対応を促すような態度だった。横向きに倒れている人に目を向けると男性の周りに広がっていく赤黒い血が目に入った。口の中から絶え間なく吐き出される血が少しずつ周囲へと広がっていく。その瞬間、忌子は身動きが取れなくなってしまった。血に近づいてはいけない。その思いが頭を占めていた。
動けずに倒れている人を眺めることしかできない。よく見ると、それは先ほどやじを飛ばしていた酔っぱらいの男性だった。赤ら顔だった顔色は色味が失われていき目を閉じている。それはただ単に酔っ払って眠っているわけではない。彼に宿っていた生命が地面に吸収されていくようだった。
「ねえ! 救急車呼んだ方がいいんじゃない!」
ぼうぜんとしていると、いつの間にか忌子の横に立っていた美友紀に肩を揺さぶられる。秀俊と晴雄も横に立っているが、彼らもただ倒れている男性を眺めているだけだった。
「大丈夫ですか!」
そのとき突然、倒れている彼のもとに駆け寄る男性の姿が目に入る。年は三十代くらいだろうか。短めの黒髪でポロシャツとジーパンを履いた男性が地面にひざまずく。手に持っていたビニール袋からペットボトルやパンを取り出し地面に放った。
彼はビニール袋に手を突っ込むと倒れている人の肩をたたきながら呼びかける。しかし倒れている男性が反応する様子はない。
次に彼はすでに出し尽くしたのか血が出ることは無くなった口元に耳を近づける。同時に手首に触れたかと思うと、おもむろに倒れている男性を仰向けにした。そしてビニール袋に手を突っ込んだまま男性の胸のあたりを押し始めた。
「白いブラウスの女性の方。すぐに救急車を呼んでください! あとそこの青いシャツの人! AEDを探してきてください」
彼は胸を押しながら指示を出し始める。その指示の仕方は、以前授業で習った心肺蘇生法のやり方だった。目の前で倒れている人は心臓が止まっている。その事実が頭の中に入ってきても、忌子の足は動かなかった。
「そこの男の子ふたり! 手伝ってくれる!」
彼がこちらに向かって声をかけてくる。もしかして俺らのこと? そんな目をしながら晴雄が秀俊を見つめている。
「ほら! 早く!」
せかされてふたりが慌てて男性のもとに近づくのを忌子は眺めていることしかできなかった。倒れている男性は目を閉じて、思い切り胸を押されているのに痛がる様子もなく微動だにしていない。
「君、心臓マッサージってやったことある?」
男性が胸を押しながら秀俊に声をかける。
「いえ」
「じゃあ教えるから代わってくれるかな」
秀俊が戸惑った様子を見せながらもうなずいているのが見える。
「じゃあ僕の手の真横に同じように手を組んで準備してくれる? イチニのサンの合図で僕が横にどくから、間をなるべく空けないで同じように胸を押して」
秀俊は言われるがままに彼の横に膝立ちで座り手を添える。
「じゃあいくよ。イチニのサン!」
声と同時に彼が横にどく。秀俊が彼の胸の上に手を添えているが、胸を押す様子がない。
「ほら! 胸を押して!」
声に促されてようやく胸を押し始める。しかし先ほどの男性の心臓マッサージに比べておっかなびっくりやっている様子が離れて見ていてもわかった。
「もっと強く押し込んで! それと腕を伸ばして体全体で押して!」
男性の指示に合わせて秀俊が腕を伸ばして心臓マッサージを続ける。先ほどよりも倒れている男性の胸が沈みこんでいく。
「その感じで続けて! あとは力を抜くときにきちんと胸が持ち上がるように」
彼は土下座するかのように顔を下げ、倒れている男性の胸の高さを確認していた。
一分程度で秀俊の心臓マッサージに力が入らなくなっていくのが見えてきた。
「よし! じゃあまた僕が代わるよ」
男性が声をかけると、秀俊の手が止まる。すると彼は割り込むように入り、すぐに心臓マッサージを再開した。彼の心臓マッサージは秀俊がやっていたものと比べると鬼気迫っていた。
身を乗り出し、杭を打ち込むかのように自分の腕と体で男性の胸を押し込んでいる。リズムも一定で、心臓を動かすという気迫が彼の中に宿っているようだった。
「君も彼の友達かな? 同じように代わってくれる?」
また一分ほど過ぎたところで彼は晴雄にも声をかけた。晴雄もこわごわであるが同じように指導を受けながら心臓マッサージを始める。見比べてみるとまったく違った。怖がっているのか、身を引いていて腕だけで押している。その分、力が胸に入っていない。案の定、身を乗り出すように言われ体全体で胸を押し始める。
三人で交代しながら心臓マッサージを続けているのを忌子は眺めることしかできなかった。疲れを感じて力が入らなくなったタイミングで交代するように男性から指示が入る。五巡ほどしたところで遠くから救急車のサイレンが聞こえてきた。
境内に救急隊員がストレッチャーと一緒にやってくる。
「代わります」
救急隊員に言われ心臓マッサージをしていた秀俊が離れる。すると救急隊員はすぐに心臓マッサージを始めた。救急車がやってきた安心感で忌子の体から力が抜ける。ずっと立ち尽くしていただけだが、それでも全身に力が入っていたことに忌子は初めて気がついた。